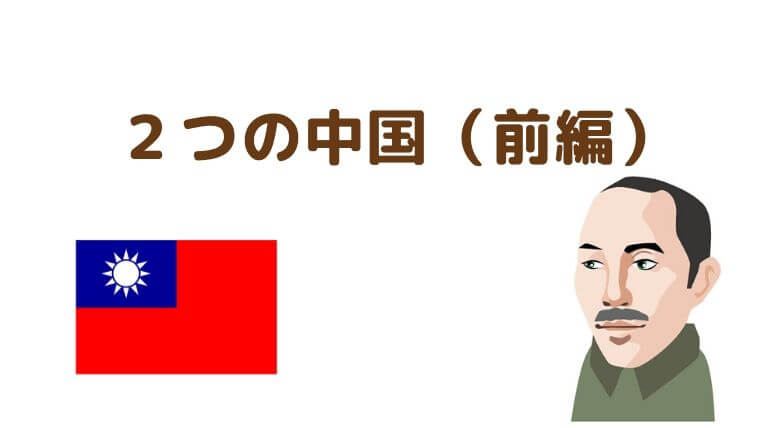幕末の動乱①
Contents
幕末を読み解く
前回は、欧米諸国のアジア侵略についてお話ししました。
幕末になってなぜ欧米諸国が日本へ接近してきたのかがお分かりいただけたと思います。
鎖国体制の中、日本は外国の発展からだいぶ遅れを取ったんですね。
黒船を見たときはほんと驚いたろうね。
さて、今日は外国の圧力を受けた日本がどのような行動を取ったのかを見ていきます。
このあたりは実にややこしい話になりますので、よく前回までの話を思い出していきましょうね。
老中、水野忠邦による天保の改革のさなか、隣の清(中国)がイギリスとのアヘン戦争に敗れました。
とうとう日本にも欧米諸国の脅威が近づいてきていたのです。
国内では、江戸の3大改革は抜本的な改革には至らず、各地で一揆や打ちこわしが多発していました。
幕府の権威と信用が落ち込む中、薩摩藩や長州藩は、独自の手法で財政を立て直しました。
これらは雄藩(ゆうはん)と呼ばれ、幕府の中でも特に発言力を持ち、一目置かれる存在になります。
1853年、アメリカのペリーの黒船が浦賀に来航しました。
翌年、日本はアメリカの圧力に屈し、日米和親条約(にちべいわしんじょうやく)を締結(ていけつ)します。
200年以上続いた鎖国体制が崩壊した瞬間でした。
さて、ここで重要なキーワードが出てきます。
不平等条約(ふびょうどうじょうやく)、尊王攘夷(そんのうじょうい)思想です。
1854年にアメリカと結んだ日米和親条約により、下田と函館の2つの港を開港しました。
この条約によって、日本の鎖国体制が崩壊しました。
問題は1856年にアメリカのハリスと結んだ日米修好通商条約(にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく)です。
これは関税自主権(かんぜいじしゅけん)がなく、領事裁判権(りょうじさいばんけん)を認めるもので、不平等条約と呼ばれます。
関税とは日本への輸入品にかける税金のことです。
やよいさん、国産のお米が5キロで3000円だとします。
外国産のお米が5キロで1000円だったらどちらを買いますか?
国産のほうが美味しいとは思いますが、その安さなら外国産のお米を買うと思います。
そうなりますよね。そうなると国内の農家がお米が売れなくなり大打撃を受けます。
確かにそれは問題だ。
そこで日本は、外国産のお米に関税をかけます。
1500円の関税としましょう。合わせて2500円になりました。
どうします?やよいさん。
それぐらいなら、国産のほうが美味しいので、3000円出して国産を買います。
そうか、500円ぐらいの差なら迷う人も出てくるね。
やっぱり500円安いからって外国産を買う人もいるもんね。
極端にどちらかが売れなくなることはなくなるね。
このように関税をかけて国内の産業を守り、貿易相手国の商品もしっかり購入する。
両者のバランスが取れる。そしてこの関税は輸入する側が自由に決めていいのです。
こうして各国は関税を決め、貿易相手国と自国の産業を守るのです。
では、関税自主権がないと言うことは・・・・。
先ほどの例のように、国産のお米は全く売れなくなります。
結果、日本の農家は大打撃を受けます。
それはひどすぎる。
領事裁判権を認めるとはどう言うことですか?
外国人の犯罪はその外国人の国の法律で裁くと言うことです。
通常、外国人が日本で犯罪を犯せば日本の法律で裁くことになります。
しかし、領事裁判権を認めてしまうと、その外国人を日本の法律では裁けなくなります。
では、日本の法律なら重罪でも、外国の法律では軽犯罪扱いだったら・・・。
極端な話、外国人が日本人を殺害したとします。
日本の法律なら死刑だとしても、その外国の法律では罰金刑で済むとしましょう。
そ、それはかなりやばい話だね。
外国人による犯罪が増えてしまいますね。
関税自主権がなく、領事裁判権を認める。
これがいかに理不尽な内容かおわかりいただけましたか?
これらが盛り込まれている条約。それが不平等条約です。
なぜ不平等条約を結んだのか
で、でもちょっと待って。
どうしてそんな一方的に日本は不平等条約を結ばせられたの?
確かにそう思います。
もっと話し合いで、アメリカと日本のお互いにとって良い条件の条約を結べなかったのですか?
そこはやはり力の差です。
黒船の脅威は日本に絶望感を与えました。
日本としては戦わずして敗北を実感したのです。負けたほうが不利な条件を飲む。
それが戦争の終わり方なんです。
そ、そうか。下手すりゃ攻め込まれてたんだもんね。
不利な条件でもとりあえずそれを呑むしかなかったんですね。
ところが、アメリカと不平等条約を結んだために、次々に諸外国と同様の条約を結ぶことになります。
オランダ、ロシア、イギリス、フランスです。
これを安政の五か国条約と言います。
ゲゲ!?そんなに!?
そして、この条約を結ぶ方法があまりよくなかった。
そのために以後、波紋を呼ぶことになります。
攘夷(じょうい)か開国か
アメリカを初め他4ヶ国と不平等条約を結んだ日本。
これを良しとしない勢力が攘夷派です。
外国人を敵として排除することが攘夷でしたね。
前回やったな。
対して外国に対して国交を結ぶのが開国派です。
1856年時点では幕府と薩摩藩が開国派です。
1856年時点と言うのは?
開国派と攘夷派は時期によって微妙に変わってきます。
それが幕末のややこしいところでもあるんです。
薩摩藩も開国派だったのですね?
薩摩藩は土地柄、欧米の驚異を目の当たりにしてきました。
西洋技術を取り入れ、その結果、外国の脅威に備える。
そのような先進的な思想を持っていたのが薩摩藩です。
当時、欧米諸国の技術と力を目の当たりにした人々は、到底日本の国力では太刀打ち出来ないと確信し、外国の要望を受け入れ開国するしかないと考えました。
それが幕府であり薩摩藩です。
対して、黒船の話を噂話でしか聞かない人々は、不平等条約により、伝統ある日本を外国人の好きなようにはさせまいとしました。
これが攘夷です。
有名なところでは長州藩、元土佐藩の坂本龍馬などがいます。
そして第121代天皇の孝明天皇もその一人です。
孝明天皇も日本は神の国であるとし、断固外国排除の攘夷を主張します。
ただし、長州藩も坂本龍馬も、いずれ開国派に考えが変わっていきます。
現実を知れば知るほど、外国と敵対するのは愚かだとわかっていくのです。
現実を知る人が開国派。知らない人が攘夷派。
ただ、そんなに単純でもないのです。
長州藩も龍馬も、攘夷の心は捨てていません。
いずれ外国と対等に渡り合い、やがてはそれを凌ぐ力を持つ。
そのためにいったん国を開いて、外国の文化を取り入れようと考えるのです。
なるほど。ただ参った降参!じゃなくていずれ勝つための開国なんだな。
薩摩藩の思想に近いものがありますね。
彼らを開国攘夷派と言います。
現実を知らず、ただ「外国人を倒せ!開国反対!」と叫ぶ下級武士達の純粋な攘夷派とは違います。
わ、わからん!?
ここは、そこまで細かく覚える必要はありません。
ただ、幕末はいろんな藩や人物が出てきますのでわけがわからなくなります。
話をわかりやすくするために、分類しているだけなので安心してください。
日本の行く末を考える時代ですから、いろいろな考えを持った人達がいてもおかしくはないですよね。
そして尊王(そんのう)と言う精神。
これは天皇を尊ぶ心です。
この尊王はどの派であっても持っている精神です。
天皇を尊ぶ心。それは日本そのものですものね。
尊王開国、尊王攘夷。
みんないろんな考えがあるけど、天皇を敬い日本をより良くしようとする気持ちは一緒なんだね。
そして、幕府の古い体制に従っていてはやがて日本はダメになる。
そのような考え方が各藩に浮上してきます。それが討幕(とうばく)です。
幕府を倒す思想です。
そのあたりを次回は詳しく見ていきますよ。