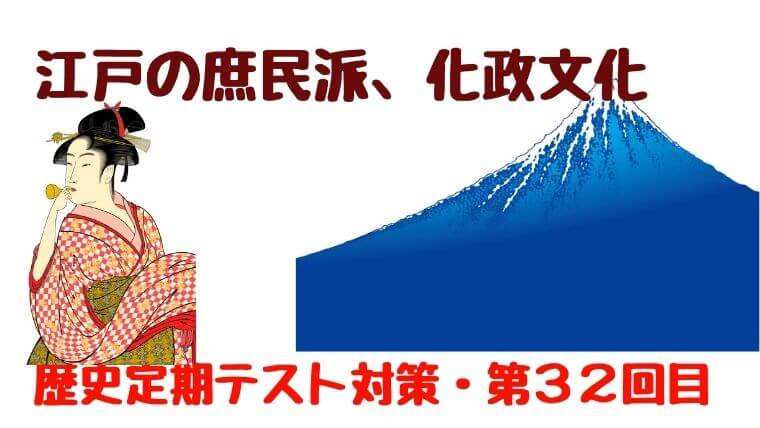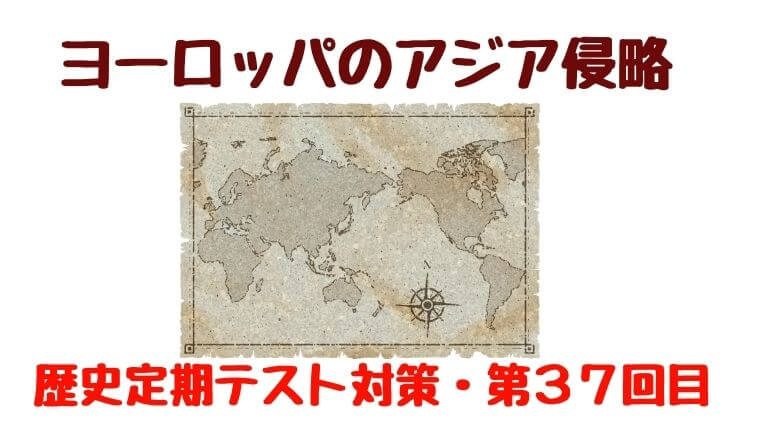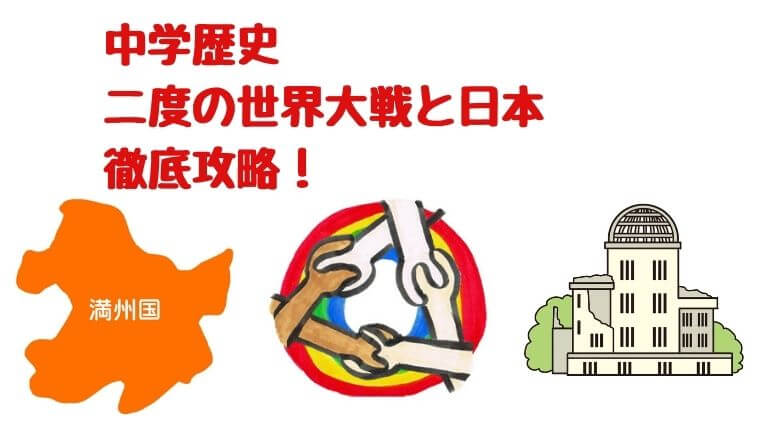桃山文化
Contents
桃山文化
中学歴史定期テスト対策の第23回目です。
教科書は110P~111Pです。
桃山文化です。
桃山文化は豪華で壮大な文化です。
大名や商人たちが権力や富を背景に、豪華な生活を送ったからです。
また、この時代は南蛮貿易も盛んに行われ、ヨーロッパ文化の影響が色濃く表れているのも特徴です。
桃山文化の特徴
桃山文化を代表するものに城(しろ)があります。
お城ですか?
支配者の権威を示すために、高く大きな城が作られました。
高くそびえ立つ天守(てんしゅ)
この天守(てんしゅ)こそが、桃山文化を象徴する城の作りです。
大阪城や安土城は立派な天守がありますね。
写真は姫路城(ひめじじょう)です。
5層の大天守と3つの小天守が結ばれています。

美しい白壁から白鷺(しらさぎ)城とも呼ばれました。
世界遺産にも登録されていますよ。
見ているだけで威厳が伝わってくるね。
城の室内には書院造(しょいんづくり)が取り入れられ、ふすまや屏風(びょうぶ)には華やかな絵が描かれています。
書院造は覚えていますか?
東山文化の足利義政の書斎などで使われた様式ですね。
武士を担い手とする簡素で気品のある文化です。
外は派手だけど、中は質素なんだね。
しかし、柱などは豪華ですよ。
ふすま絵や屏風絵などは派手やかな絵が描かれました。
作者は狩野永徳(かのうえいとく)や狩野山楽(かのうさんらく)が有名ですね。
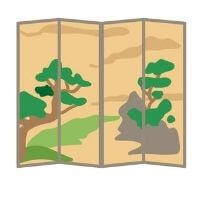
特に秀吉は黄金好きでしたからね。
大阪城の天守なども黄金が散りばめられました。
茶の湯を好んだ秀吉は、黄金の茶室なども作らせています。
黄金の茶室!!
派手派手ですね。
室町時代に茶の湯を飲む風習が中国(宋)から伝わりました。
そして桃山時代になると大名や商人たちの間でも大流行となり、政治の場としても使われるようになったのです。
ほえ~お茶が?

茶の湯と言えば、秀吉です。
ここで秀吉と茶の湯にまつわるエピソードを紹介しましょう。
豊臣秀吉と石田三成
秀吉と三成の出会いは、茶の湯がきっかけでした。
信長の下、大出世を遂げていた秀吉は、念願の一国一城の主となりました。
長浜城主です。
ある日、鷹狩りに出かけた秀吉は、帰り道にある寺に立ち寄ります。
寺で休憩をしていた秀吉に、寺の小僧が茶を持ってきました。
ぬるめのお茶は、喉がカラカラの秀吉にとってちょうどよく、秀吉は一気に飲み干しました。
すると小僧は2杯目のお茶を持ってきます。
今度は普通の熱さです。
これも飲みほした秀吉は、さらにもう1杯と所望します。
小僧は小さめの碗に熱めのお茶をいれ、持ってきました。
秀吉は、最後の3杯目を香と味を楽しみながら飲み干したそうです。
喉が渇いた秀吉に、1杯目から熱いお茶を持っていったらどうだったでしょう。
まずは喉を潤し、最後に本当の茶の味をあじわってもらう。
この気遣いに秀吉は大いに感心したのです。
この出来事をきっかけに、小僧は秀吉に召し抱えられるようになりました。
小僧の名は石田佐吉(いしださきち)
後の石田三成です。

秀吉の心をくすぐったわけだ。
やるな三成。
もうひとつエピソードを紹介しましょう。
千利休です。

利休は堺(さかい)の商人の出身です。
独自の美学のセンスから、茶の湯の道で天下一となった人です。
豊臣秀吉に仕えた利休は、時に戦場にまで呼ばれ、秀吉のために茶の湯を提供しました。
時には秀吉の相談役として、良好な関係にあった利休と秀吉ですが、最後は秀吉により切腹を命じられます。
諸説がありますが、秀吉との美意識の違いから関係が悪化したとも言われています。
利休が求めたのは名誉や富よりも、内面の精神性です。
表面だけが美しい物はただのメッキ。
内面から湧き出てくる美しさに美があると考えます。
利休はこうして、質素なわび茶の作法を完成させました。
利休が求めたのは質素。
茶室も質素であり、茶器も質素です。
しかし、内面からはどことなく力強さを感じられる。
そのような美しさを求めたのです。

ところが秀吉はと言うと、大の派手好きです。
周囲には財にモノを言わせ、黄金を敷き詰め、外見の華やかさを演出しました。
利休のどことなく気品あふれる美しさに、秀吉は完全に自分の美を否定されたと感じたのかもしれません。
徐々に利休が力をつけ、秀吉の政策に口を挟むようになってきたなどの説もありますが、結局、利休は秀吉によって切腹させられてしまいます。
秀吉は晩年に残虐性を帯びてきたとする話がありますが、利休の一件もその一端なのかもしれません。
若き日の秀吉は、寛大な心で多くの人々の心をつかんできました。
権力や名誉を手にすると、人は変わってしまうのかもしれません。
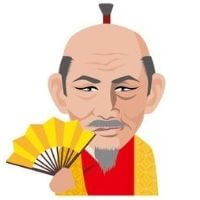
お茶で切腹なんて・・・。
ただ、この当時の茶の湯はひとつの文化を形成しています。
高価な茶器など、一つの大名の国に匹敵するほどの価値を持つ物もあったのです。
茶器が一国!?
恩賞で茶器をもらうことは、武将にとって名誉なことだったのです。
そしてその茶器をもって客人を振舞う。
戦国武将たちのこだわりが見えてきますね。

豪華で壮大な桃山文化。
その中には、利休の追求した質素な文化も存在することを覚えていきましょう。
命がけで追求したんだもんな。
桃山文化は、社会全体が日常を楽しむ風習が芽生えた時期です。
出雲のお国(いずものおくに)が始めたかぶき踊りが人気でした。
琉球(沖縄)から伝わった三線(さんしん)

これをもとに作られた三味線(しゃみせん)に合わせて、浄瑠璃(じょうるり)などが楽しまれました。
桃山文化とヨーロッパ文化
桃山文化は南蛮貿易(なんばんぼうえき)とは切っても切り離せない関係です。
ヨーロッパの珍しい物が入ってきた時代ですよね。
パンやカステラ、カルタ、時計などもこの時期に日本に伝わったのです。
天文学や医学、航海術など、新しい学問も伝わりました。
なんだか楽しそうだね。
特に活版印刷術(かっぱんいんさつじゅつ)が伝わったことは大きいです。
印刷の技術が誕生し、聖書などの書物が印刷され、布教に使われました。
印刷か!すごい!
平家物語など、日本の書物がローマ字で印刷され、日本人以外でも楽しめるようになりましたよ。
今では当たり前に海外の本も読めるけど。
当時としては、感動的な出来事だったでしょうね。
ひだのあるエリ付きの洋服を着る風習も広まりました。
ヨーロッパ風の装飾品を身に着けたり。

こうしたヨーロッパの影響を受けて成立した芸術や流行。
これらを南蛮文化(なんばんぶんか)と言います。