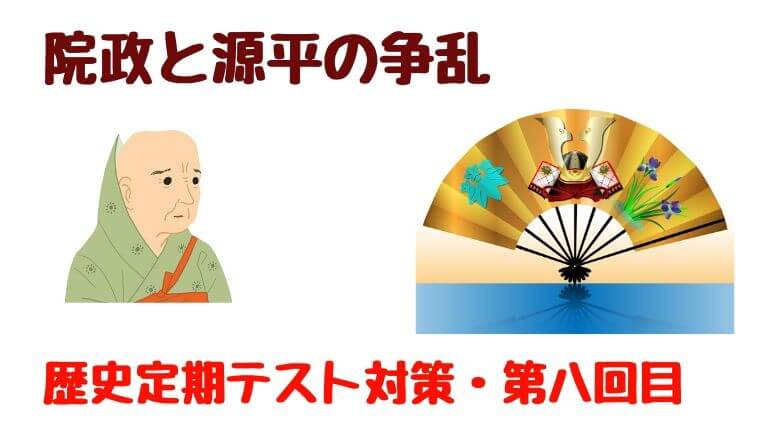幕末の動乱③
こんにちは。今日は江戸幕府が崩壊に至る決定打、薩長同盟(さっちょうどうめい)のお話です。
まずは前回のおさらいです。
幕府の大老井伊直弼により、幕府を批判する人達を処罰する安政の大獄が行なわれました。
安政の大獄で幕府に批判が高まり、井伊直弼は桜田門外で暗殺されました(桜田門外の変)
各地で幕府の体制に不満が高まり、攘夷開国の動きが高まりました。
幕府の外国に対する弱腰姿勢ではダメだ。
しかし、今のままでは外国には勝てない。
だからいったん開国はするがいずれ外国の技術を学び、外国を打ち倒す力を持とうとするのが攘夷開国です。
ここに来て幕府の威信は一気に崩れ始めました。
そこで、幕府が取った策が公武合体です。
こうぶがったい?
公武合体(こうぶがったい)
公武合体とは、幕府と朝廷が力を合わせて政治を行おうと言う意味です。
今さら感がすごくあるな。
幕府は桜田門外の変で大老が暗殺されたり、もはや将軍家としての威信を保つことが出来なくなりました。
「幕府は朝廷と共にある」
この体面を保ち、威信を回復しようとしたのです。
そうは言っても、朝廷は無視されて日米修好通商条約を結ばれてしまったんですよね?
素直に受け入れないと思いますが。
そこで幕府が考えたのが、14代将軍家茂と孝明天皇の妹、和宮(かずのみや)との婚姻です。
な、なんと!結婚!
ひどい。そんなことのために結婚だなんて
しかも、和宮には既に婚約者がいたのですが。
政治のためならば致し方ないのでしょう。
ますますひどい。
幕府は威信を復活させたい。
そのためには幕府は朝廷と共にあることを世に知らしめる必要がある。
朝廷としては攘夷を貫きたい。
そのためには幕府に開国政策を中止してもらい、攘夷を実行してもらいたい。
その利害が一致して婚姻は成立します。
けど、そんな簡単に幕府は方針変更するんですか?
安政の大獄までしておいて。
とりあえずは攘夷をすると約束し、婚姻を成立させます。
しかし、幕府には攘夷をする気はさらさらなかった。
公武合体さえ成し遂げられれば良いと思ったのです。
そんな都合の良いことってある!?
孤立する長州藩
こうして公武合体はなりましたが、幕府はなかなか攘夷を実行しません。
幕府としては、攘夷をする気はさらさらありませんでしたから当然ですね。
黙ってないよね。朝廷は。
そこで動き出したのが長州藩です。
話が前後してしまいますが、前回お話しした下関戦争は、攘夷の約束を守らない幕府にしびれを切らしたために、長州藩が動き出した戦争です。
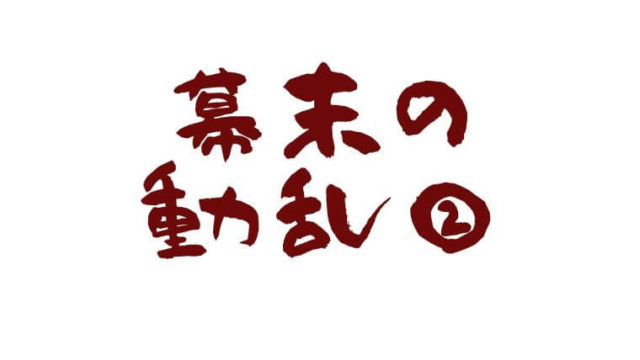
あ、あのアメリカとかイギリスにコテンパにやられた。
それがきっかけで長州藩は無謀な攘夷はやめて、いったん外国の技術を手に入れようとするんでしたね。
攘夷開国だ!
そして下関戦争の同時期に長州藩は京都でクーデターを起こしています。
京の宿屋「池田屋」
ここで長州の浪士達が集まり、孝明天皇を幕府から奪還する計画を立てます。
攘夷に踏み切らない幕府に対し苛立ちが高まる長州藩は、孝明天皇を連れ攘夷を果たすための大義名分を得ようとしたのです。
しかし、これは事前に幕府側に漏れてしまい、池田屋は襲撃されます。
襲撃したのが有名な新撰組(しんせんぐみ)です。
主に京の治安や将軍の護衛を任された。
倒幕思想の高まりとともに、京の町では、攘夷運動が過激化していた。
その京の治安を守るために幕府側が組織したのが新選組である。
近藤勇、土方歳三、沖田総司などがいる。
主に農民や町人となっていた浪士達の集まりだが、剣の腕が立ち京の攘夷派の取締にあたった。
新選組の活躍で長州側は敗北します。
これを「池田屋事件」と呼びます。
しかしその後、長州藩は武力で京の御所を攻め、天皇を連れだす計画を立てます。
しかしこれも薩摩藩や会津藩により徹底的に潰されてしまいます。
これが蛤御門(はまぐりごもん)の変です。
結果、長州藩は下関戦争に敗れ、池田屋からの天皇奪還計画の失敗。
続く蛤御門で大敗したことで朝敵(ちょうてき)とされてしまいます。
朝敵とは、朝廷の敵と言う意味です。
長州藩は天皇を味方にし、幕府を朝敵としようとしました。
しかし、計画がことごとく失敗し、自身が朝敵にされてしまったのです。
そして、蛤御門の変で戦った薩摩藩との関係も修復不能になります。
薩長(さっちょう)犬猿の仲と呼ばれる理由はそこにあります。
長州藩、孤立しちゃったね〜
薩摩藩
薩摩藩は戦国大名の島津家が藩主です。
鎖国期から琉球を中継地とした密貿易を行い、藩の財政は潤っていました。
雄藩として幕府の中でも力を持つ薩摩藩でしたが、土地柄もあり、西洋文化との交流により最新鋭の武器を手にするなど、古い体質の幕府の中にありながら異質な雰囲気を出していました。
生麦村(神奈川県横浜市)において薩摩藩の大名行列を横切ったイギリス人に対し、薩摩藩士が切りつけ死亡させた事件がおきました。
これに激怒したイギリスは薩摩藩を攻撃します(薩英戦争)
結果、薩摩藩は敗北しましたが、なかなかの戦いぶりに驚いたのはイギリスです。
落ち目の幕府よりも薩摩藩と関係を良くしたほうが良いと踏んだイギリスは薩摩藩に接近します。
これを機に薩摩藩はイギリスから最新鋭の武器を購入したり密貿易を始めました。
薩長同盟(さっちょうどうめい)
そしていよいよ今日の本題です。
薩長同盟です。
薩摩藩と長州藩は犬猿の仲でしたよね?
それがなぜ同盟を結んだんですか?
ここで登場するのが勝海舟と坂本龍馬です。
勝海舟は幕府の人間でしたが、常に日本全体の行く末を考える人でした。
勝は実際にアメリカに行き、その文化や技術に触れてきました。
そのような勝からすれば、幕府が日本を支える当時のシステムはただの時代遅れでした。
一族の世襲(せしゅう)で将軍が選ばれるのではなく、アメリカは国民の代表者として大統領が選出される。
民主主義の最先端を行くアメリカ。
日本もこうあるべきと考えたのが勝です。
同様のことが薩摩藩にも当てはまります。
薩摩藩はイギリスとの密貿易で外国の技術や文化を目の当たりにしていました。
表向きは幕府側の薩摩藩でしたが、次第に幕府の古い体制では日本は立ち行かなくなると感じ始めていたのが薩摩藩です。
ある時、薩摩藩の西郷隆盛は勝海舟と運命の出会いを果たします。
西郷は勝に諭されます。
「今、薩摩が戦うべき真の敵は誰なのか」
「日本の行く末にとって真に危うい存在は何なのか」
孤立する長州藩と力を合わせることで真の敵を倒し、日本を正しき道へ向かわせることが出来ると説得された西郷隆盛。
薩摩藩もついに勝の言葉に動かされたのです。
だとしても長州藩は薩摩藩を許すのでしょうか?
ここは利害の一致を図る必要があります。
長州藩の願いは何ですか?
えっと、攘夷と討幕だ!
薩摩藩も同じ目的を持つ同志と分かれば、長州藩としても同盟を断る理由もありません。
敵の敵は味方の理屈です。
薩摩藩が幕府を見限れば、長州藩と手を取りあえると言うことですね。
長州藩は朝敵とされていたため、まともに国内の商人から武器も購入出来ない有様でした。
しかし薩摩藩と組むことで長州藩はイギリスから最新鋭の武器が流れてきます。
何より憎き幕府を倒すことはできます。
それはそうだけど長州藩は薩摩藩を許せるかな?
そこで、長州藩に送られたのが坂本龍馬です。
龍馬の説得で薩長同盟は成立することになります。
勝海舟のお弟子さんだね!
そして幕府滅亡へ
薩長同盟を受け、幕府は長州藩を攻め立てます。
しかし、薩摩と長州の同盟で、他の各藩の戦意は著しく低下します。
各地で敗れた幕府軍。
そんな中、将軍家茂が亡くなり幕府は長州藩に停戦を申し込みます。
この苦しい情勢の中、15代将軍に徳川慶喜(とくがわよしのぶ)が就任します。
しかし、時の流れは既に薩長に傾いていました。
徳川慶喜は周囲のすすめで政権を朝廷に返すことを決断します。
260年続いた徳川幕府
この長期政権が血を流さず滅びることなど誰が想像したでしょうか(無血開城)
政権を朝廷に返したこの出来事は「大政奉還(たいせいほうかん)」と呼ばれます。
1867年でした。
いかがでしょうか。
第3回に渡る幕末の動乱でした。
複雑だけど、なんとなく一連の流れがわかりました。
でもさ、勝海舟って幕府の役人でしょ?結局幕府を裏切ったってことなの?
いろんな言われ方をされる人ですが、違います。
先ほども話しましたが、勝海舟は自分が置かれた立場で戦うのではなく、常に日本全体の行く末を考え戦う人でした。
幕府の人間ながら裏では薩長と怪しい動きをする。
本人も命をかけていたと思います。
自分の命以上に勝が案じたこと。それが「日本の行く末」だったのです。
次回からは最新章、明治時代から現代を解説していきます!