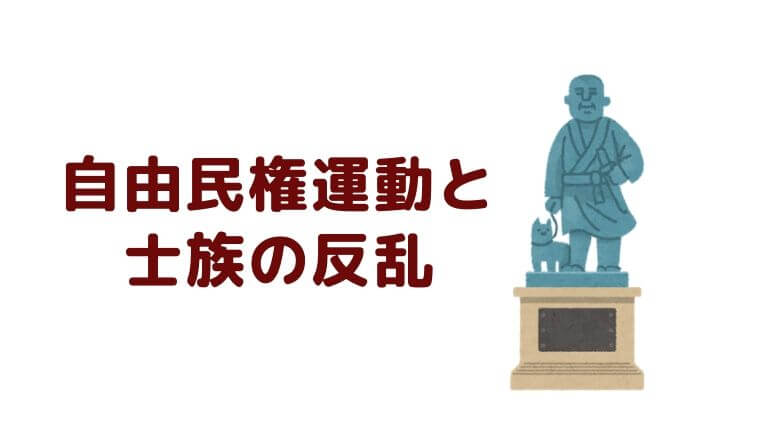孤立する日本(前編)
第一次世界大戦中の日本
なぜ第二次世界大戦が起きたかを、前回なぜ第二次世界大戦は起きたのかでお話しさせていただきました。
その流れを踏まえて、今日は日本の動向を中心に見ていきたいと思います。
まず21か条の要求を復習しましょう。
1 山東省の権益をドイツから引き継ぐこと
2 旅順・大連などの租借期限、南満州鉄道の期限を99年延長すること
3 南満州などの鉱山の採掘権を日本に与えること
第一次世界大戦でヨーロッパに各国の戦力が集中していた隙をつき、日本が中国につきつけた要求。
それが21か条の要求です。
中華民国が成立したばかりの中国では、反発するものの、この要求を受け入れざるを得ませんでした。
この当時(1914年~1918年)はアメリカと日本の経済が潤い、大きな利益を得ていた時期でした。
第一次世界大戦により、アメリカや日本の製品が飛ぶように売れたのです。
それはなぜ?
アメリカや日本はヨーロッパから遠く、戦争被害はほぼありませんでした。
ヨーロッパ諸国は戦争の影響で生産力が落ちていきます。
その結果、ヨーロッパから製品を輸入していた国々が、日本やアメリカから購入するようになったのです。
どこかが損すると、どこかが得をするんだね。
こうして日本には戦争成金(せんそうなりきん)なる者たちが現れます。
戦争のおかげで急に金持ちになった人たちです。
商売上手ですね。
第一次世界大戦によって日本国内は好景気になりました。
日本から各国への輸出が増大しました。一方、ヨーロパ諸国から日本への輸出はストップしてしまいました。
つまり、日本は輸出が増大し、輸入が激減したのです。
それはそれで問題では?
ところが、そこが日本人の勤勉なところです。
輸入が止まったことをきっかけに、輸入に頼らず自分たちで何とかしようとしたんですね。
そこで重化学工業を中心に新たな産業が発達し、日本は工業国の第一歩を踏み出すのです。
さすが日本人!!
鉄鋼の生産量が特に大きく増えたのですよ。
当時の景気の良さが伝わってくる気がします。
ところがあまり景気が良くなりすぎると、今度はインフレーションという問題が発生します。
物価が高騰することをインフレーションと言います。
物が飛ぶように売れることは通貨が世間に出回ることを意味します。
このように景気が良くなりすぎると、通貨量も増えていくことになります。
すると通貨(お金)の価値が下がりはじめるのです。
例えば1つ100円で買えたパンが、200円出さないと買えなくなる状態になります。
これを物の面から見れば物価が上がる。通貨面からみれば通貨の価値が下がる。
ということになります。
物価があまりに上昇してくると国民の生活は苦しくなってきます。
※第一次世界大戦で敗北したドイツに課せられた賠償金は、1320億マルクです。
ドイツの国家予算10年分のこの賠償金は、ドイツにハイパーインフレーションを招きます。
戦争で物資不足の中、賠償金支払いのために、ドイツ中央銀行は貨幣を大量に発行していきます。
当然通貨が増えすぎてるので、通貨の価値は下落します。
ドイツでは通貨価値が大暴落し、パンを一つ買うにもスーツケース一個分の貨幣を必要とするときもありました。
街中に価値を失った貨幣が散らばり、子供たちも貨幣で遊びだす始末でした。
国民の生活が苦しくなる中、1918年にシベリア出兵が始まります。
1917年、ロシアではレーニン主導のもとロシア革命が発生すると、資本主義国家はこぞってシベリアへ出兵しました。
社会主義革命の発生により、自国への影響を恐れたからです。
資本主義各国は、ロシア革命への干渉戦争を起こしました。
結局、ロシアの革命政府軍が勝利し、1922年に歴史上初の社会主義国家、ソビエト社会主義共和国連邦が成立します。
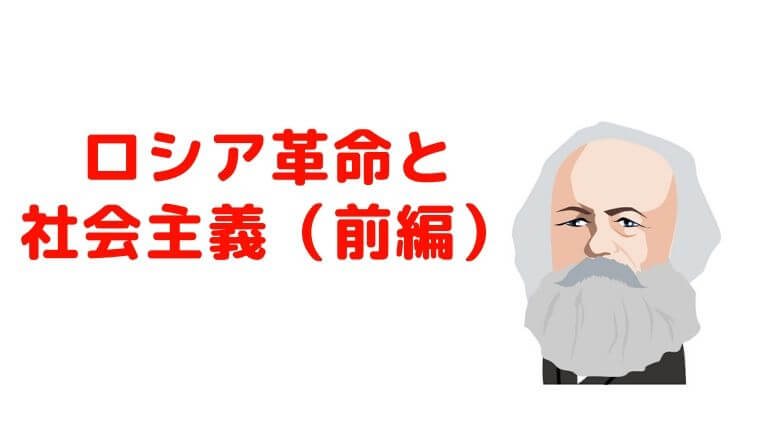

シベリア出兵を見越して、米の買い占めが起こりました。
実際に米不足になるであろうことを予測し、大量に買い占め高値で売りつけようとする人たちがいたのです。
ひどいですね。それ。
米の安売りを求める騒動(米騒動)は全国に広がり、政府は軍隊により鎮圧せざるを得ませんでした。
政府の信用もガタ落ちだね。
この米騒動で藩閥政府(薩摩長州出身者)の寺内内閣が退陣。
この時に新たな内閣総理大臣となったのが原敬(はらたかし)です。
本格的な政党内閣の誕生でした。
アジアの民族運動
第一次世界大戦が終結し、パリ講和会議では民族自決が唱えられましたが、アジアやアフリカでは依然として植民地支配が続いていました。
1919年、日本の植民地支配下に置かれていた朝鮮では民族自決の影響を受け、三・一独立運動(さんいちどくりつうんどう)が広がりましたが、朝鮮総督府に武力で鎮圧されています。
同年、山東省の返還要求が通らなかった中国は、帝国主義へ対する反対運動を展開しました五・四運動(ごしうんどう)
この運動をきっかけに孫文は中国国民党を結成し、中国共産党と協力して(国共合作)国内統一を図り、帝国主義への抵抗を強めようとしました。
山東省は結局1921年のワシントン会議により、日本から中国へ返還されます(ワシントン体制)
昭和時代へ
さて、いよいよ時代は昭和へと入って行きます。
大正最後には、国内の政治のあり方も大きく変わってきました。
まずは憲政の常道(けんせいのじょうどう)です。
藩閥政治から原敬の政党政治に変わったのが1919年のことです。
本格的に政党政治の時代に移り、加藤高明内閣が成立した1924年からは憲政会と立憲政友会の二大政党が交互に政権を担当することになりました。
これを憲政の常道と言います。
もうひとつは1925年の普通選挙法の成立です。
25歳以上の男子すべてが選挙権を持つものです。税金の制限がなくなったのですね。
このときはまだ女性には選挙権がありませんでしたね。
同じ1925年に定められた治安維持法(ちあんいじほう)も重要です。
1925年、治安維持法が制定されました。
これは国内の共産主義者への取り締まりを強化されるものでした。
1922年に社会主義国家であるソビエト社会主義共和国連邦が成立しました。
資本主義各国は社会主義思想が自国内に広がることを恐れました。
ドイツのヒトラーなども共産主義には厳しく取り締まりを行っています。
日本もこうした考えから、治安維持法を定め、共産主義の取り締まりに力を入れたのです。
これらが大正時代最後の出来事です。
そしていよいよステージは昭和時代へ入っていきます。
昭和恐慌(しょうわきょうこう)
第一次世界大戦中は好景気だった日本も、関東大震災や1927年のアメリカから始まる世界恐慌の影響を受け慢性的な不況に陥っていました。
1930年頃本格的に始まった昭和恐慌ですが、アメリカ同様に銀行が休業したり企業が倒産し各地に拡大して行きました。
銀行が立ち行かなくなれば国民は不安にかられ、ますますお金を使うことをためらいます。
こうしてお金が流通しなくなることにより、さらに不況を悪化させることになります。
そこで政府が行ったことが銀行への貸付です。
日本は日本銀行という国家が管理している銀行で紙幣発行等を行っています。
その日本銀行で大量に紙幣を印刷し、銀行に貸付けて国民の不安を取り払おうとしました。
ひとまずはこの案は成功しましたが、長引く不況の脱出口が見えず、根本的な問題解決には至りませんでした。
この時に印刷した紙幣は、急きょ印刷したために裏側は白紙という実にお粗末な紙幣でした。
裏が白紙って。怪しくて使えないね(笑)
でもとりあえずは落ち着いて良かったですね。
満州事変(まんしゅうじへん)
世界各国が世界恐慌の対策を行う中、植民地を持たない日本は本格的に満州支配に乗り出しました。
そんな中、ある事件が満州で発生します。
1931年、柳条湖(りゅうじょうこ)で南満州鉄道のレールが爆破される事件が発生しました。
関東軍(満州に置かれた日本の陸軍)はこれを中国軍のしわざによるものとして攻撃を開始し、満州の主要地域を占領しました。
1932年関東軍は清の最後の皇帝であった溥儀(ふぎ)を元首とする満州国の建国を宣言しました。
ほ、ほんとに中国のしわざだったの?
恐らくは関東軍(日本)のしわざでしょう。日本は満州進出の口実が欲しかったのです。
中国は国際連盟に日本の満州国宣言は侵略行為だと訴えました。
そりゃそうなるよね。
この後国際連盟は、リットン調査団の報告に基づき、日本軍の満州からの撤退を勧告します。
満州国の成立を侵略行為とみなしたのです。
日本は応じたのですか?
日本は反発し、国際連盟を脱退しました。
なんだかやばそうな予感・・・・。
こうして日本は世界から孤立していくことになります。
次回は、さらに踏み込んで日本国内の様子を見ていきましょう。