日本の産業革命と公害
日本の産業革命
今日は日本における産業革命を中心にお話します。
そう言えば、ここのところずっと戦争中心のお話でしたね。
日本における産業革命は1900年頃に始まりました。
ヨーロッパに比べると実に100年以上遅れて始まっています。
鎖国をしていたから仕方ないけど、相当な遅れだね。
ようやく日本にも蒸気機関の技術が伝わったのが1800年代の後半です。
電灯の設置も行われ、昼夜問わず働くことが強制されます。
良いことばかりではなかったんですね。
特に紡績業を中心に軽工業から始まった日本の産業革命ですが、日露戦争前後には重工業も発達します。
重工業の発展を支えたものは八幡製鉄所(やはたせいてつじょ)です。
やはたせいてつじょ?
日本が近代国家となるには鉄鋼材が必需品でした。
建築資材のみならず近代兵器にも多々使用されましたからね。
八幡製鉄所ができるまで、日本は外国から鉄鋼材を輸入していました。
コストがかかりすぎて思うように産業発展とはいかなかったのです。
国内で鉄鋼材が作れるようになったんですね。
かなり安上がりになるね。
自国で鉄鋼材を生産できるようになり、日本の近代化に拍車がかかります。
実はこの八幡製鉄所はある出来事がきっかけで造られました。何だと思いますか?ヒントは年代です。
1900年頃って何かあったかな。
1897年に下関条約が調印されています。
下関条約の内容を覚えていますか?
えっと、賠償金を3億円得たことでしょうか?
日本の国家予算の3倍だったね。
その資金を元に造られたものが八幡製鉄所なんです。
日本の産業革命は紡績業、製糸業などの軽工業から始まりました。
紡績業は綿花から糸を作りだします。
こうして作られたものが綿糸です。
紡績機械の導入、昼夜を問わないフル稼業に成功し、大工場が次々に作られていきます。
製糸業は蚕(かいこ)の繭(まゆ)から糸を作りだします。
こうして作られたものが絹糸です。
日本は、日露戦争後に最大の絹糸輸出国となります。
やがて八幡製鉄所が作られ重工業の発展につながっていきます。
重工業の発展が産業革命を一気に加速させます。
軽工業から重工業まで、大量生産が可能になった日本
産業の発展は資本主義経済を生み出します。
そこには労働者と資本家の社会が広がります。
労働者は資本家から賃金を得て働く、それが資本主義経済です。
資本家は利益を得て、さらに労働者を雇い大量生産を拡大して行きます。
これが資本主義体制です。
しかしここで大きな問題が発生します。
貧富の差です。
資本主義の発達により多くの労働者が生まれました。
しかし労働者の労働条件は劣悪でした。
長時間労働は当たり前、そして低賃金。
労働者の不満は高まり、労働条件を改善する運動が全国に広がりました。
それを受けて、政府は12歳未満の労働を禁止したり労働時間の制限を定めた工場法を制定しました(1911年)
しかし、労働者の暮らしや労働環境はあまり改善されませんでした。
こうした中、日本でも社会主義思想が成長していきました。
12歳未満も働かされたんだ。
ひどい労働条件だったんですね。
逆に資本家は裕福になっていきます。貧富の差が拡大して行きます。
そのような中生まれたのが財閥(ざいばつ)です。
資本家の中でも特に様々な業種(金融、鉱業、貿易)に進出し、日本経済を支配するグループが誕生しました。
一族からなるそれらのグループを財閥(ざいばつ)と呼びます。
三井、三菱、住友、安田などです。
これら財閥は、後に戦争に大きく関わったとして、アメリカGHQにより解体させられます。
財閥は解体されましたが、企業としては残り現代日本の経済に影響を与えています。
一部の人達がいい思いをする。
みんなが同じように共有できたらいいのに・・・。
それが社会主義思想です。
社会主義に関しては、別の機会にお話ししましょう。
[talk name=”奈良”]それが社会主義思想です。
社会主義に関しては、別の機会にお話ししましょう。[/talk]
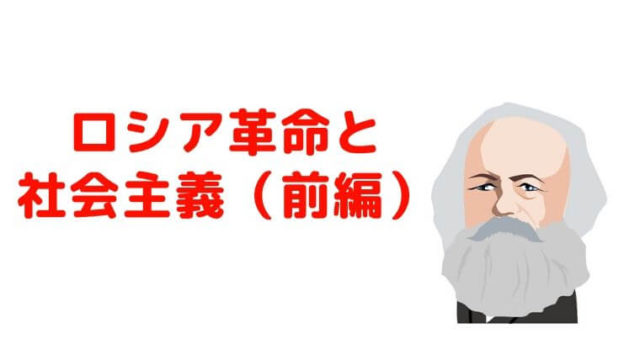

足尾銅山鉱毒事件
産業革命からの資本主義の発達は、多くの問題を生みだしました。
労働問題と貧富の差ですね。
他には公害問題があります。
いろいろ問題が出てくるんだね。
産業の発展と公害は切っても切れない関係なんです。
例えばイギリスの産業革命では、石炭が多量に使われ大気汚染の公害を招いています。
日本の公害はどのようなものがあったのですか?
有名なところでは足尾銅山鉱毒事件があります。
栃木県日光市に足尾銅山があります。
足尾銅山は幕府直轄地として古くから銅が採掘されてきました。
江戸時代後期には採掘量が激減していましたが、明治時代になると、新たな加工技術により、また採掘量が増加しました。
銅を精錬する際の廃ガスにより、あたりは植林が枯れ果て、ハゲ山が出没しました。
木が育たなければ地盤が緩み山崩れを起こします。
植林が枯れ果て、洪水が起こりやすくなりました。
また河川から田に流れる川水は汚染されていて稲も枯れ果ててしまいました。
川水の汚染は当然漁業にも影響します。
これがいわゆる足尾鉱毒事件と呼ばれるものです。
足尾の人々は怒り、政府に訴えますがまともに取り合ってはもらえませんでした。
ひどい。どうしてですか?
足尾の被害よりも銅の採掘を優先したからです。
地元の人は納得いかないよね。
やがて大きな洪水が発生し、足尾の状況が明るみになります。
そこで立ち上がったのが
栃木県の衆議院議員田中正造(たなかしょうぞう)です。
田中正造は議会で幾度となく足尾の惨状を訴えました。
しかし依然として政府は調査中として取り合う気もありません。
議会では無理だと考えた田中正造は、衆議院議員を辞しました。
そして田中は命がけの行動に出ます。
明治天皇への直訴です。
直訴は結局天皇に届きませんでした。
しかし、下手をすれば死刑にさえ値する田中の行動により、足尾の現状は広く世間に知れ渡るようになりました。
結局、足尾銅山は1973年まで採掘が続けられました。
現在は徐々に足尾の山々に緑が戻りつつあります。
産業の発展の裏側には、たくさんの問題があるんですね。
多くのものを犠牲にして現代が成り立っている。
私たちはその事実をしっかり受け止めなくてはなりません。
ほんとだね。
さあ、次回はいよいよ第一次世界大戦です。
日本が世界の動乱の中、どのような動きをするのか。
しっかりと見ていきましょう。












