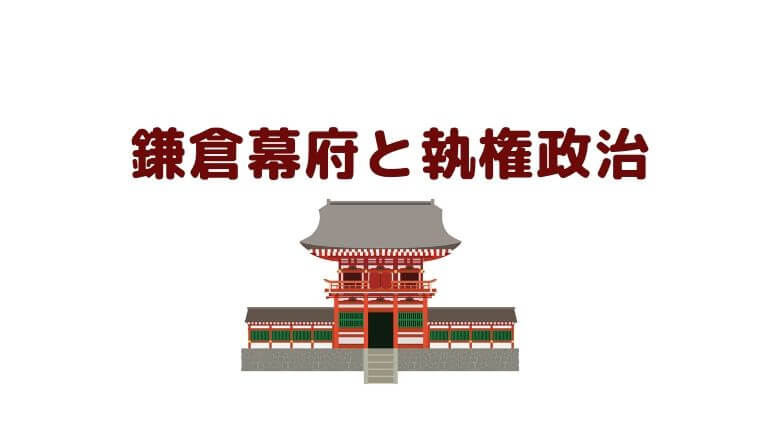元寇(げんこう)と鎌倉幕府滅亡
モンゴル帝国
モンゴルは中国北方の遊牧民族の国です。
家畜の食料の牧草は、定住すると乏しくなってきます。
乏しくなれば豊富な牧草を求め、また移動して行く移動型の牧畜生活。
それが遊牧です。
モンゴルにはそのような遊牧民族が多数存在していました。
それらを統一したのがテムジンと言う男です。
1206年、テムジンは部族の指導者たちに認められました。
偉大なるモンゴルの統治者大ハーンに選ばれチンギス・ハンと名乗ります。
チンギス・ハンを統治者とする統一モンゴル国。
それがモンゴル帝国です。
テムジンが生まれたのは1167年です。日本では平清盛が太政大臣になった時です。
じゃあ、たった100年でモンゴル帝国はこんなに大きくなったんですか!?

そうなんです。この頃は、モンゴル帝国から元(げん)と国名が変わりました。
ユーラシア大陸の大部分を支配していますね。
100年でこんなことってできちゃうんだね。
日本でさえ鎌倉幕府が出来るまであんなに苦労したのに・・・。世界はすごいですね・・・。
これを可能にしたのは、ひとつにモンゴル民族特有の機動力があります。
彼らは馬を巧みに操る騎馬民族でした。
元々遊牧民族と言う移動型の生活にも慣れており、次々に領土拡大できたのでしょうね。
これじゃあ、日本なんて敵わないよね・・・。
それから、元(げん)の皇帝フビライ・ハン(チンギス・ハンの孫)は、実に国際交流に柔軟な人間でした。
第5代モンゴル帝国(元・げん)皇帝
後に元寇(げんこう)と呼ばれる文永・弘安の役で2度日本へ攻め込む。
フビライの時に領土が最大となる。
フビライは、能力のあるものは異教徒であろうが異国人であろうが登用し、国政の重役に就かせました。
これだけ領土が拡大すれば、異文化、異民族を従えなければなりません。
言葉も違えば生活様式も全く違う国々です。
簡単に支配と言うわけにはいきませんでした。
フビライは征服先の民族を上手く活用することで、この問題を解消したのです。
東方見聞録(とうほうけんぶんろく)
す、すごすぎるフビライ・ハン!
フビライに仕えた人でマルコ・ポーロと言うイタリア人がいます。
東方見聞録(とうほうけんぶんろく)と言う記録を残した人で有名です。
マルコ・ポーロはイタリアの商人です。
元(げん)は陸路航路共に整備され、国際交流がとても盛んでした。
元(げん)の首都北京(ぺきん)は各国の商人が行き交い賑わいました。
マルコ・ポーロもそんな商人の一人でしたが、フビライ・ハンに登用されました。
フビライに仕え、自らが歩き見てきた世界の様相を綴りました。
それが東方見聞録です。
東方見聞録の中には日本のことも書かれています。
「はるか東の海にはジパング(日本)と言う国があり、国中に黄金が散りばめられている」
この黄金が何を意味しているのかは不明です。
しかし、当時の人達は黄金に溢れたユートピア(理想郷)だと騒ぎ立て、
いつしか黄金の国ジパングと呼ばれるようになりました。
昔は黄金がいっぱいあったのかな?
たまたまマルコ・ポーロが日本を訪れたのが晩秋で、見渡す限りの黄金色の紅葉シーズンだったのでは?と言う意見もありますが、真意は不明です。
元寇(げんこう)
広くユーラシアを支配下に置いたフビライは東側の諸国にも進出を試みます。
高麗(こうらい)を従えたフビライは再三と日本に使者を送りました。
やばいのに目をつけられちゃったんだね。ぶるぶる。
時の第8代執権北条時宗は完全無視を貫きました。
き、肝っ玉座ってるね。ぶるぶる。
大帝国を築いたフビライ・ハンは東の島国にガン無視され、とうとうブチ切れます。
やばいやばい。ぶるぶる。
と、当然攻めてきますよね?
大船団を率いて、いよいよ元の大軍が西日本に攻めてきます。
元(げん)による2度の襲来を合わせて元寇と呼びます。
1度目の襲来は1274年文永の役(ぶんえいのえき)です。
元(げん)は対馬、壱岐を襲い、博多に上陸しました。
火薬を使った武器に幕府軍は圧倒されましたが、朝鮮半島の高麗との対立が生じ、
元(げん)は早々に引き上げました。
1度目はただの様子見が強い戦いでした。
2度目は1281年弘安の役(こうあんのえき)です。
この時は幕府も用意周到に元(げん)を迎え討ちました。
簡単に上陸させないように博多湾に石を積み重ね防壁を作ったのです。
武士の活躍もあり元(げん)は結局上陸できず、暴風雨により撤退を余儀なくされました。
神風(かみかぜ)の由来はここから来ています。

日本史上初の侵略危機にさらされた日本ですが、幕府と御家人たちの活躍で、難を逃れました。
その後、フビライは日本への侵略は叶わず、息を引き取ります。
79歳の激動の生涯でした。
す、すごいぞ日本!
こんな小さな国があんな大国に勝ったんですね。すごい!
元としては、初めて地続きではない国を攻めたこともあり、かなり苦戦を強いられたのは事実ですね。
これで、ますます朝廷は何も幕府に言えなくなってしまいましたね。
ところがです。意外な結末が鎌倉幕府には待っていたのです。
ま、またこの展開!?
鎌倉幕府滅亡
いきなりですが、鎌倉幕府は元寇の後、約50年で滅亡します。
えー!!?なんで!?
元(げん)を追い返して幕府の力はさらに強くなったんじゃないんですか?
確かに元寇での御家人達の活躍は目を見張るものがありました。
しかし、彼らに報いるための御恩が幕府にはなかったのです。
御恩がない?どういうことですか?
元寇は、他国を攻めたわけではなく、攻められたのを追い返しただけです。
つまり他国の領地を手に入れたわけではない。
そうか!御恩、つまり御家人にあげる土地が手に入らなかったんだ!
しかも御家人たちは自費負担で元寇に備え、九州に集結しています。
中には自分の土地を売ってまでして、武具や馬を揃え参戦したものもいます。
それは気の毒ですよね。幕府は何か手を打たなかったんですか?
御家人が手放した土地を無料で取り戻せる永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)を出しました。
しかし、それも効果はなく、御家人の不満は頂点に達します。
幕府も打つ手なしか・・・。
となるとここで出てくるのはやはり・・・。
そうです。朝廷が政治の実権を取り戻すため動き出します。
第96代後醍醐天皇です。
後鳥羽上皇の起こした承久の乱は、北条政子の檄により御家人が一致団結し朝廷軍を破りました。
しかし、今回は状況が違います。
幕府のために財を投げうち戦った御家人達。
何も得るものがなく、幕府に対する信頼は崩壊しました。
こうなると簡単に幕府は内側から崩壊して行きます。
後醍醐天皇の完全勝利により、あっけなく鎌倉幕府は滅んでしまいました。1333年のことです。
後醍醐天皇に味方した御家人には、後の室町幕府初代将軍足利尊氏や有力武士の楠正成(くすのきまさしげ)がいます。