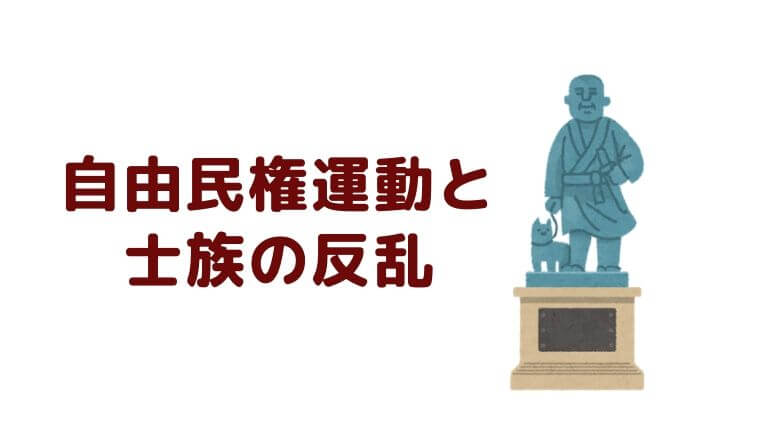孤立する日本(後編)
暴走する軍部
孤立する日本。今日は後編です。
前回(孤立する日本・前編)では、日本が国際連盟を脱退するところまででしたね。
満州国の建国は、リットン調査団の報告により侵略行為と認定されたのですね。
満州国とは、1931年に満州事変を起こした日本関東軍が建国した国です。
名目上は清朝最後の皇帝であった「溥儀(ふぎ)」を皇帝としていますが、実際は大きく異なりました。
日本関東軍の言いなりになるしかなかった溥儀(ふぎ)。
事実上、満州国は日本関東軍の占領下に置かれたのです。
国際連盟は、満州国建国を日本の侵略行為と認定した。
それで日本に対し、満州を中国に返還するように勧告したんですね。
日本はそれに応じず国際連盟脱退・・・。う~ん嫌な予感。
ところが日本国内では、多くの者が満州事変と国際連盟脱退を支持したのです。
多くの新聞の支持があったこともあり、満州国へ対する日本関東軍の行動は称賛されました。
長引く昭和恐慌脱出の糸口は、満州にあるという考えから、国民も歓迎しました。
こうした後押しもあり、軍部の間では政党や財閥を打倒し、強力な軍事政権をつくろうとする動きが出てきました。
国内が押せ押せムードだったんだね。
誰も止められなかったのでしょうか?
国際連盟脱退(1933年)の前に話が戻りますが、当時の首相の犬養毅(いぬかいつよし)は軍部の動きを止めようとしていました。
首相に言われたら、言うこと聞くよね?
ところが、もはや軍部は首相の言うことすら聞かなくなっていました。
内閣総理大臣の犬養毅は、関東軍による自作自演の満州事変の報告を受け、暴走する軍部を止めようとしました。
しかし、軍部は犬養の話に聞く耳を持ちませんでした。
「軍は天皇のものであり、政府のものではない」
これが軍部の主張でした。
さらに国内の満州事変容認ムードが後押しし、軍部の動きを止めることは不可能だったのです。
そんな中、国内に衝撃的な事件が発生しました。
五・一五事件(ご・いちごじけん)
1932年5月15日のことでした。
衝撃的な事件が発生します。
首相犬養毅が暗殺されたのです。
ええー!!?誰に!?
政治に不満を持つ海軍の将校たちです。
首相まで暗殺されちゃうなんて・・・。
もう誰も止められない・・・。
原敬以来、本格的な政党政治が続いてきましたが、犬養の暗殺でそれも終わりを告げます。
ここからは、軍人が首相になる時代となります。
二・二六事件(に・にろくじけん)
犬養暗殺の翌年(1933年)には日本は国際連盟を脱退します。
孤立しちゃうよ日本。
ここでまた、国内に衝撃的な事件が発生します。
1936年の2月26日のことでした。
1935年には東北地方が冷害に見舞われました。
農作物の凶作や長引く不況により、国民のくらしは非常に苦しいものでした。
これらはすべて、自分のことしか考えていない政治家や軍幹部が原因であるとして、陸軍の青年将校たちが反乱を起こしたのです。
約1400人の兵が反乱を起こし、政府の大臣を襲い、東京の中心部を占拠しました。
「くさりきった政治家たちから天皇陛下をお守りする」
明治時代のような天皇中心の政治を取り戻すこと。
それが彼らの思いでした。
しかし、彼らの思いは届かず、17人の青年将校が銃殺刑で処刑され終結しました。
この二・二六事件以降、軍部はさらに政治に関わろうします。
盧溝橋事件(ろこうきょうじけん)
話は満州に移ります。満州を支配下に置いた日本は、さらに中国の領内へ進出していきました。
中国では毛沢東率いる中国共産党と蒋介石の中国国民党が内戦を続けていましたが、日本の動きを警戒し、内戦を停止しました。
中国も日本だけじゃなく身内でも争っていたから大変だね。
そんな中、北京の盧溝橋で日中両軍の武力衝突が起きます(盧溝橋事件)
この盧溝橋事件がきっかけで、日中戦争が始まりました(1937年)
満州だけでは終わらなかったんですね。
これに対し、中国側は第二次国共合作を行い、日本に対抗します。
日中戦争がはじまると、日本は首都の南京(なんきん)を占領しました。
しかし、国民政府は首都を漢口(かんこう)、さらには重慶(じゅうけい)へと移し、アメリカやイギリスの支援を受けながらなんとか戦争を続けていきました。

首都南京の占領の際、日本軍は女性や子供など一般人をも含む多数の中国人を殺害したとされています(南京事件)
首都を占領ということは、日本で言えば東京を占領されたということでしょ?
普通に考えれば、そこで戦争が終結しそうですけど、中国は首都を変えながら戦い続けたんですね。
中国も意地でも負けられなかったんだろうね。
日本としては、ここで誤算がありました。
ひとつは第二次国共合作。
もうひとつは日中戦争の長期化です。
中国国民党の蒋介石は、大の共産党嫌いでした。
そのため敵国日本よりも、むしろ国内の中国共産党への弾圧を重視したのです。
しかし、日本の満州国建国により「今は中国国内が団結するときである」との説得(蒋介石は一時監禁された)により、蒋介石は中国共産党と手を組むことを決心します。
この抗日民族統一戦線(こうにちみんぞくとういつせんせん)は日本にとって大きな誤算でした。
そしてもう一つは日中戦争の長期化です。
日中戦争の最中に中国共産党の毛沢東(もうたくとう)は「持久戦論(じきゅうせんろん)」を発表しました。
内容は、「持久戦に持ち込めば日本に勝てる」というものです。
確かに、当時の日本軍は強く勢いがありました。
しかし、いかんせん島国のため資源にも乏しく、特に石油はアメリカからの輸入に頼るしかない状態でした。
国際連盟を脱退し、さらに盧溝橋事件を引き起こした日本に対し、アメリカ、イギリスは大きく反発しました。
このような国際的孤立を深める日本。
さらに資源が乏しい日本が、外国から援助を受けられないことは致命的であるとして、「戦いを長期化すべし」となったのです。
首都を変えながらも、中国が強気に戦い続けた理由がわかりました。
しかしながら、アメリカやイギリスを敵に回しても、日本は勝機があるとにらんでいました。
どう考えても厳しい気が・・・・。
第二次世界大戦の開戦。それが日本の見出した活路です。
第二次世界大戦開戦
1939年、ヒトラー率いるナチスドイツ軍がポーランドに侵攻し、世界情勢が大きく揺らぎました。
ドイツ軍は強く、1940年にはフランスを占領しました。
「イギリスの降参も間もなく」とささやかれるほど、ドイツの勢いは止まりませんでした。
そうかわかりました!イギリスは中国の援助ばかりしていられない状態になったということですね!
第二次世界大戦の開戦が日本にとっての活路というのは、世界の関心がヨーロッパへ向かうということなんですね!
そのとおりです!そして、オランダなどもドイツに降伏し、当然フランスやオランダの持つ東南アジアの植民地は手薄となります。
特にオランダ領の東インド諸島には豊富な油田があります。この油田を確保出来れば、日本には自力で日中戦争を戦い抜く確信があったのです。
ドイツの連戦連勝により、日本は手薄になった東アジアの欧米植民地へ進出を試みます。
日本の南下政策を受け、アメリカが下した決断は、日本への石油全面禁輸(輸出を禁じる)でした。
アメリカからの石油禁輸により、日本は国家崩壊までのカウントダウンが始まってしまいます。
約2年。
この2年という数字は、当時の日本の石油備蓄量で、海軍が戦い抜けるギリギリの期間でした。
ならばなお、東南アジアの油田は確保しなければならなくなります。
しかし、これ以上戦線を拡大すれば、アメリカとの軍事衝突は避けられません。
日本の出した答えは「アメリカとの開戦やむなし!(やむをえない)」でした。
日本の対外方針が明確になり、1940年、日本は躍進めざましいドイツ、そしてイタリアとの三国軍事同盟を成立させます。
大東亜共栄圏(だいとうあきょうえいけん)
1940年、近衛文麿(このえふみまろ)を首相とする内閣は、日本の戦う理由を明言しました。
つまり戦争目的を大東亜共栄圏(だいとうあきょうえいけん)と定めたのです。
ダイトーア・・・?
アジアの諸民族が欧米諸国の支配から独立し、アジア諸民族の共存共栄をはかる。
それが大東亜共栄圏です。
長引く日中戦争に対し、明確な目的をはっきりとさせることで日本国の一致団結を目指し、そして戦争への大義を得ようとしたものです。
以後、この言葉は、戦時中の目的を表す言葉として使われていくことになります。
なんだかものすごいことになってきた・・・。
日本はこの後、とうとうアメリカと開戦していくことになります。
世にいう真珠湾攻撃(しんじゅわんこうげき)に端を発し、太平洋戦争へと突入していきます。
パールハーバーですね。
太平洋戦争と第二次世界大戦はどう違うの?
太平洋戦争は第二次世界大戦の一部分だと考えてください。
第二次世界大戦はヨーロッパ中心に行われましたが、アジアや太平洋方面でも行われました。
それを太平洋戦争と呼びます。
そう考えると、日本はずいぶん長く戦争をやっていたんですね。
満州事変(1931年)から考えればとても長いです。
盧溝橋事件から日中戦争が始まりました。長引く日中戦争の間に始まったのが第二次世界大戦です。
そしてアメリカと敵対し太平洋戦争へと突入し、1945年のポツダム宣言で戦争終結ですから、約15年も戦争を続けたことになります。
15年・・・。俺の歳と一緒だ・・・。
生まれてから今日までずっと戦争なんて、辛いな・・。
中にはそういう人達もたくさんいたんです。
そして、太平洋戦争では若い命がたくさん散っていきました。
戦争で犠牲になった世界中の人々のために、私たちはしっかりと歴史を学んでいきましょうね。