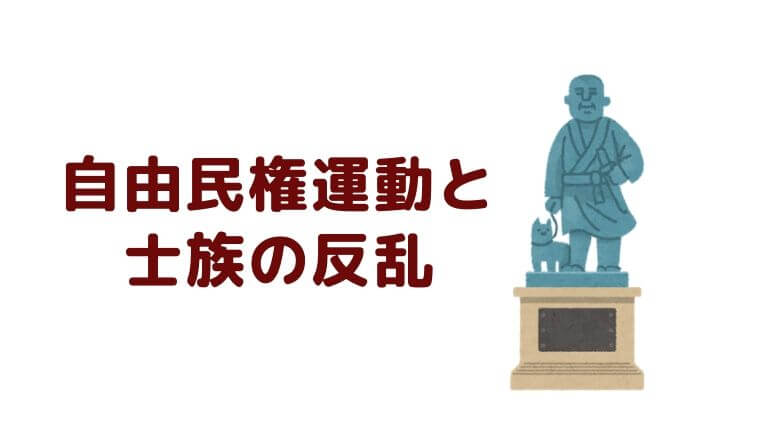明治維新(後編)
Contents
岩倉使節団
1871年から約2年に渡り欧米諸国へ派遣された使節団。
メンバーは岩倉具視(いわくらともみ)を筆頭に木戸孝允(きどたかよし)伊藤博文(いとうひろぶみ)大久保利通(おおくぼとしみち)ら総勢100名ほどのメンバーでした。
視察内容は主に欧米諸国との友好、西洋文化の視察、そして不平等条約の改正でした。
しかし、日本の国力は依然として弱く、不平等条約の改正には至りませんでした。
岩倉具視は使節団の出発の際、ちょんまげのままでした。
使節団の出発の写真では、岩倉だけがちょんまげで写っています。
ちょんまげは日本人の誇りとして、断固としてやめようとはしませんでした。
ところが欧米諸国を視察した岩倉は、外国の文化の発展ぶりに驚がくし、ちょんまげをやめてしまいました。
帰国した時の岩倉の頭を見た一同は、西洋文化がいかに優れたものであるかを悟ったということです。
使節団は長州藩とか薩摩藩の人が中心なんですね。
明治新政府は討幕派が中心に組織されました。
討幕派は薩摩藩や長州藩が主体であったので、政府内も薩長色が濃い人事だったのです。
これを藩閥(はんばつ)政府と言います。
ちょんまげのままアメリカに行ったら目立つよね。
岩倉は西洋文化を積極的に取り入れようとした人ですが、日本人の魂とも言えるちょんまげは断固として残そうとしていたのです。
しかし、あまりにも文化の違いが離れすぎていて外交の姿に臨む格好ではなかったのです。
まずは格好からですね。
実際、帰国した岩倉の姿を見て、ちょんまげを辞めた人達が多かったようです。
「あの岩倉さんが!?」という感覚だったのでしょうね。
不平等条約は改正できなかったんだね。
せっかく行ったのに・・・。
決して無駄骨だったわけではないのですよ。
特にドイツのビスマルク宰相(さいしょう)との出会いは使節団の人々に大きな影響を与えたのです。
宰相(さいしょう)とは首相、総理大臣のことです。
ドイツ帝国のビスマルク宰相と使節団との出会い。
それは日本に大きな近代化へのきっかけとなりました。
多数の小国家に分かれていたドイツ。
その中のプロイセン王国が統一し成立した連邦国家がドイツです。
小国家に分かれていたため、外交的に弱い立場にあったドイツ。
それを強国家に作り上げたのが宰相ビスマルクです。
その経緯を日本になぞり、岩倉使節団にスピーチしたビスマルク。
内容は「外国の言いなりのまま近代化を図るのではなく、外国と肩を並べる軍事力を持ち近代化を図れ」というものです。
このスピーチに熱く感動した岩倉使節団は、頭を下げることで各国に条約改正を伺うのではなく、「外国を圧倒するほどの軍事力を持つことで、いずれは不平等条約は改正されるであろう」と考えるようになります。
欧米の進んだ文化に直接触れたことや、ビスマルクが語る独立国家の在り方は、真に日本に近代化をもたらすきっかけとなったのです。
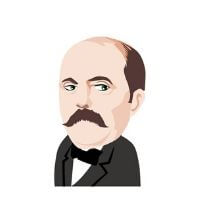
他にもドイツから学ぶ事はたくさんありました。
特に憲法の整備を考えていた日本は、ドイツ国憲法(ビスマルク憲法)から学ぶ事は多かったのです。
ドイツは皇帝を君主として憲法で統治する「立憲君主国家」です。
日本は天皇を中心として立憲君主制を目指していたので、ドイツの憲法や国家統治体制は学ぶべきことが多々ありました。
日本へ帰国した伊藤博文は、大日本帝国憲法の制定に乗り出すことになります。
ドイツと日本は大きな接点があったんですね。
ビスマルクの影響は日本の近代化には欠かせないものだったのです。
「馬鹿にされたくなかったら強くなれ」単純なようで的を得ている言葉です。
いつになったら不平等条約は改正されるの?
まだ先の話ですが、そう遠くもない話です。
岩倉使節団が帰国してからの日本の近代化は、ものすごいスピードで進んでいきます。
外国に勝ってしまうんですか?
日清戦争、日露戦争での勝利により不平等条約は完全に撤廃されます。
いずれ詳しくお話ししましょう。

日本人てすごい。
岩倉使節団の視察報告を受けた明治天皇と政府は欧米諸国に対抗するため、経済を発展させて軍備の強化に乗り出します。
これを富国強兵(ふこくきょうへい)と殖産興業政策(しょくさんこうぎょうせいさく)と言います。
士族の不満
地租改正により国家の収入は安定したものの、依然財政難が続いていました。
問題は士族への給料です。
版籍奉還や廃藩置県により、大名は土地を失いました。
藩の武士達は大名からの禄(ろく※給料)で生活していましたが、大名が土地を失うことで給料を払えなくなりました。
解放令により武士は身分が士族となりました。
大名に代わり、全国の士族には国から給料が支払われました。
その士族への給料支払いが国家支出の大半を占め、国家財政は苦しい状況になっていたのです。
そこで政府は徴兵令を出し、士族も平民も関係なく、満20歳以上の男子に兵役の義務を課したのです。
当時強国であったヨーロッパ諸国はこの徴兵制度を取っていました。
日本も近代化を目指すために、この制度を取り入れたのですが、実際は士族の大規模なリストラでした。
そのため士族は大きな不満を持つことになります。
また、農民からすれば、農作業以外に兵役の義務を持つことになり不満が高まります。
こうして徴兵反対の一揆が勃発しました。
士族は兵役の義務だけ負って、給料はなくなったわけですよね!?
ど、どうやって生活したの?
非常に苦しい生活を強いられました。
商売を始める者もいましたが、慣れないために失敗する人も多かったのです。
国家のためとは言え、すごいこと考えたね。
討幕から明治新政府の設立には士族の活躍があったからこそです。
その結果が大規模なリストラです。
士族としては国家の裏切りとしか思えない仕打ちでした。
なんだかかわいそう。
こうして士族の不満は全国各地で高まり、士族の反乱へと向かうことになります。
征韓論(せいかんろん)
岩倉使節団が欧米視察を終え、間もなく帰国する頃のことでした。
士族の反乱を決定づける出来事が発生します。
征韓論(せいかんろん)です。
岩倉使節団には主要な明治政府のメンバーが含まれていました。
使節団が欧米各国を訪問している間、留守の明治政府を預かっていたのが、板垣退助、西郷隆盛、江藤新平らでした。
士族の不満が高まる中、留守を預かっていた政府メンバーらは征韓論を主張しました。
征韓論とは武力で朝鮮を開国させようと言うものです。
当時、朝鮮は日本と同様に鎖国を続けていました。
留守を預かる明治政府が征韓論を主張した大きな理由は以下のようなものです。
1、迫りくるロシアの脅威を朝鮮半島で食い止めるため
鎖国政策で近代化が遅れた日本。朝鮮も同じような道を歩んでいたため近代化に遅れを取っています。
ロシアが南下してくる可能性がある当時、朝鮮半島は日本列島の防御壁になる存在でした。
日本は武力で朝鮮を開国させ、一気に朝鮮の近代化を図り、来るべきロシアに備えようとしました。
2、欧米諸国が行っていた植民地政策を日本も行おうとしたため
欧米の経済発展の背景には植民地政策があります。
植民地の安価な原料を元に商品を作り、植民地で売り裁く。
こうして欧米諸国は経済を発展させていきました。
植民地を求め国外に進出し支配を及ぼしていく政策を帝国(ていこく)主義と言います。
日本も欧米諸国に追いつくには植民地支配が必要だとし、そこで目を付けたのが朝鮮だったのです。
3、明治維新の諸政策に対する国内の不満を、朝鮮進出により抑えようとしたため
当時の日本は明治新政府の急激な改革により不満が高まり、一揆が多発していた時期です。
特に徴兵令による士族の不満はかなりのものでした。
そこで外国と戦うことで、国内を統一しようとする考えが芽生えたのです。
こうして生まれたのが征韓論です。
その後岩倉使節団が帰国し、明治政府内は2つにわかれ争うことになります。
外国の進んだ文化を嫌と言うほど見てきたのが岩倉使節団です。
彼らは征韓論を真っ向から批判します。
「今は外国と戦争するべきではない」
国内の近代化を強く進めて行くことが先であると言うことを主張しました。
そりゃそうなるよね。
西郷隆盛は征韓論派の中では慎重で、まずは西郷が使節として朝鮮に行く。
そして万が一命を落とすようなことがあれば、朝鮮を武力で征服するべしとの態度を取りました。
結局は武力征服なんだね。
しかし、結局岩倉使節団の大久保利通らに反対され、西郷の朝鮮派遣は実現されませんでした。
実際に海外を見てきた人と国内にいた人。
考え方に違いが生まれる。攘夷と開国みたいですね。
仕方がないことだと思います。
結局、明治天皇に征韓論は反対され、当面日本は国内経済や軍事に専念し国力を高める方向となりました。
天皇に言われたんじゃ仕方ないよね。
西郷隆盛や板垣退助は政府を去っていきました。
こうして明治政府の方針は一本化され、富国強兵と殖産興業の道を突き進んでいくことになります。
その後日本国内は短期間で発展し、外国と肩を並べるほどに成長していきます。
開国により欧米諸国の文化を取り入れ、外国と肩を並べる力を持つ。
結果、外国を打ち破るほどの力を手に入れる日本。
悲願であった攘夷開国はこうして達成されていきました。
明治維新はこうして完成を見るのです。
いよいよ世界か!
と、その前に政府を去った西郷隆盛らによる日本最後の内戦である士族の反乱を次回お話ししましょう。
そっか。士族の不満も未解決だし、西郷隆盛も志半ばで政府を去ってしまったんでしたね。
侍(さむらい)たちの最後の意地をかけた戦い。
次回はラストサムライです!