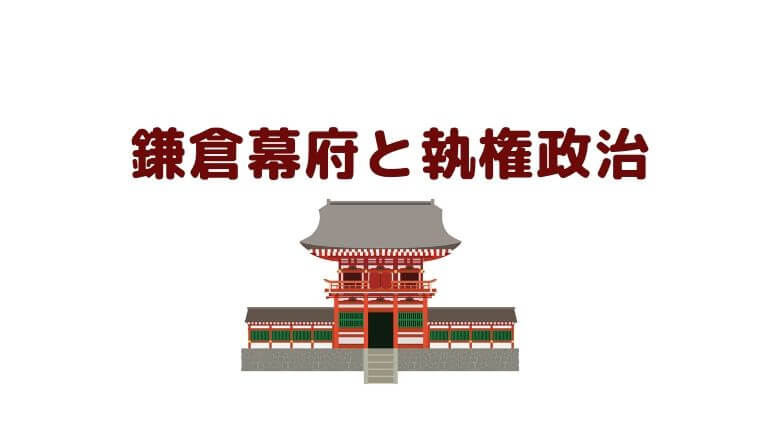鎌倉仏教と鎌倉文化
鎌倉仏教
前回(元寇と鎌倉幕府滅亡)で鎌倉幕府は滅亡しました。
今日は、鎌倉時代の仏教と文化のお話です。
鎌倉時代の仏教?今までのと何か違うの?
これまでの仏教はどちらかと言えば、護国(ごこく)仏教のスタイルです。
簡単に言えば、国を護(まも)るための仏教でした。
全国に護国寺が建てられたりしましたね。
鎌倉仏教の大きな特色は、「自分を救う」と言う言わば自分のために信仰する仏教です。
当時、日本は末法思想(まっぽうしそう)の真っただ中でした。
末法思想とは、釈迦が亡くなってから2000年後に世界は乱れると言う思想です。
1052年が末法思想始まりの年とされています。
1052年と言えば、ちょうど前九年の合戦が始まったあたりで、自然災害も重なりました。
そうした中、人々はいよいよ末法思想の時代が到来したと考えたのです。
自分の生きる未来に光を灯そうとする新しい仏教の教えは、そのわかりやすさと相まって、多くの人々の心を捉えていったのです。
鎌倉仏教は6人の僧による6つの宗派があります。
具体的に見ていきましょう。
浄土宗(じょうどしゅう)の開祖
一心に「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」を唱えれば、誰でも極楽浄土へ行けると教える。
[talk name=”奈良”]法然の教えは実にシンプルです。
どうしても僧の修行と言うと厳しいイメージがつきますが、法然の教えはただひたすら唱えるだけです。[/talk]
[talk name=”やまと”]それ、楽だな。[/talk]
[talk name=”奈良”]ただ時間があるときに念仏を唱えればいい。
そのシンプルさに瞬く(またたく)間に武士や民衆に広まったのです。
[/talk]
浄土真宗(じょうどしんしゅう)の開祖
親鸞(しんらん)は法然の弟子です。
彼は、法然の教えにさらに、阿弥陀如来(あみだにょらい)の救いを信じる心を強めることを説き、浄土真宗を開きました。
[talk name=”奈良”]阿弥陀とは大宇宙そのものを指し、お釈迦様は言わば阿弥陀の教えを伝える仏の一人にすぎないというものです。[/talk]
[talk name=”やよい”]大宇宙(だいうちゅう)?[/talk]
[talk name=”奈良”]他の宗教で言うところの神様ですね。
絶対的な存在です。お釈迦様はその方の教えを説くために生まれたものと位置づけされます。[/talk]
[talk name=”やまと”]お釈迦様より偉いのか。[/talk]
時宗(じしゅう)の開祖
[talk name=”奈良”]一遍は一風変わった教えを広めます。
踊念仏(おどりねんぶつ)と言って踊って極楽浄土へ行こうというものです。[/talk]
[talk name=”やまと”]踊り念仏!楽しそう![/talk]
[talk name=”やよい”]ダンシング!やってみたい![/talk]
[talk name=”奈良”]現代でもストレス発散は体を動かすことが1番だと言われていますからね。
嫌なことも忘れて気楽になれるのではないでしょうか。[/talk]
[talk name=”やよい”]ある意味、1番特効薬的な教えかもしれませんね。[/talk]
日蓮宗(法華宗・ほっけしゅう)
「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」を唱えれば人も国も救われると説きました。
[talk name=”奈良”]日蓮の教えは過激でした。
先の3人の宗派は、どちらかと言うと「やってごらん」というスタンスでした。
日蓮は「ねばならない」MUSTの教えです。[/talk]
[talk name=”やよい”]熱狂的なんですね。[/talk]
[talk name=”奈良”]幕府にも法華経を強要するので弾圧されたりしました。
違う宗派の僧から暴行を受けたりもしました。[/talk]
[talk name=”やまと”]すごい情熱だね。[/talk]
[talk name=”奈良”]法華経を信仰しなければやがて国難が来る!と真剣に考え、鎌倉幕府に何度も直訴しています。[/talk]
日蓮は結局相手にはされませんでしたが、しばらくして元寇が発生しました。
予言としては当たっていた・・・と言うことかもしれません。
一転して、次は瞑想(めいそう)の世界です。
マインドフルネスが現代でも静かなブームです。
座禅を組み、心を鎮め、悟りを開こうとするものです。
過去や未来に執着せず、「今この瞬間を感じること」
それが瞑想です。
これらは禅宗(ぜんしゅう)と呼ばれました。
禅宗は武士に歓迎され、幕府も保護したほどです。
[talk name=”奈良”]日蓮が幕府に直訴しているころ、第5代執権北条時頼(ときより)は禅宗を重んじていました。
[/talk]
[talk name=”やよい”]じゃあ、なおさら相手にされなかったわけですよね。日蓮さん。[/talk]
[talk name=”奈良”]ちなみに北条時頼は元寇で元(げん)に勝利した執権北条時宗のお父さんです。[/talk]
栄西(臨済宗・りんざいしゅう)道元(曹洞宗・そうとうしゅう)
ほんと、仏教っていろんな種類があるんですね。
どれが正しいとかはありません。
大切なのは、一人一人が生きる希望を持てるようになることだと思います。
私は瞑想をやってみたいです!禅宗がいいな。
俺はやっぱダンシングだな!一遍の時宗!
そのような感じで広く一般庶民にも受け入れられていったのが鎌倉仏教です。
何か楽しみがないとつまらないもんね。
それが元々のお釈迦様の教えだと思いますよ。
いろんな形になっても人々の心の支えになる。
それが仏教だと先生は思います。
鎌倉文化
それが元々のお釈迦様の教えだと思いますよ。
いろんな形になっても人々の心の支えになる。
それが仏教だと先生は思います。
さて、次は鎌倉時代の生活です。
定期市(ていきいち)と呼ばれる、いわゆるマーケットが各地で行われるようになりました。
それも楽しそう!
市は定期的に行われたので定期市です。
月に3回行われました。
どのような物が売られたんですか?
米、魚、お酒、農具や布など幅広く取り扱っていました。
とても活気的だったようですよ。
鎌倉時代は武家政権だったり外国からの侵略だったり、新しい仏教だったり、新しいことばかりですね。
この定期市が各地で盛んに行われたのは、ひとつに宋銭(そうせん)が使用されたことによるものです。
そうせん?
平清盛は、当時中国にあった王朝「宋(そう)」と盛んに交易を行いました。
宋との交易の中で宋銭が日本に輸入されました。
宋銭はとても質が良く、広く国内で使われるようになりました。
奈良時代にも和同開珎(わどうかいちん)と言う日本で初めての貨幣がありました。
しかしあまり活用されることはありませんでした。
貨幣が使用されないと物々交換が主となります。
宋銭が広まったことで、物々交換から貨幣での交換になります。
現代社会の経済活動に大きく近づいたのです。
貨幣に信用が生まれ、全国で使われることになり、定期市は大いににぎわいました。
※臨済宗や曹洞宗などの禅宗も宋から入ってきた新しい仏教です。
他にも、宋から新しい建築様式が伝わり、運慶(うんけい)作の金剛力士像が造られました。
鎌倉の大仏も宋の建築様式で造られたんですよ。

PublicDomainPicturesによるPixabayからの画像
おお!力強い!
そして、鎌倉時代を代表する軍記物は何と言っても「平家物語」です。
源平の戦いですね。
琵琶法師(びわほうし)と言う盲目(目が見えない)の法師により語り伝えられました。
最後にちょっと怖い話をして終わりましょう。
な、なぬ!?
平家物語は盲目の法師により、語り伝えられました。
壇ノ浦の戦いで海に身を投げ命を落とした安徳天皇(8歳)と平家の者達を祀った阿弥陀寺があります。(山口県下関市)、
その阿弥陀寺に芳一(ほういち)と言う琵琶法師が住んでいました。
芳一は、目が不自由でしたが琵琶の腕前はかなりのものでした。
芳一の語る平家物語、特に壇ノ浦の戦いの場面では、誰もが涙を流すほどの腕前でした。
ある夜、阿弥陀時の芳一のもとに、一人の武士がやってきました。
是非、芳一に一族の前で琵琶の弾き語りをして欲しいと頼まれました。
芳一は武士に連れられ、ある屋敷に迎えられました。
屋敷で壇ノ浦の合戦を弾いていると、大勢の人々のむせび泣く声が聞こえてきました。
また来てほしいと頼まれ、芳一は寺に帰りました。
それからと言うもの、芳一は毎晩のようにこっそり出かけていきました。
そんな芳一を不審に思った寺の和尚が後をつけてみると、なんと芳一はたくさんの鬼火に囲まれながら琵琶を奏でているではありませんか。
そして芳一の目の前にあるもの、それは安徳天皇のお墓でした。
芳一は、平家の霊達に琵琶を聞かせていたのでした。
このままでは芳一が危ない。
ある時、和尚は、芳一の体中にありがたいお経を書き綴りました。
和尚は言いました。
「芳一、これでお前の姿は平家の霊には見えない。お前を迎えに来ても、絶対に返事をしてはいけないよ。
平家の者が諦めるまで、ただじっと座っていなさい」
芳一は和尚に言われたとおりにしました。
ある夜、平家の武士が迎えにきました。しかし芳一の姿はどこにもありません。
芳一はじっと動かず息を呑みました。武士の声は怒りに変わってきています。
ここで、ふと武士はあることに気付きました。
なんと芳一の耳だけがしっかりと見えるではありませんか。
実はお経を書いた和尚ですが、芳一の耳にだけ書くのを忘れてしまったのです。
「ならばお前の耳だけでももらっていくぞ」
武士はそう言って芳一の耳を引きちぎり持って帰ってしまいました。
和尚が帰ると、血だらけで倒れている芳一の姿がありました。
耳がない芳一。耳なし芳一として語り継がれる怪談話です。
こ、怖い・・・(汗)
さあ、次は新しい時代、室町時代の幕開けです。