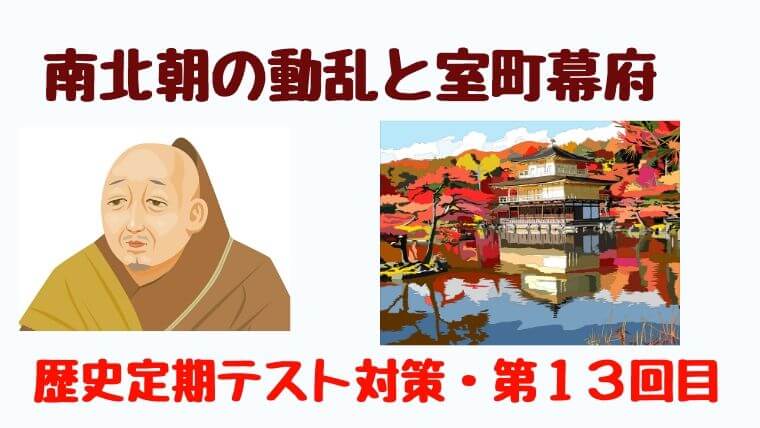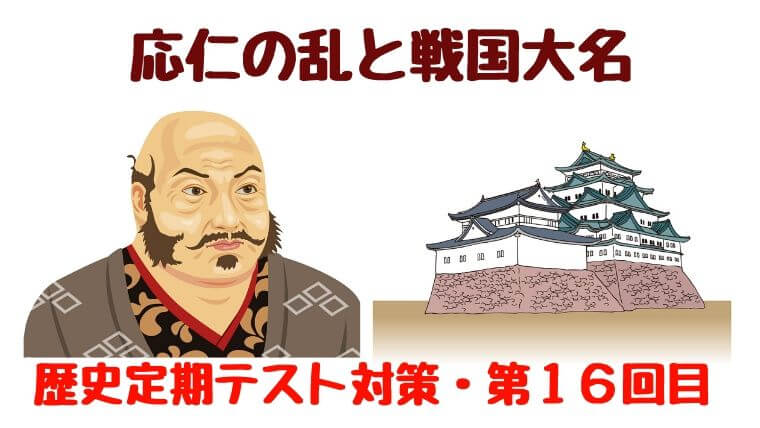室町時代のアジア
室町時代のアジア
定期テスト対策第14回目です。
80Pから81Pです。
室町時代の東アジアとの交流を中心に見ていきます。
ここでは室町時代の日本と、東アジア諸国との関わりを見ていきます。
中国では、鎌倉幕府を脅かしてきた元(げん)が衰え、新たな帝国明(みん)が建国されます。
同様に朝鮮半島では高麗(こうらい)が滅び朝鮮国(ちょうせんこく)、沖縄では琉球王国(りゅうきゅうおうこく)が建国されます。
まだ日本の領土ではなかった北海道のアイヌの人々と、積極的に交易が行われるようになったのもこの頃です。
日本を取り巻く環境が大きく変わった室町時代。
さあ、室町幕府はこれら東アジア諸国とどのように関わっていったのでしょうか。
倭寇(わこう)の被害
室町時代に東アジア諸国を悩ませていた問題があります。
倭寇(わこう)です。
倭寇(わこう)?
室町時代の海賊、それが倭寇(わこう)です。
西日本にいた武士や商人、漁師などが集団化し、中国大陸沿岸や海を行く船を襲いました。
元(げん)が力を持っていた頃には、中国大陸やその近海を荒らすなど考えられなかったことです。
しかし、徐々に元(げん)の力が弱まるにつれて、倭寇(わこう)が海賊まがいの行動を起こすようになったのです。
倭寇(わこう)に手を焼いた明(みん)は、室町幕府将軍の足利義満(あしかがよしみつ)に倭寇(わこう)の取り締まりを要請します。
南北朝を統一した将軍ですね。
義満は倭寇(わこう)を取り締まる一方で、正式な貿易船と倭寇(わこう)の船を区別するために、証明書を使いました。
証明書?
明(みん)から与えられた勘合(かんごう)と呼ばれる証明書を、正式な貿易船に持たせたのです。
そのため、日明貿易は、勘合貿易(かんごうぼうえき)とも呼ばれます。
当時の航海は危険が伴う上、倭寇(わこう)の存在に脅かされていました。
中には正式な貿易船に成りすまし、物品を奪っていく倭寇(わこう)もいました。
そのため、正式な貿易船と倭寇(わこう)を区別するために使用されたのが勘合(かんごう)です。
勘合貿易で、日本は刀や銅などを輸出し、明(みん)からは銅銭や生糸、絹織物を輸入しました。
この勘合貿易は、日本と明の対等な形ではなく、朝貢(ちょうこう)、つまり日本は明の皇帝に従うという形を取っていたことを覚えておきましょう。
朝鮮国の建国
14世期末、朝鮮半島でも大きな動きがありました。
高麗(こうらい)が滅び、朝鮮国(ちょうせんこく)が建国されました。
高麗(こうらい)は元々元(げん)に服属していました。
しかし、元(げん)の支配力が弱まることで、滅ぼされることになってしまいます。
滅ぼしたのは李成桂(りせいけい)という人物です。
彼が建国した朝鮮国は、ハングル文字を作り、中国とは離れた独自の文化を築いていきます。
現在の朝鮮半島の原型ともなった国です。
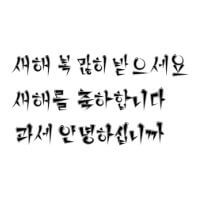
朝鮮国も同様に倭寇(わこう)に悩まされ、日本に取り締まりを求めています。
足利義満は朝鮮と日朝貿易を行い、こちらからは綿織物や仏教経典を輸入しています。
琉球王国(りゅうきゅうおうこく)と中継(なかつぎ)貿易
次は沖縄。琉球王国(りゅうきゅうおうこく)です。
15世紀に首里(しゅり)を首都に沖縄が統一されました。
琉球王国の誕生です。
琉球王国と言えば、中継(なかつぎ)貿易です。
中継貿易とは、海外から輸入したものをそのまま外国に輸出し、利益を得る貿易です。
例えば中国から絹織物を輸入し、それをそのまま日本へ輸出するなどです。
言葉は悪いですが転売のようなイメージです。
こうして琉球王国は利益をあげていきます。
琉球王国と言えば、首都首里(しゅり)にある首里城が有名です。
2019年に火災で被害を受けてしまいましたが、日本で世界遺産に登録されているお城です。

琉球王国ができる前の沖縄は、各地で力のある豪族が勢力争いをしていました。
日本みたいだね。
豪族は按司(あじ)と呼ばれ、城(グスク)を根拠地にしていました。
初めは多数存在した按司(あじ)ですが、やがて3つの大きな勢力にまとまります。
按司(あじ)の3つの勢力を北山(ほくざん)中山(ちゅうざん)南山(なんざん)と言います。
この中で、中山(ちゅうざん)の王、尚氏(しょうし)が沖縄を統一しました。
この尚氏(しょうし)が建国したのが琉球王国です。
アイヌ民族との交易
北海道はかつて蝦夷地(えぞち)と呼ばれ、アイヌと呼ばれる人々が住んでいました。
実は北海道と呼ばれるようになったのは明治時代になってからです。
蝦夷地は独特の文化を持っていました。
14世紀頃、日本とアイヌ民族との交易が盛んに行われていました。
このことは、蝦夷地の海に面した各地に、多くの宋銭(そうせん)が発掘されていることからわかりました。
いかがでしたか?外国も絡んでくるのでちょっとわかりづらい箇所ですね。
とにかく重要語句の意味をしっかり理解してください。
倭寇(わこう)と正式な貿易船を区別するために、何を使用しましたか?
日本と明との貿易を何と言いますか?
日本は明に対し、何を輸出し、何を輸入しましたか?
日朝貿易では、日本は朝鮮から何を輸入しましたか?
中継(なかつぎ)貿易とは何ですか?
アイヌ民族と交易があったことは、何が発掘されたことでわかったのでしょうか?