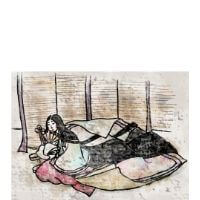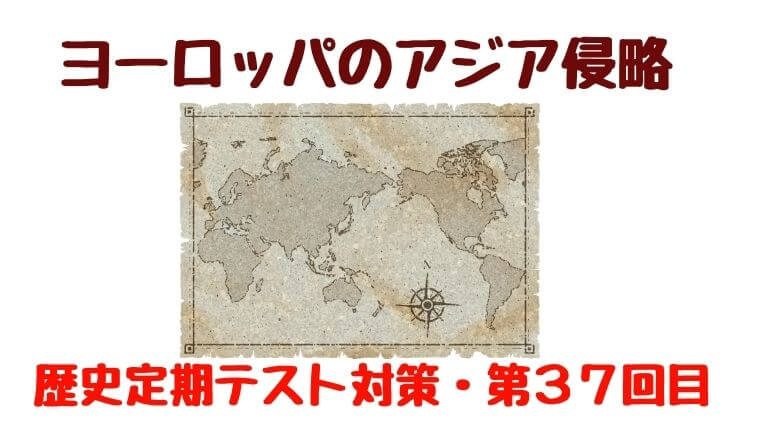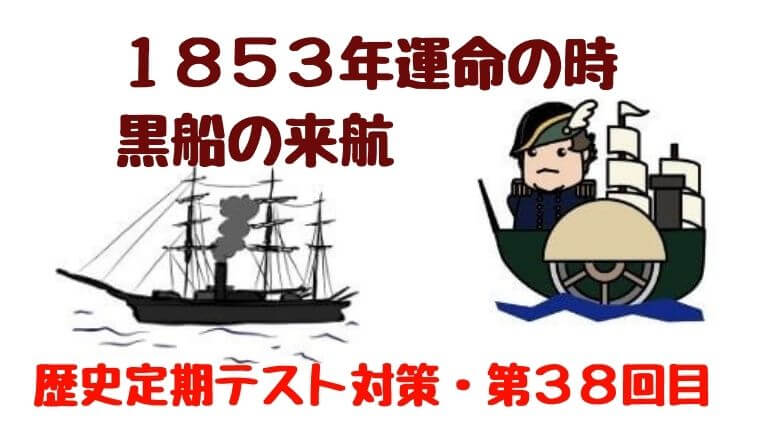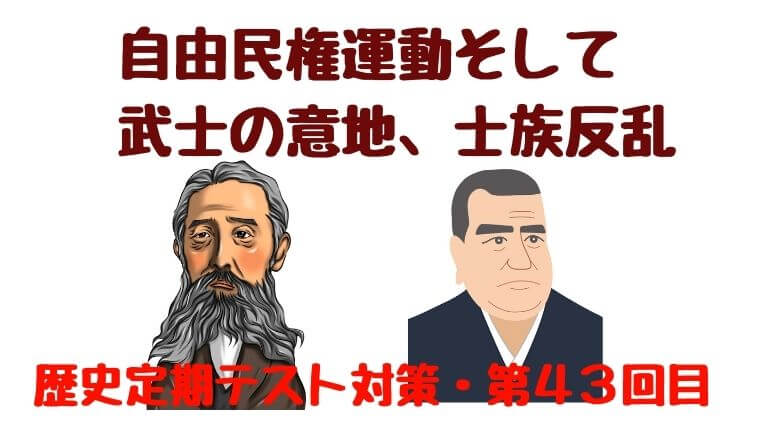この世は藤原一族のものなのよ
この世は藤原一族のものなのよ
定期テスト対策の第六回目です。
時は平安時代。藤原一族の栄華と国風文化です。
50P~51Pです。
藤原一族と言えば摂関政治(せっかんせいじ)です。
摂関政治の内容を記述で答えられるようにしておくことが大事です。
国風文化の内容も大切ですが、なぜ国風文化が芽生えたのかを説明できるようにしましょう。
これらの記述に対応できることで、確実に20点はアップします。
平安時代は華やかな、貴族を中心とした文化が栄えた時代です。
優雅な暮らしがイメージしやすい時代です。
平安時代の建築様式に寝殿造り(しんでんづくり)があります。
広い庭園に中心となる家屋が寝殿(しんでん)と呼ばれます。
家主の居室になる場所であり、客を通す客間ともなります。
その寝殿を中心に、渡殿(わたりどの)と呼ばれる廊下によって、複数の建物がつながっています。
これが寝殿造りと呼ばれる建築様式で、平安時代の特に上層階級の貴族が過ごした屋敷です。

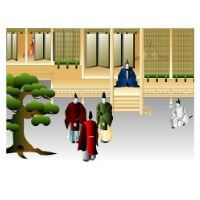
美しい庭園と寝殿造り。
貴族の華やかな暮らしが想像できますね。
摂関政治(せっかんせいじ)
平安時代と言えば、藤原氏です。
藤原氏の始祖は大化の改新の中臣鎌足(なかとみのかまたり)です。
中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)を支え、蘇我氏を倒しましたね。
藤原氏は自分の娘を天皇のきさきにし、生まれた子を次の天皇にし勢力を伸ばしてきました。
やがて天皇をさしおき政治を行うようになっていきます。
天皇が幼い時は摂政(せっしょう)に、成長すると関白(かんぱく)という天皇を補佐する役に就き政治の実権を握っていきます。
このような摂政や関白が中心となった政治を摂関政治(せっかんせいじ)と言います。
朝廷の中で強大な権力を得た藤原氏。
特に道長(みちなが)の時に、藤原氏の全盛期を迎えます。
「この世をば、わが世とぞ思う望月(もちつき)の、欠けたることもなしと思えば」
意味は、「私には、この満月のように、全く欠けているものなどないではないか」と言うような内容です。
これは藤原道長が詠んだ有名な句ですが、道長の権力の強さがよくうかがえる句です。
摂関政治により権力を手中に収め、全国の国司達は藤原氏やそのまわりの貴族達に贈り物を送り、政治は乱れに乱れました。
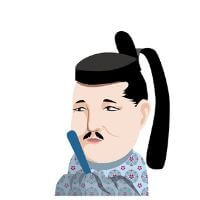
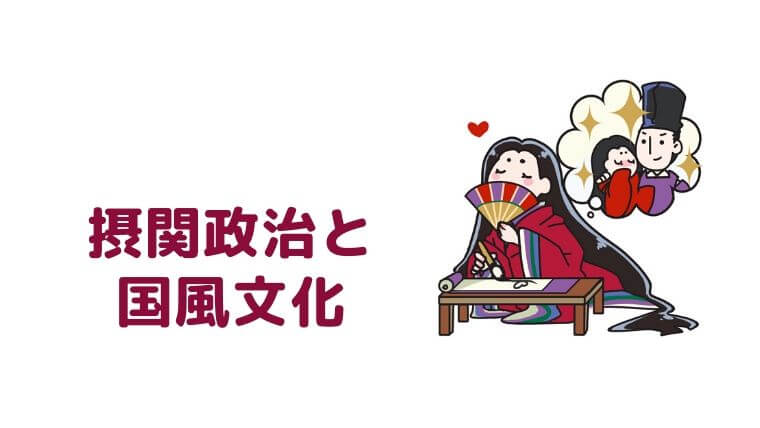
国風文化
菅原道真(すがわらのみちざね)の進言により、遣唐使が廃止されたのが894年のことです。
それまで何かと唐の文化の影響を受け続けてきた日本ですが、遣唐使の廃止により唐文化と日本の交流が減少します。
そこで芽生えてきたのが日本独自の文化である国風文化です。
遣唐使が廃止され、芽生えた文化が国風文化です。
国風文化の特徴はなんと言っても仮名文字(かなもじ)です。
漢字から仮名文字(ひらがなやかたかな)が使用されるようになり、文学作品に大きな影響を与えました。
紀貫之(きのつらゆき)の古今和歌集(こきんわかしゅう)は仮名文字を使用した優れた文学作品です。
漢字と違い、平仮名はその丸みを帯びた愛らしい形から、女流作家誕生のきっかけにもなりました。
紫式部(むらさきしきぶ)や清少納言(せいしょうなごん)です。
女性による文学作品も国風文化の特色です。
紫式部の源氏物語(げんじものがたり)
清少納言の枕草子(まくらのそうし)が有名です。
浄土信仰(じょうどしんこう)
阿弥陀如来(あみだにょらい)にすがり、死後には極楽浄土(ごくらくじょうど)へ生まれ変わることを願う。
これを浄土信仰(じょうどしんこう)と言います。
平安時代の半ばごろ、社会が乱れ人々の不安な気持ちが増していきました。
そこで人々は念仏を唱えることにより極楽浄土を目指したのです。
余談ですが、阿弥陀如来とは、お釈迦様の師匠とも言うべき存在です。
宇宙の源でもあり、全知全能の神。それが阿弥陀如来です。
その阿弥陀如来がいる場所が極楽浄土です。
極楽浄土とは「あらゆる苦しみのない世界」とされており、念仏を唱えた者は、死後極楽浄土へ行けると信じられていました。
浄土信仰の各地への広まりとともに、各地に阿弥陀如来像やそれを収める阿弥陀堂(あみだどう)が各地につくられました。
日本各地にある「~阿弥陀堂」は、阿弥陀如来像が収められている場所であり、かつて極楽浄土信仰のために作られたものです。
京都府の宇治(うじ)にある平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)は当時の代表的な阿弥陀堂です。
平等院は、鳳凰がつばさを広げたような美しい形をしていることから、鳳凰堂と呼ばれるようになりました。

源氏物語絵巻のような、日本の自然や風俗をえがいた絵は大和絵(やまとえ)と呼ばれ、日本画の基にもなりました。