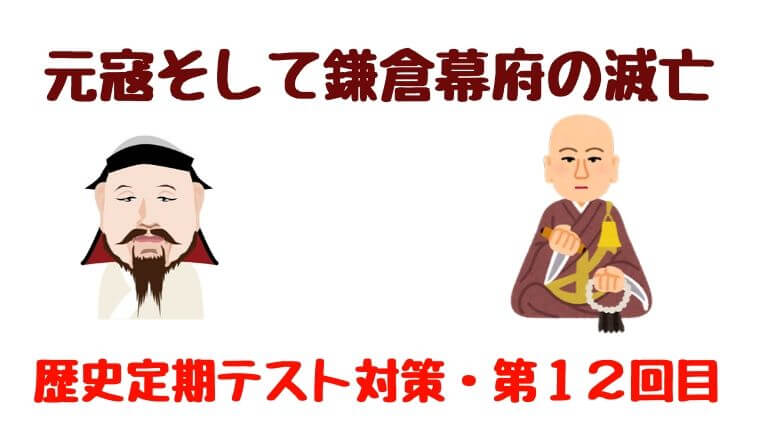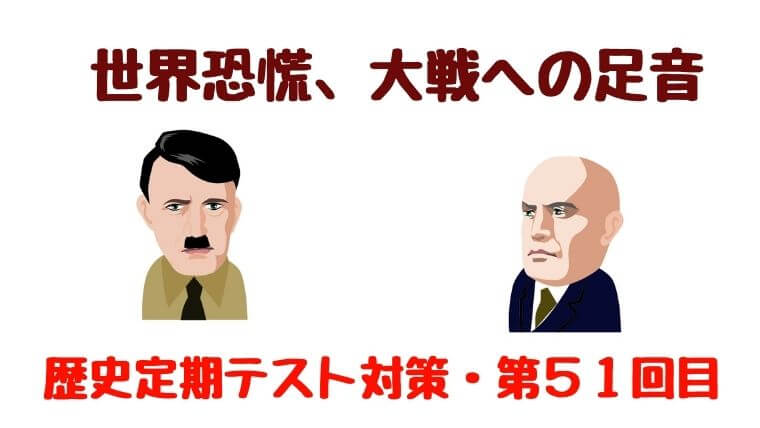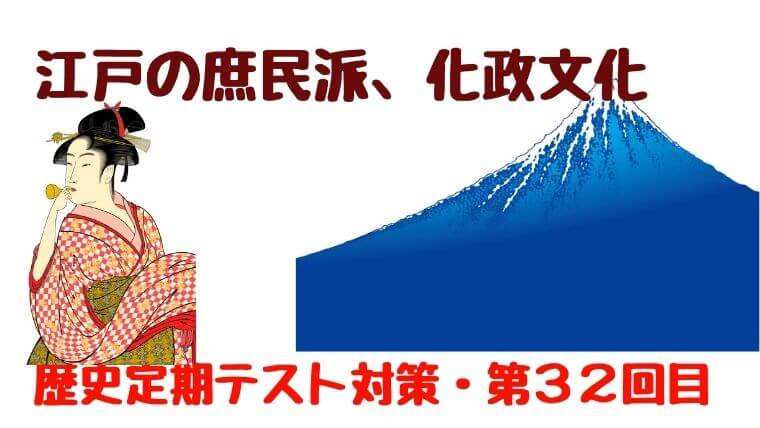尊王攘夷と開国のはざまで
尊王攘夷(そんのうじょうい)と開国のはざまで
中学歴史定期テスト対策の第39回目です。
欧米の国々と不平等条約を結ばされた日本。
国内では開国か尊王攘夷かで意見が分かれます。
教科書は156P~157Pです。
江戸時代末期、いわゆる幕末と呼ばれる時代です。
このあたりから歴史教科もかなり複雑になってきます。
しかし、大まかな歴史の流れをつかみ、話を追っていけば理解しやすくなります。
流れは以下の通りです。
苦手意識を持たず、まずは幕末から明治時代の全体像を掴みましょう。
欧米の力を目の当たりにし、欧米に従わざるを得ないとする開国派。
天皇を尊び外国人を打ち払おうとする尊王攘夷(そんのうじょうい)派。
これらの日本国内の意見の違いから、幕府と藩の争いが始まります。
最終的には江戸幕府は滅亡することになります(大政奉還)
その後時代は明治時代へ。
日本はハリスと結んだ日米修好通商条約をきっかけに、安政の五か国条約を結びました。
いわゆる不平等条約です。
この不平等条約を解消するために、日本は奔走することになります。
欧米各国をまわり、外国視察と不平等条約の撤廃を目指した岩倉使節団(いわくらしせつだん)
しかし、日本は相手にされません。
不平等条約の撤廃は、苦難の道となります。
岩倉使節団は、欧米視察の際に運命的な出会いを果たします。
ドイツのビスマルク宰相(さいしょう)です。
ビスマルクは使節団にこう言い放ちました。
「敵になめられたくなければ、強くなれ」
日本は、ただお願いするだけではダメだと気付きました。
欧米並みに強くなる。
こうして日本はまず憲法制定に取り掛かります。
近代国家の代名詞ともいえる憲法。
憲法が整備されている国家は、特に近代化が進んでいると言えるでしょう。
伊藤博文(いとうひろぶみ)を中心に、日本は大日本帝国憲法を制定します。
ドイツの憲法をお手本にしています。
途中、武士の誇りをかけた反乱が日本国内に発生します。
明治新政府樹立の立役者、西郷隆盛(さいごうたかもり)は、最後は武士の意地をかけて新政府と戦い、戦死しました。
その後、日本は幾多の苦難を乗り越え、強くなりました。
日清戦争の勝利、日露戦争の勝利。
欧米に引けをとらないことを立証した日本は、とうとう不平等条約の撤廃に成功し、近代国家の仲間入りを果たすことになります。
大まかな流れですが、幕末から明治の流れです。
参考にしてください。
まずは、今日は開国と尊王攘夷運動をバッチリおさえましょう。
尊王攘夷(そんのうじょうい)運動の高まり
まずは尊王攘夷運動の意味をおさえておきます。
尊王(そんのう)とは、君主を敬うと言う意味です。
攘夷(じょうい)は、敵を打ち払うことです。
尊王(そんのう)は天皇を敬うこと。
攘夷(じょうい)は外国を打ち払うことか。
尊王攘夷(そんのうじょうい)とは、天皇を尊び、外国の敵を打ち払うという思想です。
開国派は、外国を受け入れて、国交を開こうと言う思想です。
どちらが正しいんですか?
ここは非常に難しいところです。
幕府は外国の脅威を目の当たりにし、これは絶対に敵わない。
ならば鎖国をやめ、国を開き、外国と交易を持つしかないと思ったのです。
幕府以外の朝廷とか藩はどうだったんですか?
実際に外国の脅威、つまり黒船などを見たこともない。
だからその圧倒的な実力も知らない。
古き日本の伝統を、外国人に踏みにじられてなるものか。
となるわけです。
そうか。テレビやインターネットもない時代、黒船もただの噂でしかないもんね。
実際に見たことがある人ではないとわからないよね。
知らない人達は、幕府の開国の動きを腰抜けに感じたのです。
それが、尊王攘夷運動(そんのうじょういうんどう)ですね。
井伊直弼(いいなおすけ)は、独断でハリスとの日米修好通商条約や安政の五か国条約を結んだとされています。
しかし、外国の実際の姿を知らない朝廷や諸藩に説明しても、話が通じないであろうと考えたのかもしれません。

じゃあ、井伊直弼(いいなおすけ)を暗殺したのは。
尊王攘夷派の水戸藩の元藩士達に暗殺されました。
有名な桜田門外(さくらだもんがい)の変です。

井伊直弼(いいなおすけ)は、幕府に反抗する尊王攘夷(そんのうじょうい)の思想の持ち主たちを処罰しました(安政の大獄)
それに対して、過激な尊王攘夷派の人間たちに殺害されてしまったのです。
公武合体(こうぶがったい)
黒船の正体を知りながらも尊王攘夷(そんのうじょうい)を貫こうとした人もいます。
吉田松陰(よしだしょういん)です。

松陰は、山口県の長州藩出身です。
黒船来航を聞いた松陰は、単身黒船に乗り込もうとし、失敗した人です。
幕末の尊王攘夷(そんのうじょうい)を掲げる、幕末の志士達を育てた松下村塾(しょうかそんじゅく)は有名です。
伊藤博文や高杉晋作など、多くの志士を生み出しました。
敵の強大さを知りながらも、その敵を倒そうとした人もいたのですね。
結局は、幕府に対する危険な思想の持ち主ということで、安政の大獄で処刑されてしまいました。
けど、幕府に対して不満がある人を処罰していったら、結局幕府も恨まれるだけだよね?
そこで幕府が考えだしたのが公武合体(こうぶがったい)政策です。
独断で政策を決定し、反抗する者は処罰する。
その幕府へ対する不信感は高まるばかりでした。
そこで幕府が考えた政策は、朝廷との結びつきを強めることでした。
天皇や朝廷との結びつきを強めることにより、幕府は独り歩きしているわけではないということをアピールしようとしたのです。
そのためにとった幕府の手段が、天皇の妹和宮(かずのみや)を第14第将軍家茂(いえもち)と結婚させることでした。
天皇と将軍家が親戚関係にあることで、幕府と朝廷はしっかりとつながっていることをアピールしたのです。
これを公武合体政策(こうぶがったいせいさく)と言います。
開国による経済の影響
次は、開国に伴ってどのように経済に影響したかを見ていきます。
ここは試験でも頻出ですよ。
長い鎖国政策により、日本と外国の経済状況は大きな差が生まれていました。
端的に言えば、金(きん)に対する価値が大きく異なっていました。
日本では金と銀の交換比率が1:5
外国では金と銀の交換比率が1:15となっています。
これはどういうことかと言うと、日本では銀500gで金100gと交換できます。
外国では、銀を1500g出さないと金100gと交換できません。
つまり、同じ銀でも、外国で金と交換するより、日本にいったん持ち込んで交換したほうがお得に金と交換できるのです。
つまりどういうこと?
イギリスに住んでいるやまとさんが、銀貨を15枚持っています。
やまとさんは金を手に入れたい。
イギリスだと銀貨15枚で金貨1枚と交換できますね。
ところが、日本に持っていけば15枚の銀貨を3枚の金貨と交換できることがわかりました。
やまとさんならどうしますか?
そりゃ日本に行って3枚もらうよ。
あ!そういうことか!
そうなのです。
開国当初、この金銀の交換比率の違いによって、大量に日本の金(小判)が外国に流れてしまったのです。
経済に敏感な人は、そうやって大儲けするんですね。
これはまずいと思った幕府は、ある手段に出ます。
それが小判の質を落とすことでした。
金の量を減らした万延(まんえん)小判を作り流通させたのです。

どっかで聞いたことがあるような・・・。
そう。第5代将軍の徳川綱吉が同じことをやりましたね。
結果はどうでしたか?
物価が高騰(こうとう)しました。
逆に言えばお金の価値が下がってしまった。
そのとおりです。
インフレーションの発生です。
物価があがることをインフレーションと言います。
物の価値が上がりすぎて、生活必需品なども高価なものとなります。
一般人の生活も苦しくなるので、インフレーションは好ましくない状態です。
幕府は金の流出を防ごうとし、逆に経済を苦しくさせてしまいました。
綱吉の時代と全く同じことをした幕府。
何も教訓を得ていないことに、さらに幕府に対する反感は募ります。
尊王攘夷(そんのうじょうい)運動は、幕府の開国政策だけではなく、経済政策面に対する反抗でもあったことを覚えておきましょう。
世直し一揆とええじゃないか
こうして日常生活に行き詰ると、幕府への反抗が目立つようになります。
借金の帳消しや生活用品の値下げを求め、世直し一揆と呼ばれる暴動や、打ちこわしが頻発します。
け、結局幕府が何かやると、一揆や打ちこわしが始まるんだね。
ほんと、江戸時代は鎖国の影響で、世界の時間の流れに取り残されてしまっていたんですね。
各地で「ええじゃないか」と熱狂し、騒ぎ立てる人々が増え、幕府へ世直しを求める運動が行われました。