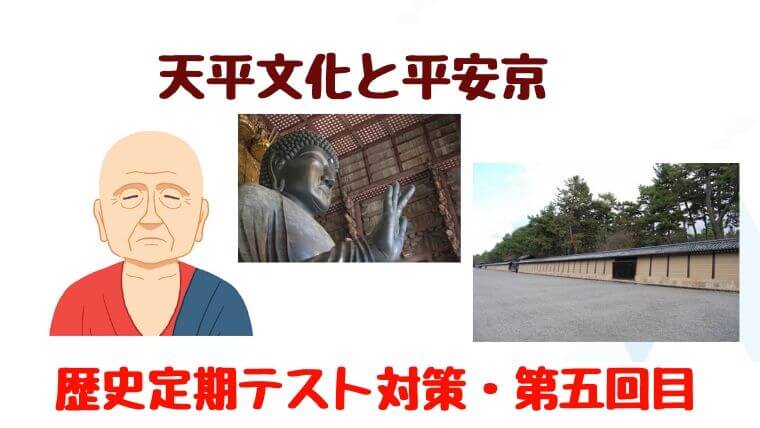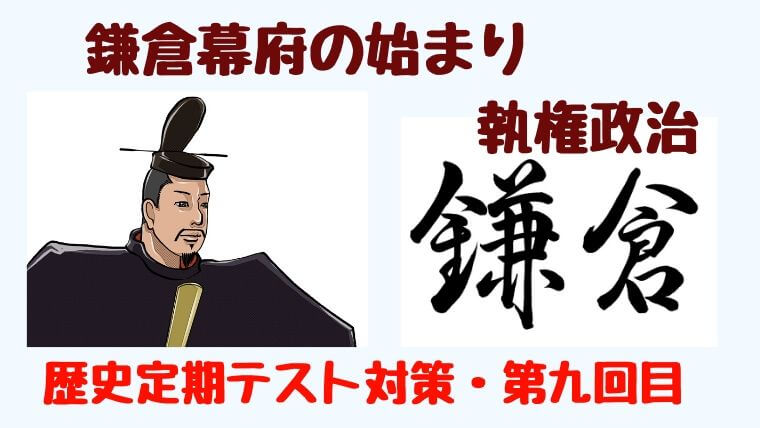秀吉と太閤検地
秀吉と太閤検地
中学歴史定期テスト対策の第22回目です。
教科書は108P~109Pです。
豊臣秀吉の政策です。
信長の亡き後、天下統一を果たした豊臣秀吉。
秀吉は、国内統一後、安定した社会を作るために改革を行いました。
主だったものは刀狩(かたながり)と太閤検地(たいこうけんち)です。
対外政策では、海外貿易、そして朝鮮侵略が行われます。
刀狩と太閤検地
豊臣秀吉が行った大改革は、刀狩(かたながり)と太閤検地(たいこうけんち)です。
刀狩(かたながり)?
太閤検地(たいこうけんち)?
刀狩とは、一揆(いっき)などの反乱を防ぐために、農民や寺社から武具を没収したことを言います。
これにより、武士と農民の区別がはっきりとなされるようになりました。
戦う者、耕す者の区別です。
身分の区別が明確化され、兵農分離が成し遂げられました。
検地(けんち)とは、田畑の大きさを測り、それによって収穫量を割り出すことです。
検地を行うことで、ある程度の年貢の徴収量を計算できるようにしました。
ところが、この検地には問題があったのです。
この当時、物の長さや量を測る基準が全国で統一していませんでした。
つまり田畑の面積の測り方が、地域によって異なっていたのです。
全国を統一した秀吉は、田畑ごとの正確な収穫量を割り出したいと考えました。
そのため行ったことが、長さを測るモノサシ、体積を量るマスを全国で統一することです。

こうすることで、田畑の収穫量を正確に予測することに成功しました。
そして、収穫量を米の体積である石高(こくだか)で表しました。
全国の土地を石高という統一的な基準で表すことが出来るようになったのです。
この秀吉による全国的な統一検地を太閤検地(たいこうけんち)と呼びます。
東北では30㎡の田畑が、西日本では50㎡の大きさとして扱われていると考えればわかりやすいですね。
確かに、それは混乱するな。
全国で統一するのは本当に大変だったでしょうね。
頭いいんだな。秀吉って。
余談ですが、秀吉の政策には石田三成(いしだみつなり)という人物が大いに関わっています。
秀吉の成功の裏には、優秀な家臣に支えられてきた事実があります。
戦略戦術面では軍師(ぐんし)の黒田官兵衛(くろだかんべえ)

そして財政などの内政面では石田三成(いしだみつなり)が大きく貢献しています。

国が大きくなればなるほど、領地の人口が増え、多くの食料を必要とします。
一度戦いとなれば、数か月分の米を蓄えなければなりません。
これを兵糧(ひょうろう)と言います。
これらのやりくりを若い石田三成が行っていたのです。
当然、秀吉から信頼され、かわいがられた三成。
しかし、それを良く思わない古参(こさん)の武将たちが大勢いました。
結局、三成と古参の武将たちの不仲を徳川家康に利用され、秀吉亡きあと、あっけなく豊臣家は滅んでしまいます。
今の話はテストには関係ありません。
秀吉の天才的な人を取り込む魅力、そしてそれを支える天才的な頭脳を持った黒田官兵衛や石田三成。
教科書には書いてませんが、面白い話だと思いませんか?
歴史はヒューマンストーリーですからね!
やっぱり徳川家康って、抜け目ないね。
秀吉の朝鮮侵略
定期テスト対策21でも説明しましたが、秀吉はバテレン追放令を出しています。
信長と違い、秀吉はキリシタンを警戒していました。
しかし貿易の重要性を見抜いていたから、ある程度キリシタンを放置していたことも事実です。
キリスト教を完全に追放してしまうと、外国との関わりが大幅に制限されてしまいますものね。
秀吉は、京都、長崎、堺の商人が東南アジアへ渡航することを積極的に支援しました。
日本を統一したら次は外国か。
とうとう秀吉は周囲の反対を押し切り、明(みん)の征服に乗り出します。
世界征服。
それが秀吉の最終的な野望です。
明(みん)って、あの中国ですよね!?
そ、そんな大きい国にケンカを・・。
蒙古襲来から考えれば、とんでもない出来事です。
逆に日本から攻めていくのですからね。
1592年、秀吉は諸大名に命令を下し、15万人の軍勢を朝鮮半島に侵攻させました。
狙いは明の征服です。
日本は初戦で快勝を続けました。
しかしやがて明の援軍が到着すると一気に押し戻されてしまいます。
日本の苦戦を見ると、朝鮮軍も一気に力を盛り返し、李舜臣(りしゅんしん)の水軍が日本の水軍を破りました。
これを文禄(ぶんろく)の役(えき)1592年と言います。
その後、明との講和交渉が始まりましたが、交渉は決裂。
秀吉は再度朝鮮に侵攻します。慶長(けいちょう)の役(えき)1597年。
日本では長引く戦で不満が高まりました。
そのような中、秀吉が亡くなります。
秀吉の生誕ははっきりとしていませんが、61か62歳の生涯であったと言われています。
秀吉が亡くなると、一気に停戦ムードが加速し、日本は朝鮮半島から撤退していきました。
この際、日本に連れてこられた朝鮮人陶工(とうこう)達により伝えられたのが焼き物の技術です。
彼らの優れた陶工技術により、後に有田焼(ありたやき)と呼ばれる焼き物が出来ました。

秀吉は最後は暴走してしまったのですか?
農民の出身で大出世を遂げた秀吉。
若き日は慈悲深い人間でした。
温かく思いやりのある人間性を持つ秀吉。
そんな秀吉の周りには多くの人が集まりました。
秀吉は天下統一を果たすと、人格が変わっていったとする話があります。
考え方の違いから千利休(せんのりきゅう)を切腹させたり、子ができない秀吉の跡継ぎであった甥(おい)の秀次(ひでつぐ)を自害に追い込んだりとした話です。
秀吉は晩年に待望の嫡男(ちゃくなん)秀頼(ひでより)を授かります。
秀吉は秀頼の行く末が心配で、心配の種を全て取り除きたかったのでしょう。
秀次に後継ぎが決まってから秀頼が誕生したことで、秀次を自害させてしまった秀吉。
豊臣の力を知らしめるために意地でも明を征服したかった秀吉。
全ては我が子、秀頼(ひでより)のかわいさゆえかもしれません。
結局、秀吉は最大の心配の種を取り除くことができないまま、生涯を終えます。
徳川家康です。
明との長い戦争。
戦地に赴くでもなく、大阪で内政を行っていた石田三成に対し、古参の武将たちの不満が高まります。
家康は、秀吉が亡くなると、さっそく三成を利用し、豊臣の内部分裂を仕掛けていくのです。
結局、秀頼と秀吉の妻、淀君(よどぎみ)は大阪城で自害することになり、世は徳川の時代を迎えるのです。
我が子かわいさゆえに。
秀吉は、若いころとは打って変わり、孤独の晩年を過ごした人なのです。
![]()