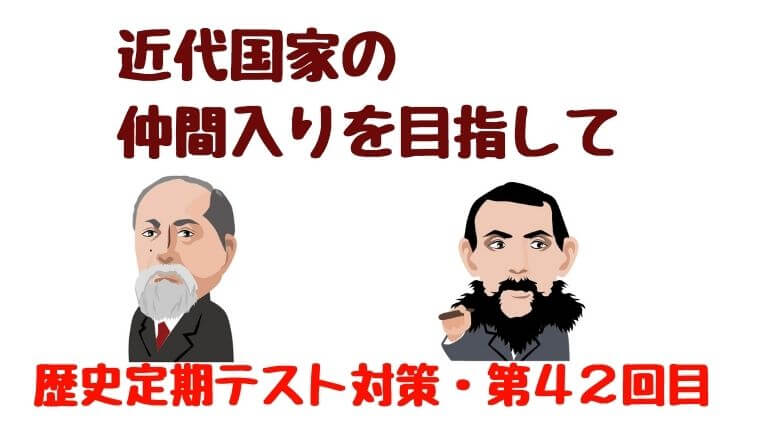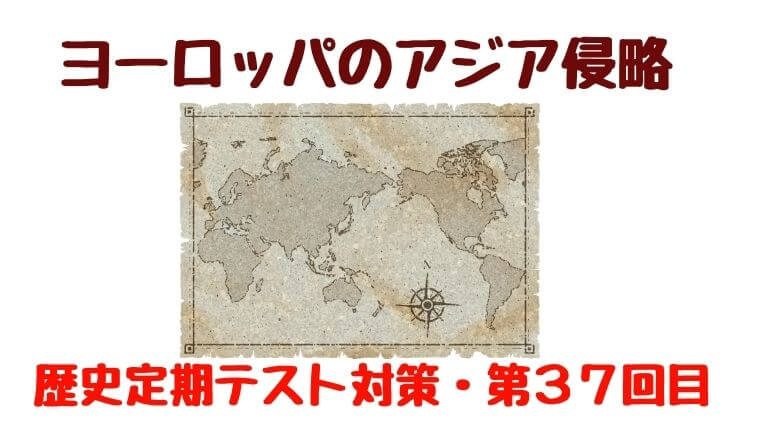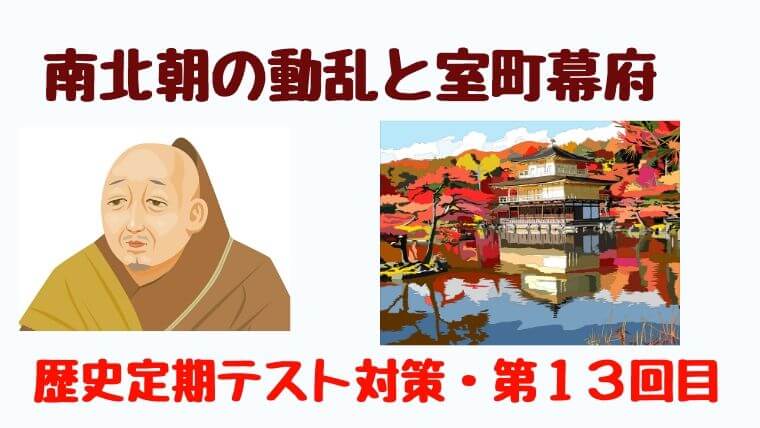これからは武士が政治を行います
これからは武士が政治を行います
定期テスト対策第八回目は、武士政権の成立です。
力をつけてきた武士が、とうとう政権(政治を行う権利)を手に入れるまで成長してきます。
教科書の68P~69Pです。
ここでおさらいをしておきましょう。
政権は本来天皇にあります。
そして律令体制の下では、実質的には天皇の下にある太政官(だじょうかん)が政治を行っていました。
ところが、公地公民の制が崩れ、律令体制が崩れ始めると天皇の力が一気に弱まっていきます。
そこで現れたのが藤原氏でした。
藤原氏は自分の娘を天皇に嫁がせたりしながら、朝廷内で大きな権力を手にしていきます。
広大な荘園を手にし、摂関政治(せっかんせいじ)を確立するなど、時代は藤原氏の全盛期でした。
おもしろくないのは天皇です。
長年日本を動かしてきた天皇。
しかし、朝廷内の一貴族に過ぎない藤原氏に政権を奪われ、天皇は権力の奪還を考えました。
こんな時に現れたのが武士達です。
徐々に力をつけ始めた武士。
彼らを上手く利用することで、天皇は権力を取り戻そうと考えていくのです。
院政(いんせい)
藤原氏とつながりが薄い後三条天皇(ごさんじょうてんのう)が天皇に即位し、事態は変わり始めます。
荘園管理を徹底し、藤原氏ばかりに荘園が流れないようにするなど、徹底的な政治改革を行い、藤原氏の勢いを抑え込むことに成功しました。
こうして天皇の力を取り戻していくのですが、ここから院政(いんせい)と呼ばれる政治スタイルが始まります。
天皇が位(くらい)を譲ると、上皇(じょうこう)となります。
いわゆる隠居(いんきょ)生活に入るのですが、この上皇が引き続き政権を担当していくことを院政(いんせい)と呼びます。
天皇が政治の場を去り、上皇となって住んだ場所が院(いん)と呼ばれました。
その院(いん)で引き続き政治を行ったことから、院政(いんせい)と呼ばれました。
天皇が政治を行うと言っても、天皇は年中を通し、各種行事をこなすことに手いっぱいだったと言われています。
こうした事情から政治がおろそかになり、スキをつかれ藤原氏のような貴族に政権を奪われてしまいました。
その弱点を補ったのが院政(いんせい)です。
天皇は従来通り各種行事を取り仕切る。
代わりに位(くらい)を譲った上皇が政治を行うというスタイルを作り上げたのです。
ただしこれは、結局は天皇以外の者が権力を持ち「藤原氏の摂関政治と何ら変わらないのではないか」という批判もありました。
かくして上皇は大きな権力を持ち、やがてそれを良しとしない天皇と対立していくことになります。
その対立に大きく貢献していくことになるのが武士たちです。
保元・平治の乱(ほうげん・へいじのらん)
院政(いんせい)は白河上皇や鳥羽上皇の時に大いに力をふるいました。
特に寺社を優遇したので、僧は大きな力を持ち、武装した兵(僧兵)となりました。
上皇は僧兵や武士を巧みに利用し、勢力を拡大して行きました。
上皇が力を持つ反面、不服に思う天皇との争いが始まります。
この2つの争いに大いに健闘したのが源氏と平氏の武士です。
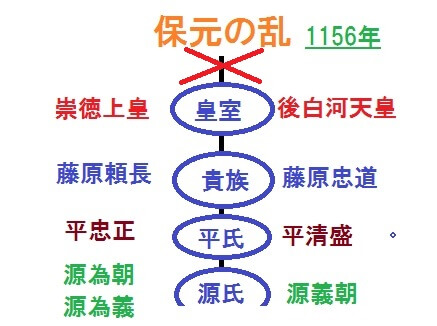
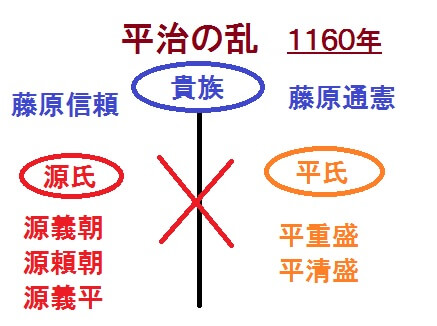
保元の乱は源氏平氏の区別なく、親も子も争いあう非情な争いでした。
続く平治の乱は完全に源氏と平氏がわかれて争いました。
詳しくは以下をご参照ください。

この2つの乱により朝廷内の争いが収まったことから、武士の力が大きく認められました。
源平の争乱
保元・平治の乱は平氏の活躍で後白河天皇の勝利に終わりました(保元の乱は源平入り乱れた骨肉の戦いでしたが)
平清盛(たいらのきよもり)は、その後も後白河上皇の院政を助け、武士として初めての太政大臣(だいじょうだいじん)になりました。
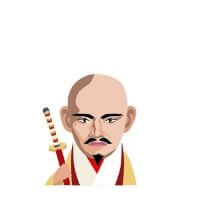
太政大臣は律令体制の太政官の中でも最高役職です。
適任者がいなければ空席となるくらい、誰でもなれる役職ではなかったのです。
その役職に武士が就任することになるとは、一体誰が想像できたことでしょうか。
こうして力をつけた平氏。
平清盛は娘を天皇のきさきにしたり、中国の宋(そう)との貿易の利益を得るため、兵庫県の港を整備しました。
航海の安全を祈願するために、広島県の厳島神社をたびたび参詣しました。

平氏の勢いはとどまることを知りませんでした。
しかしそのおごりから「平氏でなければ人ではない」と言う者達まで現れ始め、徐々に平氏に対する不満は高まって行きます。
そのような中、立ち上がったのが平治の乱で惨敗を喫した源氏でした。

平治の乱後、平清盛は源氏の若き後継者たちを生かしてしまいました。
そのため、平氏は源氏により滅ぼされることになります。
その後継者たちこそ源頼朝(みなもとのよりとも)と源義経(みなもとのよしつね)です。
源平最後の戦いは壇ノ浦(だんのうら)の戦いと呼ばれ、平家物語(へいけものがたり)の中で悲しく詠われています。