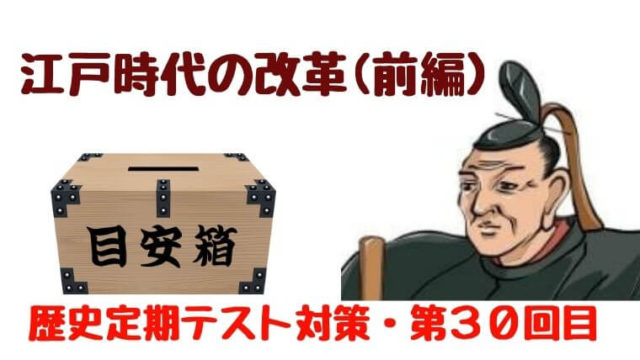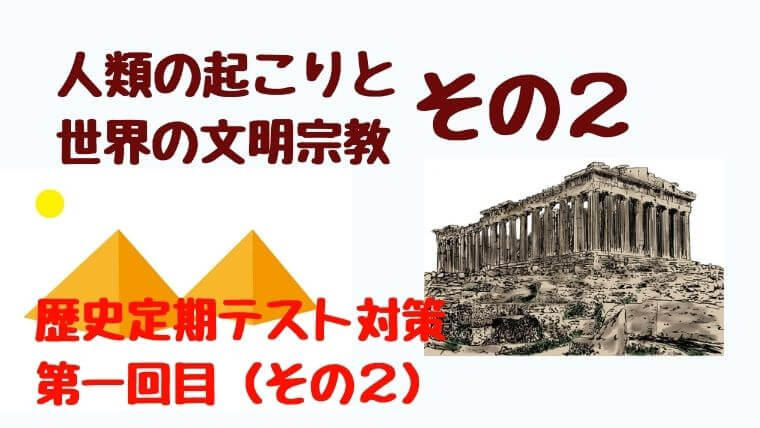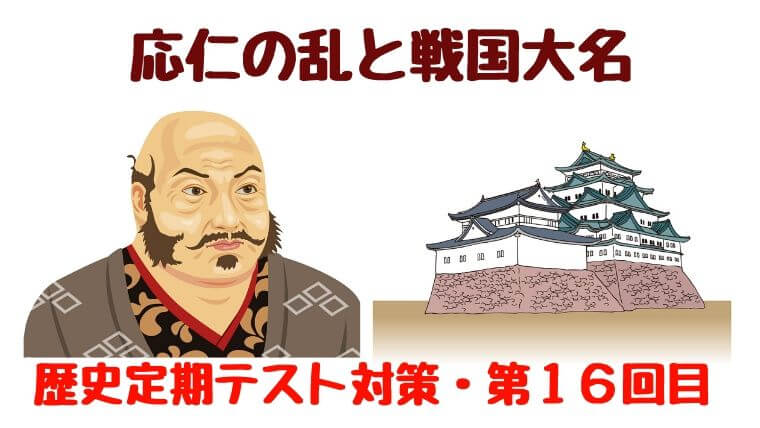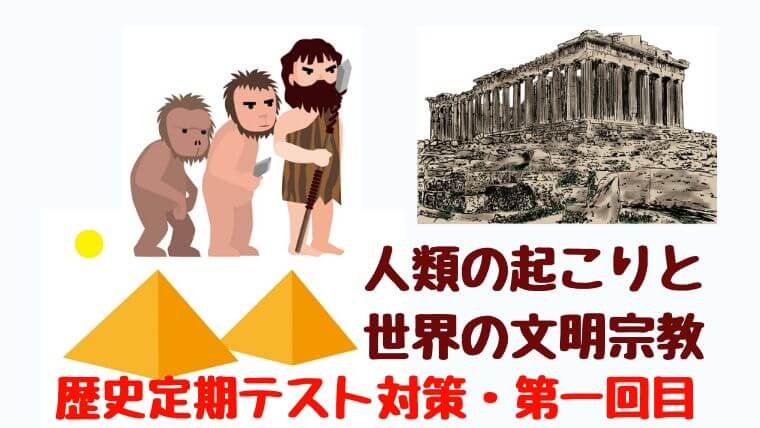改革を制すものは江戸時代を制す(後編)
前回に引き続き、江戸時代の諸改革です。
ここまで、徳川綱吉の政治、新井白石の正徳の治、徳川吉宗の享保の改革を見てきました。
それでは、後編に進みますよ。
田沼意次(たぬまおきつぐ)の登場
米を財源の中心に置いた幕府の財政では、豊作不作の影響が大きくなります。
金、銀の生産も伸び悩んでいた江戸中期。幕府の財政状況はかなり厳しかったと言えます。
将軍て大変なんだね。
時は流れ、将軍が第九代家重(いえしげ)第十代家治(いえはる)の頃です。
新たな改革者が登場します。老中の田沼意次(たぬまおきつぐ)です。

田沼は、従来の米による税収に頼らず、商業を活性化し金銭による税収を目指そうとしました。
良い案ですね。
田沼意次は株仲間(かぶなかま)を奨励し、彼らに特権を与える代わりに営業税を取るようになりました。
株仲間(かぶなかま)は、同業者同士が協力し、営業を独占するシステムです。
例えば、複数の八百屋同士が株仲間を組織し、幕府に営業を保護してもらいます。
幕府は株仲間から税金を得る代わりに、株仲間を保護します。
株仲間に入らない八百屋は、営業が出来なくなる仕組みです。
幕府は株仲間からの税金を、幕府の財源にあてました。
田沼意次は、この株仲間の制度を奨励し、どんどん株仲間を作らせ、営業税を徴収していったのです。
田沼意次の政治は、従来の農業中心の政治体制から商業中心の政治体制へ移行しようとしたところに特色があります。
幕府の財源確保手段である年貢米では、安定した財源確保が出来ないからです。
主な政策が株仲間の奨励
印旛沼(いんばぬま※千葉県)の干拓を行い新田開発
鉱山開発、蝦夷地(えぞち※北海道)の開発
俵物(たわらもの)の貿易※アワビなど海産物を俵に入れて輸出したもの。
田沼の政治により、幕府の財政も安定を見せつつありました。
ところが、貨幣中心の生活になり、ある問題が発生します。
賄賂(わいろ)の横行です。
地位や特権を金で買う風潮が生まれ、田沼意次は責任を問われます。
次いで1782年の天明の大飢饉と浅間山の噴火により各地で凶作。
結果百姓一揆や打ちこわしが頻発し、とうとう田沼は失職してしまいました。

寛政(かんせい)の改革
飢饉(ききん)や打ちこわし、一揆などで荒れた江戸。
これを立て直そうとしたのが老中、松平定信(まつだいらさだのぶ)です。
徳川吉宗のお孫さんに当たります。

松平定信は祖父徳川吉宗の政治を復活させようとしました。
質素倹約に努め贅沢を禁じる。
昌平坂学問所(しょうへいざかがくもんじょ)を建て、学問を朱子学(儒学)のみとする。
政治批判を厳しく禁止し、出版物も厳しく統制した。
借金で苦しむ武士を助けるため、借金を帳消しにした。
※これを棄捐令(きえんれい)と呼びます。
これが寛政の改革(かんせいのかいかく)の主な内容です。
結局、うまく行かなかった吉宗の享保の改革を真似たところでは失敗は目に見えていました。
極端な倹約や武士びいきの改革のため、あっけなく松平定信は失職しました。
田沼の政治のほうが良かったと皮肉も出るほどでした。
江戸幕府、最後の改革
そしていよいよ、江戸幕府の最後の改革になります。
天保の改革(てんぽうのかいかく)です。
老中、水野忠邦(みずのただくに)の政策です。

1841年に水野忠邦が行った改革です。
質素倹約を奨励し、営業を独占している株仲間を解散させる。
質素倹約は相変わらず進めることになります。
米が不作で価格があがり、一揆や打ちこわしが起こる。
結局江戸時代はこれの繰り返しでした。
幕府が手軽に出来ることと言えば、武士から庶民に至るまで贅沢を禁じることしかなかったのです。
そして、天保の改革と言えば、株仲間の解散です。
田沼意次の政策により、盛んになっていた株仲間を解散させました。
独占営業をやめさせ、個々人に営業を行わせることにより経済の活性化を狙いました。
アヘン戦争で清がイギリスに敗れ、異国船打払令(いこくせんうちはらいれい)をやめる。
忠邦が、欧米諸国には、武力ではとうてい敵わないことを知ったためです。
忠邦は、日本を訪れた外国船に対して燃料のマキや水を与え、丁重に帰ってもらいました。
江戸や大阪近辺の大名の領地を幕領(ばくりょう)にしようとした。
江戸や大阪を幕府直轄地にして来るべき外国との戦いに備え、防御力を高めようとしました。
当然元々の領主であった大名たちの反発を受け、失敗します。
結局大きな成果は出せず、忠邦は2年余りで失脚しました。
そうか、もう幕末だから外国がどんどん日本にやってくるんだ。
質素倹約を一生懸命やっているときに、中国がイギリスに負けたり。
幕府には、危機感も相当あったでしょうね。
そのため、1825年に出された異国船打払令を忠邦はやめることにしたのです。
清が負けるほどの欧米の力。
下手に敵することは避けなければなりませんでしたから。
なんか、一番嫌な時代に老中やった人のような気がする。
年貢米に頼り、一揆や打ちこわしが起これば質素倹約。
結局江戸時代の改革は大きな成果を得らえませんでした。
先生が言うように、米に頼ってしまったからなんですね。
安定した収入は、やはりお金じゃないと。
江戸時代は260年続きました。
いろいろ問題はありましたが、それほどの長期政権を続けられたことは、何よりも平和な時代だったからです。
確かに。江戸時代よりも前の政権は、すぐ変わったり、戦争ばっかりだったし。
江戸時代は食糧問題はあったけど、それ以外は平和だったね。
鎖国政策下、欧米は驚くほどの成長を遂げています。
日本は長く自分達の殻(から)に閉じこもっていましたからね。
貨幣経済が当然の欧米に比べ、米に重きを置く日本。
相当時代遅れだったことはわかるでしょう。
江戸の改革を年代順にまとめましょう。
根幹になるのは質素倹約(しっそけんやく)です。
年貢米を税収にしていたので、飢饉(ききん)が発生すると一気に幕府や藩は貧乏になります。
それでも幕府は年貢米を徴収します。
米屋は米の価格を上げて儲けようとします。
起こった民衆は打ちこわしや百姓一揆を起こします。
改革は失敗し、また新たな者が改革を行う。
しかし基本となるのは質素倹約。
年貢米依存では結局、時代遅れだということを知ります。
しかし、時は既に遅く、欧米の脅威がアジアへ進出を開始していたのです。
日本も間もなく、欧米の脅威にさらされていくことになります。
結局、江戸の諸改革は一定の成果をあげつつも、結局は元通りと言う形で終わりました。
そこで各藩が独自に動き出すことになるのです。
特に薩摩藩(さつまはん)と長州藩(ちょうしゅうはん)が大きく飛躍していくことになります。