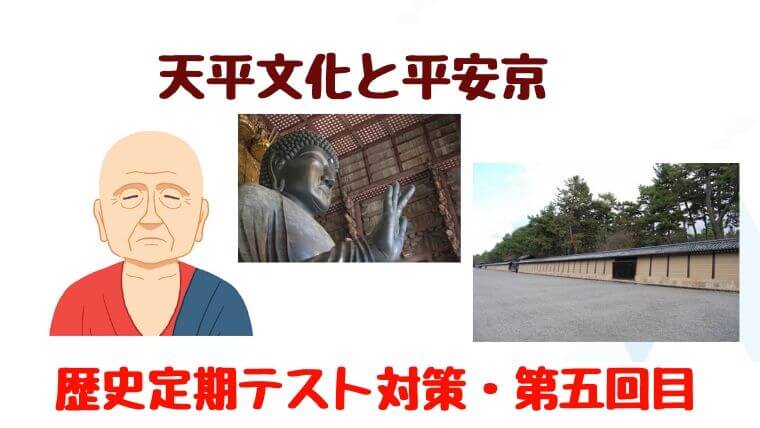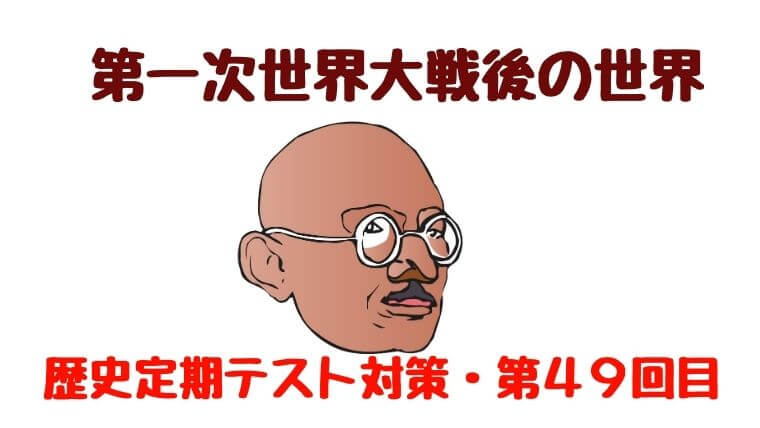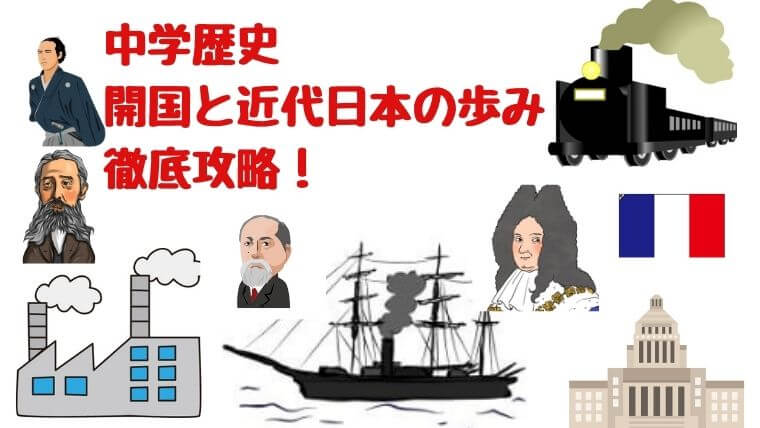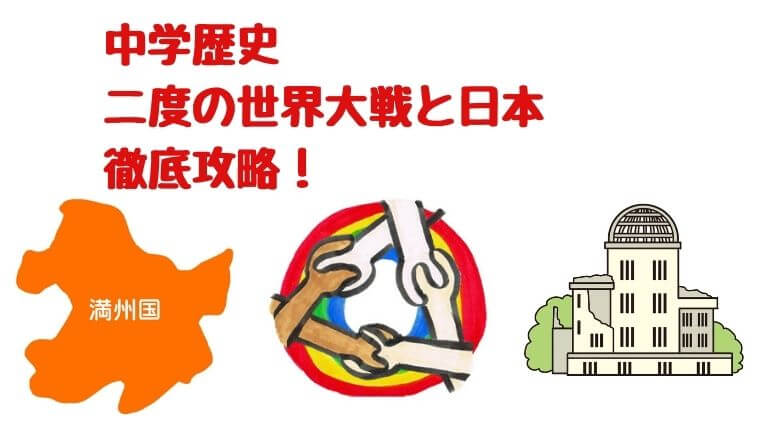デモクラシーと社会運動
デモクラシーと社会運動
中学歴史定期テスト対策の第50回目です。
1912年から1926年の約15年間は、日本では大正時代にあたります。
たった15年間ですが、日本は第一次世界大戦への参戦、関東大震災、普通選挙法の実現など激動の時代でした。
教科書は206P~211Pです。
デモクラシーとは民主主義を意味します。
大正時代は、人が人として生きる権利を求め、戦った時代でもあります。
労働者が労働条件の改善を求める戦い。
差別に苦しむ人々の戦い。
第一次世界大戦と民主主義が、どのようにつながっていくのかを読み解いていきましょう。
藩閥内閣と政党内閣
藩閥(はんばつ)政治に対しては、古くから批判がありましたね。
ちょっと確認しましょう。
明治政府は、江戸幕府討幕に貢献した薩摩(さつま)長州(ちょうしゅう)土佐(とさ)肥前(ひぜん)の各藩が主体となり政治を行いました。
これら4つの藩を藩閥(はんばつ)と呼び、藩閥による政治を藩閥政治と言います。
藩閥政治に対しては、批判が多く、同じ藩閥に属していた西郷隆盛や板垣退助は、藩閥に反抗しました。
武に訴える西郷隆盛は西南戦争を起こしました。
言論で訴える板垣退助の主張は、後に自由民権運動となり、全国に広がりました。
それでも藩閥による政治は続きました。
大日本帝国憲法が制定され、国会が開設された後も、藩閥内閣が政権を担当しました。
時には立憲政友会といった政党(せいとう)が政権を担当することもありましたが、藩閥の力は根強かったのです。
しかし、時代は藩閥の独裁体制を許さない動きになってきました。
民衆が結集し、ついに藩閥内閣を打倒する事件が起きたのです。
これを第一次護憲運動と言います。
時は1912年、立憲政友会の政党内閣が倒れ、藩閥の桂太郎(かつらたろう)が首相になりました。
再び藩閥内閣が成立したのです。
しかし、これに対して新聞や知識人は「藩閥を倒し、憲法に基づく政治を守れ」と声高に叫びました。
それに後押しされた民衆も立ち上がり、国会議事堂を取り囲む事件が起きたのです。
これが第一次護憲運動です。
「憲法を護(まも)る」運動です。
第一次護憲運動によって桂太郎は退陣を余儀なくされました。
特筆すべきは、民衆の力で藩閥内閣が倒されたということです。
こうして民衆の力によって世の中を変える時代が始まりました。
大正時代の始まりです。
西郷や板垣のような人物が藩閥を倒そうとしたわけではなく、民衆の力で藩閥を倒した。
一般民衆が主体の社会。
民主主義(デモクラシー)の社会ですね。
大正時代は、特に民主主義が強く主張された時代です。
大正デモクラシーという言葉は、こうして生まれたのです。
平民宰相(へいみんさいしょう)原敬
第一次護憲運動の結果、藩閥の勢力はかなり弱体化します。
そしてとうとう藩閥内閣から本格的な政党内閣への移行の時がやってきます。
第一次護憲運動で藩閥の桂太郎が退陣しても、変わらず政権は藩閥が担当しました。
しかし、桂太郎の退陣で、藩閥の勢力はかなり弱体化していました。
そのような中、第一次世界大戦が勃発します(1914年)
日本の経済は第一次世界大戦の影響で好景気となります(大戦景気)
戦争では軍需品の増強が必要になり、国内産業も活性化されるからです。
日本からは連合国やアメリカに工業製品の輸出が大幅に増えました。
一方で、好景気も行き過ぎると物価の上昇を招きます。
お金の流通量が増えると、物の価値が上がるのです。
つまりお金の価値が下がりだすのです。
好景気の日本でしたが、いつの間にか民衆の生活は苦しくなります。
さらに厄介なことが起こりました。
シベリア出兵(1918年)による米の買い占めです。
ロシアで発生した社会主義革命(ロシア革命)の余波を恐れた日本は、その余波を食い止めるためにロシアに軍を派遣しました。
これがシベリア出兵です。
その際の米の買い占めによって、米の価格が急上昇してしまいました。
生活が苦しい民衆は暴動を起こします。
この暴動を米騒動(こめそうどう)と言います。
これらの失態の責任を取り、藩閥の寺内内閣は倒れることになります。
そこでいよいよ政党内閣の出番ってわけだね。
国会に議席を持つ人間の集まりが政党です。
本来、議員の各集団(政党)の中でも最大規模の政党が政権を担当するべきなのです。
当時は立憲政友会が最大規模(最も議員数が多い政党)の政党でした。
ところが、日本では明治維新から大正時代まで、藩閥による政治が平然と行われていました。
討幕に貢献したという理由だけで、政治の場を独占してきたのです。
近代国家の仲間入りを果たしたはずの日本の、お粗末な部分でした。
ところが、米騒動をきっかけにいよいよ古き体制が崩れ始めるのです。
それがいわゆる本格的な政党内閣の始まりと呼ばれるものです。
こうして新たに内閣総理大臣に就任したのが原敬(はらたかし)です。
原は、薩長の出身でもない、平民から選挙を経て議員となり、首相になった人です。
初の平民宰相(へいみんさいしょう)の誕生です。
藩閥のしがらみもなく、正当な手続きを経て議員になり総理大臣になった人なんですね。
議員だけで構成する政党(立憲政友会)が政権を担当するのです。
陸海軍、外務の3大臣以外の大臣も全て立憲政友会の議員から選出されます。
それで本格的な政党内閣って呼ばれるんだね。
社会運動の広がり
何度も言いますが、大正時代は民主主義の意識が民衆に強く芽生えた時代です。
権力は人民に由来し、人民により行使されるという考え方です。
「国王とか一部の人間に権力があるのではない」という考え方ですね。
一人一人に平等に権利があるのです。
その権利とは。生きる権利、政治に参加する権利、教育を受ける権利・・・。
様々なものがあります。
今じゃ当たり前にみんなが持っている権利だけどね。
議会や国会、そして議員を選ぶ選挙権。
これらは自分が政治に参加する権利です。
一人一人が政治に携わるのは無理な話なので、より同じ考えの人を議員として選び、代表して政治を行ってもらうのです。
大正時代は、まさに人の社会に対する考え方の変換期だったんですね。
大正デモクラシー!
皮肉なことに、民主主義の考え方が急速に拡大していった要因には、第一次世界大戦も絡んでいます。
国家をあげての総力戦であった大戦は、おのずと民衆を社会に引きずり出すきっかけになったのです。
「俺たちは、私たちはこのままでいいのだろうか?」
これまで国家の言われるがままに動いていた民衆も、戦争という政治に無理やり引き込まれた結果、国家の在り方、社会の在り方に対して疑問を持つようになったのです。
そのような民衆の感情を後押ししたのが、吉野作造(よしのさくぞう)の民本主義(みんぽんしゅぎ)という思想です。
みんぽんしゅぎ?
政治の目的は、一般民衆の幸福や利益にあるとしました。
そのためには一般民衆の意向に沿った政策決定が重要だとしました。
この吉野作造(よしのさくぞう)の思想を、民本主義と言います。
民本主義実現のためには、誰にでも開かれた平等な政治の実現のために、普通選挙制度の確立、藩閥ではなく、政党が内閣を組織する政党内閣制の実現が重要であると説いたのです。
第一次世界大戦によって、社会の在り方について考え始めた民衆は、この民本主義の思想に後押しされ、強く民主主義について考えることになります。
国家の言いなりから、自分たちが主体の社会。
大きな変換ですね。
大正時代すげー。
もう一人、美濃部達吉(みのべたつきち)の天皇機関説も大正デモクラシーに大きな影響を与えています。
その国の在り方を決める権利(主権)は国家にあり、天皇は国家の最高機関として憲法に従って統治するという
憲法学説を天皇機関説と言います。
天皇機関説と政党内閣については、下の記事で詳しく説明していますので、興味のある方はご覧ください。

民主主義思想の高まりは、あらゆる差別問題にまで飛び火しました。
過酷な労働者の労働条件、部落、性別、それらの差別に苦しむ人々が平等な社会を求めて立ち上がりました。
労働運動
第一次世界大戦によって、日本は好景気になり労働者が大幅に増えました。
当時の労働者の労働条件や環境は劣悪なもので、それらを改善する要求が増加しました。
これが労働運動です。
労働者の立場は、雇い主の資本家と比べれば非常に弱いものでした。
労働者達は、自分たちの身を守るためにも労働運動を展開したのです。
ストライキ(労働争議)は、労働者が雇い主に対して労働条件の改善を求めるために集団で労働をストップしてしまうことを言います。
第一次世界大戦前に結成された友愛会は、労働組合の全国組織へと発展しました。
1920年に日本で最初のメーデーを主催しました。
メーデーとは、労働者の祭典であり、最低賃金制や8時間労働を要求しました。
さらに労働組合は1921年に日本労働総同盟へと改称し、労働者の団結と、労働条件の改善を求めました。
これだけ労働運動が盛んになると、社会主義運動なども起きたのでしょうか?
ロシア革命の後でしたから、当然社会主義運動も活発化しました。
1920年には日本社会主義同盟が結成されたりしました。
国家が成長すると、必ず労働者問題は起こるんだね。
ロシア革命の影響で共産主義意識が高まりましたからね。
日本共産党が結成されたりしました。
農村では小作料の減額を求め、小作争議が起こりました。
1922年には、全国農民組合が結成され、農家の権利を守る運動を展開しました。
全国水平社
実は、江戸時代は深刻な差別がありました。
人として扱ってもらえないなど、よくある話でした。
人として扱ってもらえない・・・・。
彼らは、ある一定の地域に住まわされるようになり、その子孫が住む場所は部落(ぶらく)と呼ばれ差別の対象になりました。
部落差別に苦しむ人々は、自力で差別からの解放を目指す運動を展開します。
部落解放運動(ぶらくかいほううんどう)です。
1922年には、全国水平社が結成され、部落解放運動は全国に展開しました。
女性運動と平塚らいてう
当時は、女性への差別も深刻な問題でした。
平塚らいてうは、女性の解放を訴え、1920年に新婦人協会を設立しました。
女性にも政治に参加する権利などを求めました。
普通選挙法の実現
最後は普通選挙の実現です。
納税額による制限を撤廃し、満25歳以上の男子に選挙権を与える普通選挙法です。
でも男子だけなんですね。
納税額の制限が撤廃されただけでも大きな前進ですけどね。
25歳以上の男子なら誰でもだから、相当人数は増えたんじゃないかな?
有権者は4倍に増えました。
また同時に治安維持法(ちあんいじほう)が成立しました。
これは共産主義を取り締まるためのものです。