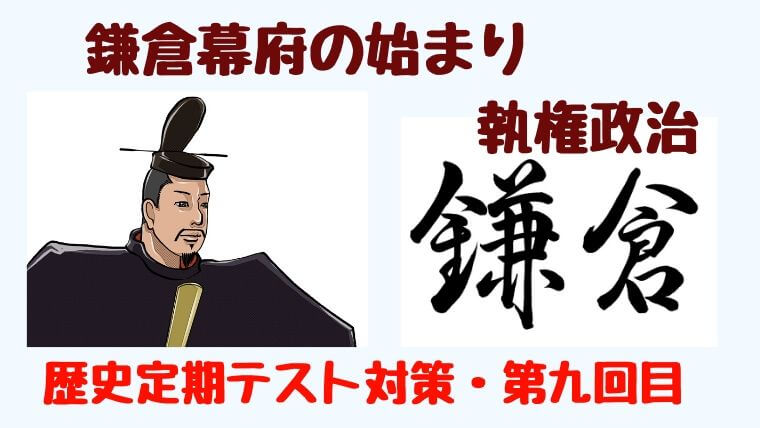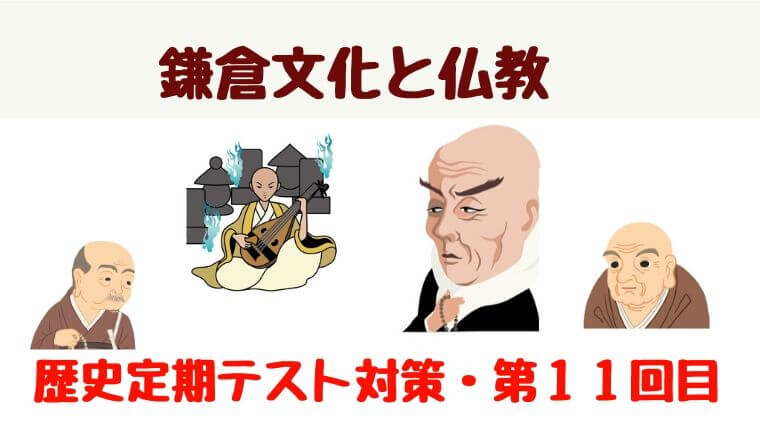1853年運命の時。黒船来航
1853年運命の時、黒船来航
中学歴史定期テスト対策の第38回目です。
欧米列強のアジア侵略が激化する中、とうとう日本にも運命の時がやってきます。
黒船の来航です。
教科書は154P~155Pです。
キーワードは不平等条約(ふびょうどうじょうやく)です。
鎖国政策が崩壊し、開国を余儀なくされた日本。
そこでは不平等条約という過酷な条件が課されました。
以後、この不平等条約のために日本は苦しむことになります。
東インド艦隊司令長官ペリー
ヨーロッパ諸国が東アジア進出を試みるように、アメリカもまた東アジアを目指しました。
長い太平洋を横断する際に、日本は燃料補給などの中継地として重要な地点にありました。
そこでアメリカは東インド艦隊司令長官ペリーを日本に派遣しました。
日本の鎖国政策をやめさせ、港を開放させるためです。

突然、黒煙をふかしながら浦賀沖(神奈川県)に現れた4隻の黒船。

鎖国下の江戸時代の人々は度肝(どぎも)を抜かします。
巨大な鉄の塊が、人力ではなく勝手に動いている。
そして立ち並ぶ大砲。
産業革命とは無縁の江戸時代の人々にとって、目を疑うような光景でした。
1853年、ペリー来航です。
さて、思いだしてください。
この頃の江戸時代は、どのような出来事があったでしょうか?
歴史の勉強は、必ず世界とのつながりを意識してください。
ここまでの勉強で、ペリー来航には産業革命がおおいに関係していたことがわかったはずです。
産業革命の影響がどのように日本の歴史に影響していったのか、よく意識してください。
ペリーの来航がきっかけで、鎖国下の江戸時代がようやく世界とのつながりを取り戻すのです。
天保の改革(てんぽうのかいかく)が行われていた頃かと・・・。
水野忠邦(みずのただくに)か!
二人ともいいですね。
天保の改革は1841年です。
水野忠邦は2年で老中をやめさせられています。
ということは、全然かぶってなかったですね(汗)
そうですね。しかし、年代の並べ替え問題では、この微妙な年代の違いは問われますよ。
ですから、必ず前後の出来事は意識しましょう。
そういうとこで差が出るって先生言ってたもんな。
では、天保の改革が行われたころ、世界で起きていた出来事には何がありましたか?
1841年・・・1841年・・・。
そうだ!アヘン戦争です!1840年です。
そのとおり!しっかりアヘン戦争の内容も覚えておいてくださいね。
ついでにアヘン戦争の講和条約・・これは何でしたか?
こ、講和条約!?な、なんだっけ?
南京条約(なんきんじょうやく)です!
お見事です!
すげ
南京条約の内容も説明できるようにしましょうね。
開港した5つの港名、場所、賠償金額、どこをイギリスに譲り渡しましたか?
そ、そこまでは覚えてなかったです・・・。
賠償金を払うために、清は重税を国内に課しましたね。
するとどういう反乱が起きたのですか?
その結果、イギリスと清はどうなったのですか?
タラー(汗)
いかがですか?私がその気になれば簡単に平均点の5点は落とせますよ。
さらに難しくもできます。
勘弁してほしい。
でも、今の内容は、前回のテスト対策37回目(ヨーロッパのアジア侵略)で全て説明しています。
ただ、自分が覚えきれていないだけなんですよね。
コツは産業革命を中心に、世界がどう動いていったのかを追うことです。
なぜいきなり教科書で世界史の授業が入ってきたのかが、わかると思いますよ。
ふ、復習しよう・・・。
さて、話を戻します。
アヘン戦争の清の敗北は、日本国内を恐怖させました。
そしてとうとう恐るべき事態がやってきたのです。
それが黒船ペリーの来航だったのです。
日米和親条約(にちべいわしんじょうやく)
突然の来訪者に江戸は大混乱に陥りました。
ペリーは日本に開国させるため、大統領の国書を江戸幕府に渡しました。
翌年、回答をもらうことを約束し、ペリーは引き上げていきました。
幕府はいかに対応すべきか困り果て、大名や朝廷にお伺いをたてました。
これまで、政治は幕府の専門分野で行い、大名や朝廷には事後報告だった江戸幕府。
国の一大事に大名や朝廷に相談を持ちかける様を見て、周囲はこう思いました。
「もはや幕府はあてにならない」
江戸時代の諸改革、失敗しては百姓一揆や打ちこわし、そしてまた苦し紛れの改革。
ただでさえ幕府の政治に疑問を持たれていた矢先に、外国の脅威を目の当たりにした各藩や朝廷。
幕府には任せてはいられないという思いが勝り、やがて大名や朝廷の発言権が強まっていくことになります。
1854年、ペリーは約束通りに来訪しました。
幕府はやむなく日米和親条約(にちべいわしんじょうやく)を結びました。
その結果、下田と函館の2港を開き、アメリカの領事を下田に置くこと、そしてアメリカ船に食料や水、石炭を供給することになりました。

こうして江戸幕府の鎖国政策は崩れ去り、日本は開国することになったのです。
最後はあっけなかったね。
あっけないほど、力の差が歴然としていたのです。
ちなみに台場は、江戸湾(東京湾)の防備のために砲台を置いた場所です。
大砲が届く距離を計算して、設計されていました。

ちなみに島のとこですよ。
もちろんレインボーブリッジなどはありませんでしたからね。
不平等条約の締結(ていけつ)
1856年、アメリカの総領事として日本に着任したハリス。
ハリスは幕府に通商条約を結ぶことを強く求めました。
通商条約とは、商取引を行うための条約です。
ここは日米和親条約と混同するところです。
日米和親条約は、港を開くことを約束し、下田に領事を置くことを認めた条約です。
いわば国交(こっこう)を持ちましょうという条約です。
いったん国を開かせたアメリカは強気に出てきます。
今度は商取引を行うように日本に迫ってきました。
こうしてアメリカと結んだのが日米修好通商条約(にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく)です(1858年)
ところがこの条約は、日本を窮地に陥れるための条約でした。
まず、この条約を締結するにあたり、幕府の大老井伊直弼(いいなおすけ)は朝廷の許可を得ませんでした。
井伊直弼の独断の行動は、諸藩や朝廷の怒りを買うことになります。
函館、神奈川、長崎、新潟、神戸の5港を開き、そこでアメリカ人が自由に貿易を行うことを認めました。
なぜ日米修好通商条約が不平等条約と呼ばれるのかは、以下の通りです。
関税自主権(かんぜいじしゅけん)がなく、領事裁判権(りょうじさいばんけん)を認めること。
関税とは日本への輸入品にかける税金のことです。
安い外国産の製品が輸入されると、国内の製品が売れなくなります。
国内の産業を守るために、外国からの輸入品には関税をかけ、価格をあげて国内の製品を守ることができます。
関税自主権がないとは、まさにこの関税をかけることができずに、外国の安い製品がそのまま売られることになります。
国内の同産業は大打撃を受けることになります。
領事裁判権を認めるとは、外国人を日本の法律で裁けなくなるということです。
通常、外国人が日本で犯罪を犯せば日本の法律で裁くことになります。
しかし、領事裁判権を認めてしまうと、その外国人を日本の法律では裁けなくなります。
このような日本に一方的に不利な条約を不平等条約と言います。
詳しくは、以下をご覧ください。

こんな一方的な条約を結ばれてしまうって、本当に日本とアメリカの差は大きかったんだね。
さらに安政の五か国条約を結ぶことになります。
アメリカと不平等条約を結んだために、次々に諸外国とも不平等条約を結ばされたのです。
(オランダ、ロシア、イギリス、フランス)
ヨーロッパばかりですね。
やはり産業革命の力はすごいですね。
井伊直弼(いいなおすけ)って人、いろいろ勝手に決めてしまって大丈夫なのかな?
井伊直弼(いいなおすけ)は後日、暗殺されてしまいます。
やはり相当恨みを買われてしまったのでしょう。
ちゃんと相談していれば良かったのに・・・・。
確かにそう言われることが多い人です。
しかし、当時、外国の恐ろしさを確実に把握している人は、幕府の人間がほとんどでした。
反対をはねのけてでも、外国には逆らわないという方針を貫かなければならなかったのかもしれませんね。
そうか、実際に黒船を見たことない人達は、なんとでも言えますもんね。
外国の恐ろしさを知る人、知らない人。
この温度差が、やがて日本国内を内乱へと進ませていきます。
開国派と尊王攘夷(そんのうじょうい)派として争っていくことになるのです。