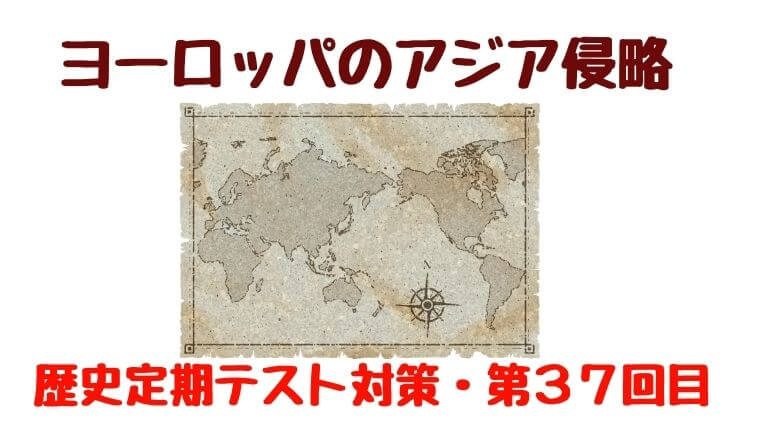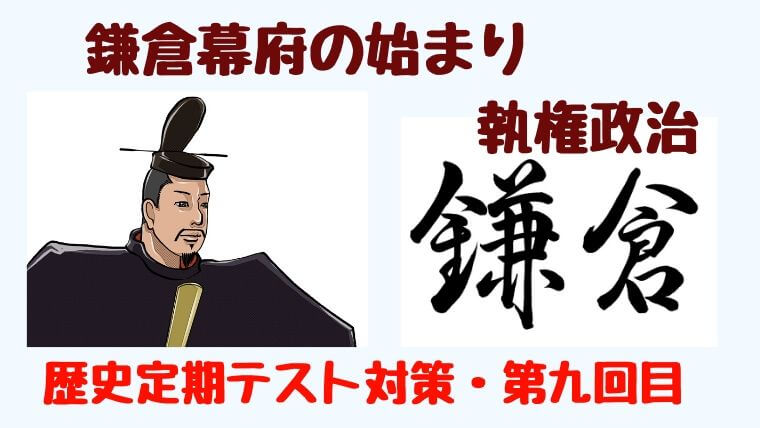江戸の街づくりは天才的!
江戸時代の街づくりは天才的!
中学歴史定期テスト対策の第29回目です。
教科書は122P~123Pです。
江戸時代の街道整備と都市の繁栄です。
江戸時代には全国的に寛永通宝(かんえいつうほう)が流通しました。
地方の特産品も江戸に運ばれ、大いに産業も賑わいました。
これらを可能にしたのは、江戸時代の巧妙な街づくりです。
江戸を中心に全国各地へ続く街道(かいどう)を整備しました。
そして、大阪から江戸への航路も整いました。
整備された街道と航路。
これらによって日本全国の物流が盛んになりました。
江戸時代の街道(かいどう)
現在の東京都の基盤、江戸の街づくりは非常に計算しつくされていた作りです。
江戸の中心に各地方に延びる街道が整備されました。
現代の経済の要(かなめ)を担う東京が、既に江戸時代に完成されていました。
東京の現在の姿が、江戸時代には既に作られていたと言うのは驚きですね。
試験には全く関係ありませんが、江戸の街づくりには、南光坊天海(なんこうぼうてんかい)という僧が関わっていたとされています。
108歳(134歳という説あり)の長寿を全うした天海。
江戸の街づくりには、家康の右腕として活躍した天海の働きは欠かせないものでした。
天海は風水に徹底してこだわり、江戸城を中心として街の配置にこだわりました。
そして街道(かいどう)の整備です。
江戸を中心に、各地方へアクセスできる街道を整備しました。
この街道整備のおかげで、江戸時代の物流は盛んに行われたのです。
実は、この南光坊天海は明智光秀説があります。
な、なぬ?光秀は本能寺の後、死んだのでは?
そこははっきりとわかっていないところですね。
いろんなミステリーがあるところが歴史の面白いところです。
現実的に、光秀だという可能性は高いのですか?
そのあたりは、また別の機会にお話ししましょう。
まずはテスト対策をやりましょうね。
ちぇ、つまんねーの。
下の図を見てください。

各街道と航路を示した図です。
なんか今も良く聞く名前だね。
新幹線とか。
東海道新幹線、日光街道、中山道・・・。
ほんとだ!
これらの街道が整備され、江戸を中心に大阪や京都が結ばれました。
大勢の人々が行きかい、途中の都市も大いに賑わったことは想像できると思います。
そうか、人が一人二人歩ける道ではなくて、大勢の人が行き来できる道を作ったんだね。
工事は大変だったろうな。
それが道路として整備されて、現代社会でも交通の要になっているんですね。
人が動けば金が動きます。
江戸時代は交通整備により、経済活動が活発化した時代なんですよ。
おや?この素っ裸の人は?

この人たちは飛脚(ひきゃく)です。
全国に手紙や荷物を届けました。
すげー!走って移動したんだ。
もちろん、あまりに遠方の場合は同業者へのリレー方式でつないだりしました。
隣町まで行って、別の人へ託すなど。
それでも相当な距離を走りましたけどね。
多くの人が遠方から来るのでは、宿も必要ですよね?
大きな街道沿いには、宿場が置かれました。
旅人だけではなく、遠方から来る参勤交代の大名行列にも使われました。
すげー!大名も泊まったんか!?
さすがに一般人と同じ場所に泊まるわけにはいきませんからね。
大名や幕府の役人が宿泊する宿場は本陣(ほんじん)、庶民が宿泊する場所は旅籠(はたご)と呼ばれて区別されていました。

上の写真は関所(せきしょ)です。
東海道の箱根関所です。
地方の大名たちが幕府に反抗するのが目的です。
どんなことをした場所なんですか?
人と物の取り締まりです。
参勤交代では、江戸に各大名の妻が、人質として住まわされていましたね。
その妻たちがひそかに領地に戻らないように見張りました。
そうか。人質がいるから大名たちは江戸幕府に反抗できないんだもんね。
江戸から脱出しようとする女性を「出女(でおんな)」と呼び、警戒しました。
関所では、江戸方面への鉄砲の持ち込みが警戒しました。江戸で戦争を起こさせないためです。
江戸に入ってくる鉄砲を「入り鉄砲(いりでっぽう)」と言い、これも厳重に警戒されました。
入り鉄砲に出女。
取締も厳しそうですね。
菱垣廻船(ひがきかいせん)樽廻船(たるかいせん)
陸路のほかにも、航路も発達しました。
商業の発達した大阪から、物資を江戸へ大量に運ぶ手段を確保するためです。
もう一度先ほどの地図を見てみましょう。

大阪から江戸へ、木綿や油、醤油(しょうゆ)を運ぶ船が菱垣廻船(ひがきかいせん)。
酒を運ぶ船が樽廻船(たるかいせん)です。
東北地方や北陸の年貢米を大阪や江戸に運ぶためのルートを確認しましょう。
オレンジ色が東廻りルートです。
緑色が西廻りのルートとなります。
街道と航路。
これらの整備によって、江戸は大都市として成長していくことになります。
三都(さんと)の繁栄
江戸、大阪、京都を三都(さんと)と言います。
江戸は将軍の城下町が置かれ、将軍のおひざもとと呼ばれました。
武士や職人、商人が集まり、江戸中期には100万人を超える大都市に成長します。
大阪は全国の商業の中心地で天下の台所と呼ばれます。
北陸や西日本の大名は大阪に蔵屋敷(くらやしき)を置き、年貢米や特産品を蓄えました。

京都には朝廷や大きな寺社があり、学問や文化の中心となりました。
西陣織(にしじんおり)や京焼きなどの工芸品も生産されました。
そう考えると、東京の歴史って意外に浅いんですね。
徳川幕府が開かれてから約400年。
これほどの大都市に成長するとは、誰も想像しなかったでしょうね。
家康が初めてやってきた頃の江戸が、ただの湿地帯だったなんて、信じられないな。
両替商や株仲間が発達したのも江戸時代です。
株仲間(かぶなかま)は、同業者同士が協力し、営業を独占するシステムです。
例えば、複数の八百屋同士が株仲間を組織し、幕府に営業を保護してもらいます。
幕府は株仲間から税金を得る代わりに、株仲間を保護します。
株仲間に入らない八百屋は、営業が出来なくなる仕組みです。
幕府は株仲間からの税金を、幕府の財源にあてました。
両替商は、銀行のようなものです。
当時、東日本は金、西日本は銀が主流に流通しました。
金と銀の価値は違います。
東日本の人間が西日本に来ると、金を銀に交換しなければなりませんでした。
その交換を両替商が行ったのです。
両替商は、金と銀を交換する際に、手数料を取り儲けていました。
江戸の三井家、大阪の鴻池(こうのいけ)家は、大名にも貸し付けを行い、莫大な利益をあげました。
以上、江戸時代の街道作りと、都市の発達でした。