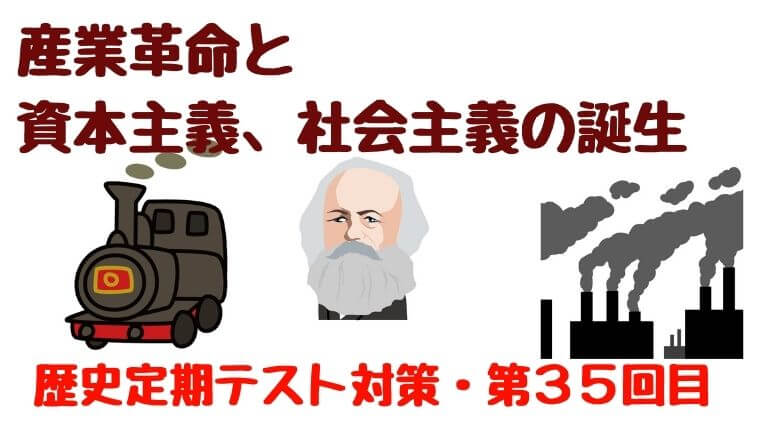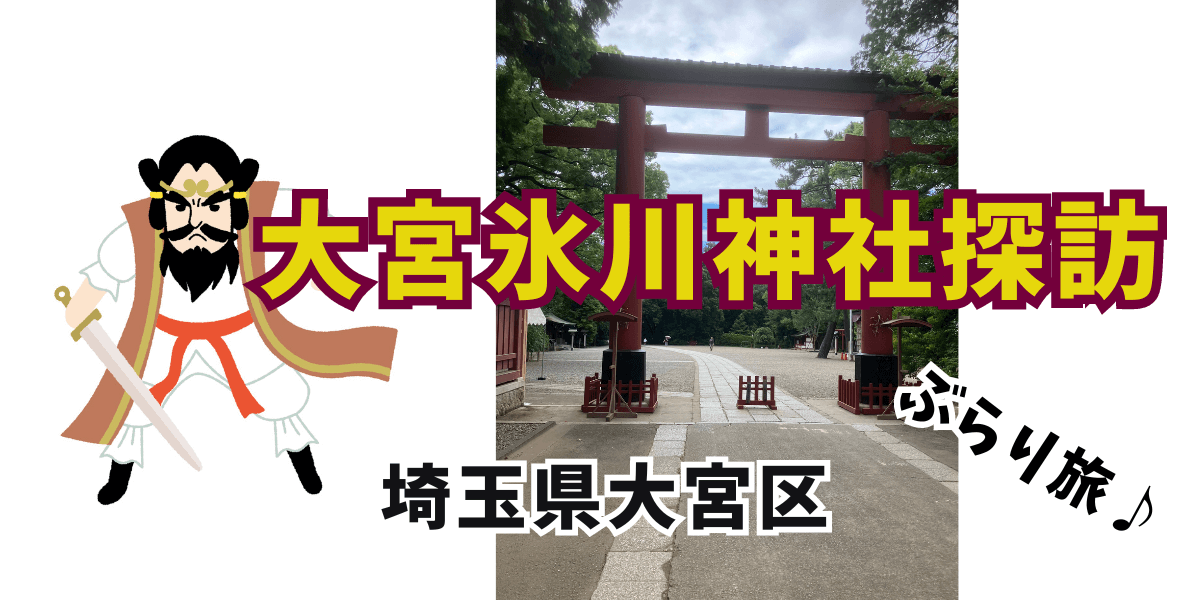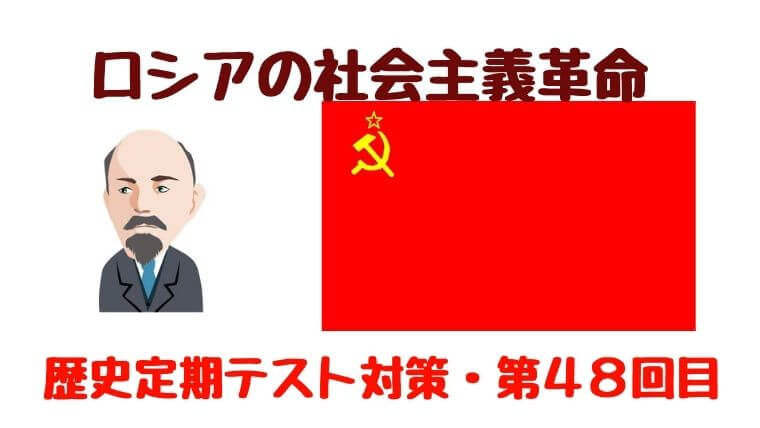江戸の街道整備と暮らし
江戸の街道整備
徳川幕府が開かれてから江戸は急成長して行きます。
江戸はやがて国際都市「東京」へと変わります。
江戸幕府が開かれた当初、江戸の人口は約10万人ほどでした。
しかし18世紀に入ると人口は100万人を超え、世界でも有数の大都市に成長しました。
そして現在(2019年)では、東京都の人口は推定1200万人です。
江戸初期から100倍以上に増加した人口。
このことからも江戸の都市計画がいかに優れていたものであったかがわかります。
その都市計画のひとつに、江戸の街道整備があります。
都市の発展には交通網の整備が欠かせません。
人の往来、物流ともに、どの方面からもアクセスしやすいこと。
そして、交通網の基盤となる道路には、それなりの広さや路面の整備されていること。
また遠方からの物資輸送のため港町が整備されていること。
政治・経済・文化の中心となる江戸。
徳川幕府は、この交通網の整備と経済発展により急成長を遂げていきます。
五街道
幕府が置かれた江戸と京を結ぶ道が東海道です。
他に中山道(なかせんどう)日光道中、甲州道中、奥州道中の5街道があります。
他には脇(わき)街道と呼ばれる主要道路も置かれました。
聞いたことがある道の名前だね。
各街道には一里(いちり)毎に目印を置きました。
一里ごとに盛り土を置き、塚(つか)を作ります。
それを一里塚(いちりづか)と呼びます。
何の目印なのですか?
江戸まであと何里か。あるいは江戸から何里離れたかの目印です。
江戸の中心地である日本橋が五街道の起点になっています。
そこから各街道の一里毎に一里塚が置かれます。
一里は約4kmです。
三里で約12kmです。
中山道の三里目「志村一里塚」(※現板橋区)は国家指定の史跡にされています。
「志村一里塚」は日本橋から12km離れた地点であることがわかります。
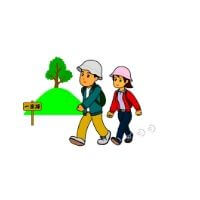
これは通行人にはわかりやすくて良いアイデアですね!
それから各街道には宿場が置かれ、旅人や大名行列の宿になりました。
こうした交通路と宿場が充実したおかげで、江戸に人が集まりやすくなりました。
すごい!私だったら「江戸に行ってみたい!」ってなるだろうな。
思うだけではなく、実際に行きやすくなった。
それが江戸の街道整備の素晴らしさです。
このふんどしの人はなんだ!?

この人達は飛脚(ひきゃく)と言いますよ。
飛脚とは、ふんどし姿で街道を走り、手紙や荷物を各地に届ける配達業です。
江戸から京へは幕府と朝廷間の連絡もあり、飛脚の存在はとても重要です。
しかしこの距離を一人で走り続けるわけではありません。
飛脚は同業者が各宿場に滞在しており、次の宿場で別の人間にバトンタッチし入れ替わり配達します。
これをリレー方式と言います。
江戸と京を結ぶ東海道には53の宿場町がありました。
例えば、一人2宿場を走り約27人のリレーでつなげば、一人約20km走ることになります。
江戸から京へは約500kmありますが、早くて3日で届けたそうです。
歌川広重(うたがわひろしげ)の「浮世絵(うきよえ)」東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)が有名です。
江戸時代に入ると、街並みや人々の生活の様子がかなり現代人に近づいてきますよ。
京都まで3日って!?今の運送業とあまり変わらないですね!すごい!
ランニングシューズではなく草履(ぞうり)ですからね。
しかも現代と違って、でこぼこ道です。大変な仕事だったと思います。
お、俺嫌だそんな仕事・・。
水運も発達しましたよ。
大量の物資を運ぶにはやはり水運が一番です。
木綿や油、醤油(しょうゆ)を運ぶ菱垣廻船(ひがきかいせん)
酒を運ぶ樽廻船(たるかいせん)
これらの運搬船は定期的に大阪から江戸まで往復し物資を搬送しました。
また東北や北陸の年貢米を大阪や江戸に運送するのに西廻り航路(にしまわりこうろ)や東回り航路(ひがしまわりこうろ)を開きました。

株仲間(かぶなかま)と両替商(りょうがえしょう)
江戸時代初期から株仲間(かぶなかま)と呼ばれる制度が始まりました。
かぶなかま?
同じ商業を営む(同業者)の組合のことです。
座(ざ)と同じことですか?
よく覚えていましたね。やよいさん。
座は室町時代にあった団体ですね。
こちらも同業者同士が組合(座)をつくり、営業を独占しましたね。
時代が違うだけ?
それもありますが、組合を保護してくれるところがそもそも違います。
座は武士や貴族、寺社に税を収めて保護してもらいました。
株仲間は?
株仲間の保護者は幕府です。国の保護です。
株仲間とは同業者による組合のことです。
例えば江戸に大きな魚市場があるとします。
そこに所属しなければ漁業を行い、魚を自由に売りさばくことは出来ません。
それが株仲間です。
その魚市場に所属できる権利。
この権利のことを株と言います。
この株を所有することで魚市場の仲間入りが認められます。
反対にこの株を持たなければ、勝手に漁業を行い魚を売り裁くことはできません。
株仲間は幕府や藩に税金を納めて、保護してもらっています。
そこに属さない個人営業者は一切保護されず締め出されてしまいます。
いかに安く新鮮な魚を仕入れ、庶民から人気のある魚屋でも、です。
幕府や藩、株仲間の双方に取って有益な仕組みでした。
幕府は米の税収以外に安定して得られる税を確保しようと考えました。
米などの年貢(ねんぐ)による税は、その年により収穫量が変わり、安定した税収を望めません。
そこで商人や職人たちからのお金による税収を考えます。
それが株仲間を保護することにより得られる税収でした。
座は信長の時に楽市楽座(らくいちらくざ)に変わりましたよね?
そうです。楽市楽座の内容は覚えていますか?
確か自由に商売出来るようになったとか・・・。
そうです。座を廃止したんですね。
座に入らなくても自由に商売が出来るようにしました。
座に入らなければ、安くて質の良い物でも売ることは出来なかったんですよね。
結果、庶民にとっては全く利点がありませんでした。
誰でも安くて質の良い物が欲しいですよね。
しかし、それらは座に排除されてしまいました。座に入っている業者たちが扱うものしか購入出来なかったのです。
じゃあ、質が悪くても、座が高値で売りつけて来たら・・・・。
庶民はそれを買うしかなかったのです。それを廃止し、自由な商売を取り入れたのが信長です。
楽市楽座により新鮮で安い品々が地方から集まりました。
庶民は大喜びです。結果、人がたくさん集まってきますね。
信長は戦だけでなく、経済面でも天才的な一面があったのです。
株仲間もやっぱり同じような道をたどるのですか?
株仲間により価格を決められると、庶民はそれに従わざるをえなくなります。
個人で安くサンマ1匹50円で売ろうとしても、株仲間が1匹150円と設定したら庶民は150円で買うしかありません。
庶民の敵!!
結果、物価の高騰(こうとう)を招き、混乱が起きます。
このあたりの話は、また後日行いますね。
株仲間と呼ばれる団体があった。
今日はそれだけ抑えてください。
両替商(りょうがえしょう)
江戸時代は金貸しの時代でもあります。
金を売ると言う商売です。
どんな仕事ですか?
お金を貸して利息を取る。
この利息で利益を上げていきます。
銀行ってことだね。
有名なところで江戸の三井家、大阪の鴻池(こうのいけ)家があり、大名にまで金を貸していました。
だ、大名にまで!!?大名って金持ちじゃないの!?
江戸の街並みを作り、街道を整備し江戸城を改修すること。
そうした事業は外様大名を中心とした各大名の出資から行われました。
他にも参勤交代などで財政難になっていた大名もいましたからね。
大名のみんながみんな金持ちではありません。
大名と言えど大変な時代だったんですね・・・。
三越(みつこし)は知ってますね?
これは三井高利と言う人が「越後屋(えちごや)」呉服店を営んだことに由来しています。
おお!三と越!
呉服は従来、富裕層しか購入できない物でしたが、「安く多く」をモットーに庶民に対して商売繁盛させていったのです。
三越の歴史ってそこから始まるんですね!
他には金貸し業として、現在の三井住友銀行などがあります。
ちょっと後の話になりますが、三井・住友・三菱などが一族による企業独占をして、財閥(ざいばつ)と呼ばれます。
な、なんか難しい・・・。
結局財閥も、国家に著しく関与したとして、第二次世界大戦後アメリカGHQにより解散させられます。
このあたりは明治時代に入ったらやりましょう。
今は財閥と言う言葉だけ覚えておいてもらえれば良いですよ。
武家諸法度(ぶけしょはっと)とか街道整備。
飛脚に株仲間に両替商。
江戸時代おもしろいです!
三越が江戸時代に関係してるのはびっくりした!三井住友とかよく聞くもんね。
次は日本史上平和真っ盛りな時代、元禄文化の登場です!