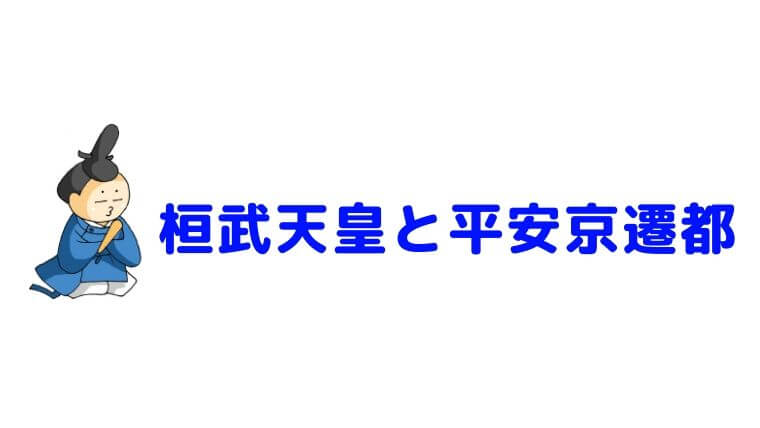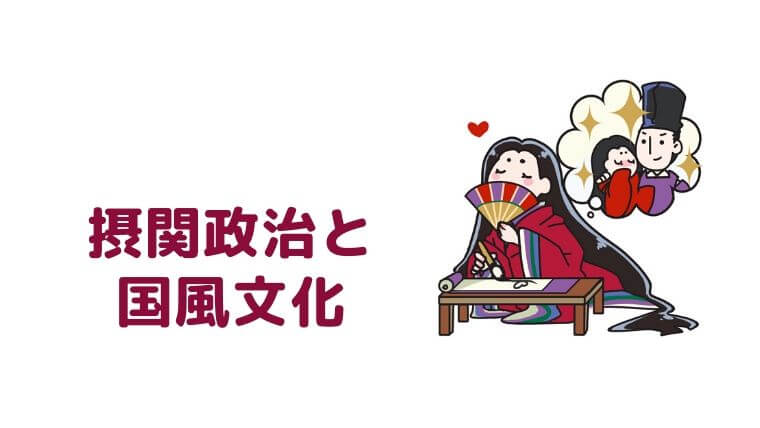律令制度の仕組み(後編)
律令制度の完成
律令制度の仕組みとして、五畿七道と二官八省のお話しをしました。
それが前回の内容でしたね。内容は理解出来ましたか?
天皇中心の政治が地方まで行きわたるように、七つの道路と行政区を整えました。
天皇一人だと大変だから、いろんな役割を決めてみんなで仕事を分担したんだな。
そのとおりです。全国を五畿七道にわけて、太政官と八省、国郡里制により各地の政治を行ったのですね。
律と令の法整備
和同開珎の使用
平城京の整備
公地公民の制の整備
五畿七道の整備
二官八省の整備
これらの整備により、日本が目指した律令国家は完成しました。
天皇中心による国家支配体制が出来上がったのです。
こうして律令制度の完成は成ったのですが、その基本となる公地公民の制についての話をしていませんでしたね。
そう言えば、天皇中心の話が出たときに、真っ先に出たのが公地公民の制と言う言葉でした。
土地と人民を天皇の物とするってやつ?
この公地公民こそが、律令国家の仕組みを支える土台です。これを詳しく見ていきましょう。
班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう)
公地公民の制により、各地の豪族が有していた土地や人は、全て天皇が支配することになりました。
大化の改新で蘇我氏が滅び、天皇の力が強まったから実現できたんですね。
さて、実際、土地と人民が天皇の物になったからと言っても、それをどう活用していくかが問題になります。
一人で土地を持ってても仕方ないもんね。
そこで、いったん豪族から天皇に返させた全ての土地を、国民一人一人に分配していくことにしました。
すごい!太っ腹!
と、思ってしまいますが、実は国民にとっては厳しい制度でした。
詳しくは以下の通りです。
公地公民の制の下、人民は良民と奴婢(ぬひ)(奴隷)にわけられ、
6年ごとに作られる戸籍に登録されます。
戸籍に登録された全ての6歳以上男女には、身分や性別に応じて口分田(くぶんでん)が与えられます。
その人が死ぬと、口分田は国に返すことになります。これを
班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)と言います。
口分田の面積に応じて租(そ)を負担します。
※租とは収穫量の3%の稲を収める物税です。
一般の良民の成人男子は、布や特産物を都まで運んで納める調・庸(ちょう・よう)の税や、
兵役(へいえき)の義務が課されました。
租は非常時の食料として倉庫に蓄えられました。
調・庸は貴族、役人への給与や朝廷の運営費に使われました。
兵役では、唐や新羅の侵攻に備えるために、九州北部や対馬、壱岐に送られる人がいました。
これらを防人(さきもり)と呼びます。
6歳で田んぼをもらっても・・・、どうやって耕すの?
亡くなったら返すって・・・。一生懸命耕しても、自分の物にならないのはひどいと思います。
そうなんです。律令国家を支えるのは、法でもお金でも、優秀な太政大臣でも国司でもありません。
律令国家を支える一番大切なもの、それは人民です。
その大切にしなければならない人民を、大切にできなかった・・。
6歳の子供が田の管理を行えるわけがありません。
しかし与えられた口分田に応じて、容赦なく租は徴収されます。
仮に父親に6歳以下の子供が4人いたとします。
その4人分の口分田の面倒を父親が見なくてはいけません。
田植えから稲刈り、日々の手入れ全てです。
しかし父親には調・庸(ちょう・よう)の義務があり、都まで税を届けなくてはなりません。
都への旅費も当然自腹です。
時には兵役の義務まであります。
「一体、誰が口分田の面倒を見るの?」
いかに庶民の負担が大きかったかお分かりいただけると思います。
あまりにも負担が大きすぎるが故、口分田を捨て、逃亡する者も出てくる始末でした。
推古天皇や聖徳太子は、そんな国を作ろうとしていたわけじゃないと思う。
反面、貴族は役所で高い地位につき、調・庸や兵役の義務もありません。
その上、高い給与や土地も与えられました。
よりよい政治をしなければならないのが貴族のはずなのに・・・。
奴婢(奴隷)の人々は、人身売買の対象にされました。
また、奴婢同士でしか結婚できずに、生まれた子供も奴婢にしかなれなかったのです。
う~ん、律令国家ってそう言うものなのか。
墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)
班田収授法は、口分田を与えられるとは言え、それは生きている間だけの話です。
どれだけ頑張って良い田を作っても、死ねば国に返さなければなりません。
やる気が出ないな。そんなの。
自分の物のようで自分の物じゃないですもんね。
そこで、723年に、朝廷は三世一身の法を出しました。
開墾した田は本人が生きている間は私有出来ます。
新たに開墾すれば、その田は孫の代(三世)までの私有が認められました。
しかし、あまり効果は上がりませんでした。
孫の代で返すってことは、結局期間が延びただけですもんね。
やっぱりやる気が起きないよ。そんなの。
そこで、743年に、朝廷はこの法を出しました。
墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)です。
新しく開墾した土地(墾田)は、口分田のように租がかかりますが、私有が永遠に認められました。
売買をすることも出来ます。
この背景には、深刻な口分田不足と、農民の開墾意欲の低下がありました。
朝廷は、開墾を進める必要性が出てきたため、墾田の永久私有を認めたのです。
良かったね。農民の人達。
荘園(しょうえん)の誕生
ところが、これにも落とし穴がありました。
新たに開墾して田を作ったものは、その田を永年私有出来ると言う墾田永年私財法
聞こえは良いですが、ただの個人が、新たな田を開墾して行くのは限度がありました。
祖を納めるためには、まず口分田をしっかり耕し良い田にしなければなりません。
その他に調·庸などの義務もあり、兵役の義務もあります。
更に当時の農具もあまり良い物ではありません。
個人が新たに開墾し、田を増やして行くことは、余りにも無理があったのです。
負担が大きすぎるよね。
そうなんです。
代わりに貴族は調·庸の義務がなく、裕福です。
彼らは、人を雇い開墾させ、私有地を広げました。
どんどん貴族だけが裕福になっていくんですね。
さらに、彼ら貴族は寺院の特権である税免除(祖がない)を巧みに利用しました。
どんなこと?
自分が開墾した土地を寺院に、寄付をするのです。
なるほど。寺院の物であれば役人も税は取れませんものね。
けど寄付したら自分の物じゃなくなっちゃうでしょ?
それは表向きです。
実際は自分たち貴族が使うのです。
頭が回るね。
全国規模でこのようなことが起きました。
するとどうなると思います?
朝廷は税収入がなくなってしまうのではと思います。
その通りです。
貴族だけがいい思いをしてるんだね。
こうして、律令国家の根幹を成す公地公民の制は崩壊していくことになるのです。
苦労して、律令国家を作ったのに。
そこで、新たな動きが出てくるのです。
この一部の人間だけが得をするシステムを変えようとする動きが。
またヒーローが登場するんだ!楽しみだね。
墾田永年私財法により、各地に私有地が増えました。私有地の管理のための事務所や倉庫は「荘(しょう)」と呼ばれました。
そのため、貴族や寺院の私有地は「荘園(しょうえん)」と呼ばれるようになったのです。