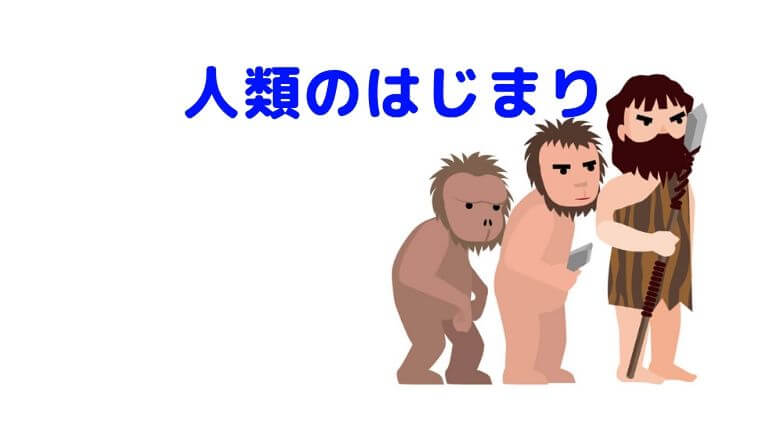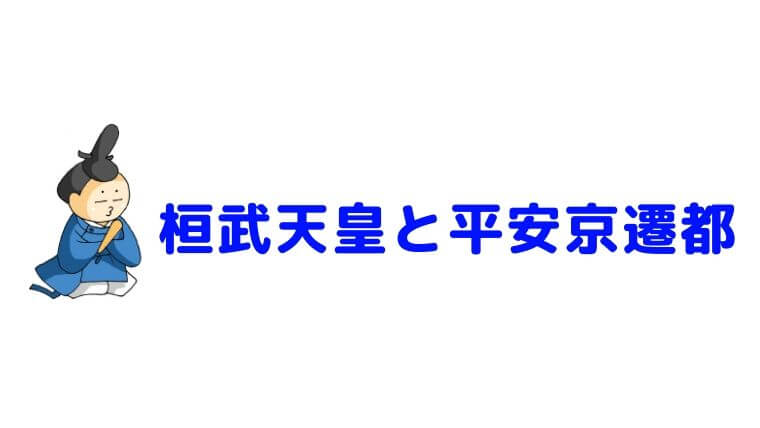大化の改新と律令国家
蘇我氏の独裁
推古天皇、聖徳太子の政治改革(天皇に政治の実権を取り戻す)は、まずまずの成果をあげました。
しかし、相変わらず有力豪族の力は強く、完全に天皇中心とする政治基盤を作るには至りませんでした
相当な力を持った豪族たちをまとめていくのは、とても大変なことだったんでしょうね。
天皇とか王様って、とんでもなく権力があると思ってたけど、苦労してたんだね。
特に蘇我氏の力は相当なものでした。
矢面(やおもて)に立つのは天皇でも、実質的な政治的な力は同等と思ってよいのかもしれませんね。
発言力とか強そうですね。
そうですね。蘇我氏の一言の影響力はかなり大きかったと思います。
やり辛そう(汗)聖徳太子・・・。
でも、蘇我馬子と推古天皇、聖徳太子は協力し合って政治改革を進めた仲ですよね?それがどうして、敵対してしまったんですか?
すぐに敵対と言うわけでもありませんが、馬子は元々聖徳太子を良く思っていなかったと言うのは確かだと思います。
そうなの!?
さらに馬子には華々しい実績があります。
なんだなんだ?
先の物部(もののべ)氏との戦いにおいての勝利の立役者です。
仏教派対神道派の戦いでしたね。
実績十分、天皇との関係も申し分ない馬子が、年齢わずか20歳程度の聖徳太子と対等に扱われることは、不満だったかもしれません。
聖徳太子ってそんなに若かったんだ!?
さらに、聖徳太子は推古天皇の甥(おい)でもあり、摂政と言う立場でもあったので、対等と言うよりは、むしろ聖徳太子主権の体制だったと言えます。
若くて優秀すぎる・・・。それはそれで大変なんですね。
推古天皇はとても賢い方だったようで、馬子と聖徳太子との微妙な関係を上手くコントロールしたようです。
馬子を抑え、主導権は聖徳太子に持たせつつ、改革を進めていったのです。
ますます推古天皇、すごい!
そのような状況でしたから、聖徳太子や推古天皇の死後、蘇我氏の権力は揺るぎないものとなっていきました。
結局元に戻ってしまうんだね。
特に馬子の後、蘇我蝦夷(えみし)、入鹿(いるか)親子の時、蘇我氏の独裁政権は最盛期を迎えることになります。
蘇我氏は、元々天皇家とは外戚ですが、天皇に自分の娘を嫁がせたりして、さらに天皇家との関係を強固なものとしました
大化の改新
聖徳太子生前の頃までは、なんとか足並みを揃えていた大和政権内部もやがてほころびが見え始めます。
蘇我氏としては、目の上のたんこぶが取れた思いだったのでしょうね。
蘇我馬子の後、蝦夷、入鹿親子の天皇無視の態度、次いでは聖徳太子の息子である山背大兄王(やましろおおえのおう)討伐により、蘇我氏の勢いは天皇をしのぐまでになりました。
え!?聖徳太子の子が殺されちゃったの!?
天皇の後継者として有力候補の山背大兄王を討ったことで、蘇我氏の立場は揺るぎないものとなりました。
これらの蘇我氏による独裁政治を良しとしない勢力が現れます。
中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と中臣鎌足(なかとみのかまたり)
です。
中大兄皇子は後の天智天皇です。
聖徳太子とは縁戚にあたります。
中臣氏は、物部氏と共に近畿地方にいた豪族です。
中臣氏は、物部氏と共に先の神道派対仏教派の戦いで蘇我氏に敗北しています。
よって、中臣鎌足にとっては、中大兄皇子を見方につけ、蘇我氏へのリベンジを果たすチャンスが到来したわけです。
ちなみに、中臣鎌足は後の藤原鎌足。
後に栄華を誇る公家藤原一族の始祖です。
とある式典で蝦夷・入鹿親子を暗殺した中大兄皇子は一気に政治改革に着手します。
あ・ん・さ・つ!!
怖い・・。
蝦夷・入鹿の暗殺により、蘇我氏は滅亡することになります。
中大兄皇子らの目指したものは、聖徳太子らの志を受け継いだ
天皇中心の政治体制確立です。
天皇家の宿敵である蘇我氏を滅ぼし、天皇の力が一気に高まります。
これをきっかけに長年の憂いであった、有力豪族の弱体化を図りました。
豪族が有していた土地と人民を、国家が直接支配することに成功しました。
これを公地公民の制(こうちこうみんのせい)と言います。
蘇我氏の滅亡から、公地公民による天皇の権力強化(中央集権化)が進みます。
これら一連の動きを
大化の改新(たいかのかいしん)
と呼びます。
645年のことでした。
「大化」とは、日本で初めて定められた年号です。
律令国家への歩み
ずっと苦労してきた豪族相手に、土地と人民を全て明け渡させるって、よく考えたらすごいことですよね?
やはり蘇我氏の滅亡が大きいですね。
天皇家を脅かす最有力豪族である蘇我氏が討たれ、天皇家には逆らえないと言う気持ちを根付かせたのでしょう。
大化の改新は成功に終わったんですね。
中大兄皇子ってその後どうなったの?ヒーローだよね!?
蘇我氏との戦いに勝利した中大兄皇子ですが、息をつく間もなく、危機が迫ってきました。
どうしたの!?
東アジアに不穏な動きが起きたのです。
不穏な動き?
大化の改新前後の東アジアの情勢について見てみましょう。
7世紀初めには、大国隋が滅び、新たに唐(とう)が中国を統一しました。

その後、唐は新羅と組み、百済を滅ぼし、強国高句麗までも滅ぼしたのです。
百済と日本はとても関係の深い国です。
その百済が滅ぼされたことで、一気に日本には緊張状態が走ることになります。
百済がやられた!?日本は助けなかったの!?
滅亡寸前の百済復興のために、日本は大軍の援軍を送りました。
しかし、唐・新羅連合軍に敗れてしまいます(白村江の戦い)(はくそんこうの戦い)
こののち、新羅は唐の勢力を追い出し、朝鮮半島を統一します。

白村江の戦いに敗れた中大兄皇子は、唐や新羅の攻撃に備えるべく、
西日本の各地に山城を築きました。
防衛の拠点となったのは、九州の大宰府(だざいふ)です。
中大兄皇子は都を滋賀県の大津宮(おおつのみや)に移し、即位します。
天皇になったんだ!!
天智天皇(てんじてんのう)です。
天智天皇は初めて全国の戸籍を作るなど、天皇中心の政治の確立を進めました。
変わりゆく都
天智天皇の没後、皇位継承者をめぐり、争いが起きます。
また戦争か
大友皇子との戦いに勝利し、天武天皇(てんむてんのう)が即位します(壬申の乱※じんしんのらん)
実は、天武天皇は天智天皇の弟、大友皇子は息子です。
弟と息子が争うなんて、天智天皇も天国で心を痛めたでしょうね。
天武天皇は都を飛鳥に戻しました。
その後天皇となった持統天皇は藤原京を造りました。
藤原京は、中国の都にならい、道路によって碁盤の目に区画された、
日本で初めての本格的な都です。
「日本」と言う国号が使われ始めたのもこの頃と考えれれています。

さあ、次は律令(りつりょう)国家の完成です。
いよいよ推古天皇から始まった天皇中心の政治体制が確立する時が近づいてきますよ!