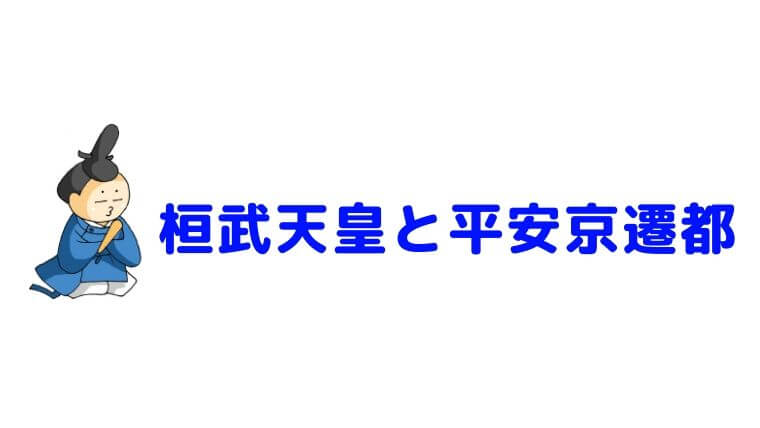貴族と仏教の天平文化
聖武天皇
第45代の聖武天皇が治めていた8世紀前半の文化を天平文化と言います。
余談ですが聖武天皇の父は、律令国家の体制を固めた文武天皇です。
天平文化を、一言で説明するならば、貴族を中心とした仏教文化です。
天平文化は平城京を中心に花開きました。
また、そこには唐の文化の影響が強く見られます。
遣唐使、僧、留学生の往来により、多くの唐の文化が日本の生活に取り入れられていったからです。
東大寺の大仏を造った人ですね。

当時は災害や疫病(えきびょう)に悩まされ、仏教の力で国家を守ろうとしたのです。
それであんなでかい大仏を造ったんだね。
聖武天皇の妻、光明皇后と協力し、国ごとには国分寺と国分尼寺を建てました。
そして奈良の都には東大寺を建てたのです。
それほど深刻だったんでしょうね。疫病も。
ところで、前回「律令制度の仕組み(後編)の中でも話しましたが、743年の墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)により、公地公民の制が崩壊しました。
実はこの墾田永年私財法を出したのは聖武天皇です。
え!?じゃあお父さんの文武天皇が作った律令国家の土台を壊してしまったのは!?
聖武天皇ということになるでしょう。
しかし、単純に聖武天皇に責任を押し付けるのは筋違いだと思います。
問題は、貴族や僧にあらゆる特権を与えていたこの当時の政治体制にあると私は見ています。
僧の特権
どのような特権があったのですか?
既にお話ししたように、寺院は租を納める必要がありませんでしたね。
その他には刑罰を免除されるなど、国からはとても厚く保護されていました。
刑罰!?悪いことしても捕まらないのか!?
ただし、仏教の力で国を守るようにと、強く命じられていたようではあります。
具体的には何をしたのですか?
僧としての務めを果たしてもらうことでしょう。
人々の模範となるような生き方を示すことです。
行基と言う僧は、一般の人々と共に橋や用水路を造る努力をしました。
いい人もいたんだね。
いい人もいれば、悪い人もいるのは世の常です。
僧の特権を欲しがり、勝手に僧を名乗る人間さえ出てきたのです。
え!?そんな簡単にお坊さんってなれるんですか?
いいえなれません。僧になるためには高尚(こうしょう)な僧から戒律(かいりつ)を授かる必要があります。
コーショー?カイリツ?
仏門に生きる者に必要な戒めのことを戒律と言います。
戒律を弟子に与えられる僧は、相当な修行を積んできた(高尚な)者しかなれませんでした。
当時の日本には、戒律を与えられるほど十分な修行を行った僧はいませんでした。
そのため、勝手に僧を名乗るエセ坊主が各地に現れたのです。
聖武天皇はこのような状況を打開するために、唐から偉いお坊さんを招く決断をします。
なんかどの時代も天皇って大変だね。
鑑真(がんじん)
正しき仏教の姿を取り戻そうとする聖武天皇は、唐の鑑真に来日を依頼します。
盲目になりながらも日本に渡航し、正しき仏教の教えを伝えました。
当時の航海は命がけです。
6度目の航海でようやく日本に到着した時には、既に両目を失明していました。
1~5回目は鑑真を慕う弟子たちに阻まれ、航海を断念したようです。
鑑真が初めて日本へ上陸したのは、1回目の試みから起算すると約10年かかっています。
日本の現状を救おうとする鑑真の覚悟は相当なものだったのです。
鑑真が来日し、聖武天皇は厚くもてなしました。
鑑真のために、奈良に唐招提寺(とうしょうだいじ)を建立しました。
聖武天皇も鑑真から戒律を受けています。
エセ坊主やら鑑真さんとか、いろんなお坊さんがいるんだね。
自分の命を捧げてそこまでしてくれるなんて、すごい人だと思います。
鑑真は、生涯を奈良の唐招提寺で終えます。
正しき仏教を伝えたいと言う思いを、最後まで貫いたのです。
遣唐使と天平文化
天平文化は唐文化を色濃く受け継いだ文化です。
これは、遣唐使により日本から唐へ渡る人が増えたことや、留学生を介して唐文化が伝えられたことが要因です。
また、当時の唐はシルクロードの発終着点であり、広くアジア、ヨーロッパの文化が流入してくる地でもありました。
その結果、唐の文化に世界各国の文化も入り混じり、国際色豊かな文化が芽生えたのも天平文化の特色です。
奈良の正倉院には国際色豊かな品々が、聖武天皇の愛用品と共に保管されています。
仏教と優雅な貴族、そして唐の国際色豊かな文化、それらが天平文化の特色です。
そうか。シルクロードと唐はつながってたから、ヨーロッパの品物が日本に入ってきてもおかしくないよね。
ガラス工芸品とかステキ
文学作品も素晴らしいものが生まれています。
文学作品では日本に現存する最古の和歌集である万葉集がまとめられました。712年に古事記、続いて720年には日本書紀が歴史書としてまとめられました。
その他、地方の国ごとに自然、産物、伝統を記した風土記(ふどき)もまとめられました。
芸術だけじゃなく、文学そして国際交流。
天平文化の華々しさが伝わってきますね。
その背景には疫病だったりニセのお坊さんだったり
自分のことしか考えていない貴族だったりなのに。
こんなに素晴らしい天平文化が生まれたのは不思議です。
だからこそ、この文化遺産を大切にしなければなりません。
たくさんの人の苦しみの中に生まれた一筋の光。
それが鑑真であり芸術です。
彼らの功績を大切に後世に残して行く。
それが現代に生きる私達の仕事です。ですから・・・
だからこそ、歴史を学びましょうってことでしょ、先生!
そのとおり!
天平文化と言えば、聖武天皇と仏教。
仏教の力を借りて日本を疫病や災害から守ろうとした聖武天皇。
しかし、余りにも行き過ぎた仏教保護は、ニセの僧を各地に生み出し、国分寺や国分尼寺、東大寺の大仏像の建立に、国家財政の負担が増していきました。
ここから脱仏教色の濃い時代がやってきます。
仏教の地、奈良を離れ新たな都にて新しい時代をスタートさせようとする天皇が現れたのです。
桓武(かんむ)天皇の平安遷都(せんと)です。
次は桓武天皇と平安京のお話しです。
いよいよ舞台は京都に移りますよ。