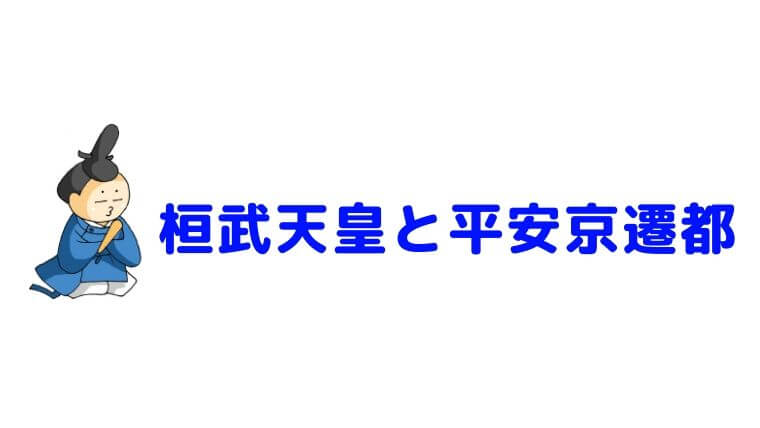摂関政治と国風文化
シルクロードで栄華を誇った唐も徐々に衰え始めました。
そのような中、長く続いた遣唐使を廃止しようと提案した者がいます。
留学生などの往き来も多くなり、唐の文化は彼らにより日本へもたらされるようになったこと。
衰えた唐からはもはや何も得るものがなくなったこと。
それらのことから、航海の危険をおかしてでも遣唐使を派遣するメリットが失われたからです。
遣唐使廃止を申し出たのは
菅原道真(すがわらのみちざね)
です。
894年のことでした。
学問の神様ですね。
そうです。九州の大宰府天満宮(だざいふてんまんぐう)には多くの受験生が祈願に行きます。
何故神様なの?
道真は死後天神となったと言う伝説があるからです。
頭脳明晰で学問の神様として、大宰府天満宮に祀られています。
道真の出世は目覚ましく、太政官の右大臣の役職まで就きました。
当時の第59代宇多天皇が、道真を重く信頼していたこともありますが、朝廷の中での力を増して行く藤原氏の力を抑えると言う意味もありました。
遣唐使廃止を提案し、その案が通るなど道真の発言力の高さが伺い知れます。
しかし、宇多天皇の後、第60代醍醐(だいご)天皇の時に状況は変わります。
道真の出世は貴族の間では嫉妬の的でした。
宇多天皇の後ろ楯をなくし、左大臣の藤原時平の陰謀で地方役人の大宰府務めに左遷(させん)させられます。
そして道真は無念の中、静かに亡くなりました。
道真の死後、京都では不可解なことが起きます。
道真の左遷に加担した者たちが、次々に事故や病で亡くなったのです。
落雷による火災や疫病の流行、作物の凶作など不幸が続きました。
人々は惨めな死を遂げた道真の祟りだと恐れ、道真を天神様として祀るようになりました。
これが大宰府天満宮の由来です。
大宰府天満宮の由来って、悲しいお話なんですね。
Contents
摂関(せっかん)政治
中臣鎌足(なかとみのかまたり)を覚えていますか?
大化の改新で中大兄皇子と協力して蘇我氏を滅ぼした人!
その通りです!中臣鎌足は後の藤原鎌足です。平安時代に栄華を極める藤原一族の始祖です。
藤原氏は自分の娘を積極的に皇室に嫁がせたり、朝廷での立場を強化していきました。
やがて、天皇が幼い時は摂政(せっしょう)として政治を行い、天皇が成人すれば関白(かんぱく)として政治を助ける
摂関政治
を行います。
実質的に藤原氏による独裁が始まりました。
藤原道長
藤原一族の摂関政治は、藤原道長・頼道親子の時に最も安定しました。
「この世をば我が世とぞ思うもち月のかけたることをなしと思えば」
これは藤原道長の詠んだ歌です。
「この世は自分のためにあるようなものだ。この満月のように、私には欠けているものは何もないではないか」
と言う意味です。
道長の権力の強さがよくわかる歌です。
藤原氏は摂関家と言う代名詞がつくほど摂関政治により朝廷を裏で操った一族です。
なぜ藤原氏はそんなに力があったのですか?
先ほどあったように、大化の改新の功労者に藤原鎌足(元は中臣鎌足)がいますね。
その労を認められ、藤原一族は朝廷内でも重要な地位を占めるようになりました。
大化の改新の立役者だもんね。
そこから藤原一族は、皇室へ積極的に関与してきます。
自分の娘を皇室に嫁がせ、その子を次期天皇にするなど、あの手この手で地盤を固めていきます。
女性は、政治の道具なんですね。
いかに天皇の血筋と親戚関係を結ぶかで、朝廷の中での立場は重要になりますからね。
10世紀に入ると、地方の政治は国司に任されるようになりました。
すると、国司は自分の収入を得ることだけを考え、行動しました。
結果的に地方の政治は乱れました。
藤原氏や貴族たちは、国司から多くの贈物をもらい繁栄しました。
国司は権力者に贈り物をすることで、自由に地方で振舞うことが許されたのです。
また同じか・・・。
どうしていつも同じことを繰り返すんでしょうね。
権力とカネ。いつの時代も、これに目がくらんでしまうものです。
しかし、貴族が好き放題出来る時代も、まもなく終わりを迎えることになります。
そうです。武士の時代の幕開けです。
権力とカネ。いつの時代も、これに目がくらんでしまうものです。
しかし、貴族が好き放題出来る時代も、まもなく終わりを迎えることになります。
国風文化
武士の時代に入る前に、とても大切なお話しをしておきましょう。
なんだなんだ?
国風文化のお話しです。
国風文化?
冒頭で、菅原道真による遣唐使の話をしましたね。
唐が衰えてきたから、危険な航海までして遣唐使を続ける必要性がなくなったんですね。
そうです。それまでは仏教をはじめとして、多くの文化が唐から伝わってきました。
遣唐使の廃止により、唐文化の流入がストップすることになります。
思えば漢字とか稲作なんかも全部中国のほうから流れてきたんだもんな。
唐文化が入ってこなくなり、代わりに日本独特の文化が芽生えてきます。
それが国風文化です。
大陸から伝わる文化が薄れ、日本独特の文化が芽生えます。
それが国風文化です。
国風文化は、摂関政治の頃に最も栄えました。
国風文化により、生みだされたものは以下の通りです。
仮名文字(かなもじ)
漢字を変形させて、日本語の発音が出せるように工夫した仮名文字が作られました。
平仮名の原型です。
仮名文字を初めて使用した和歌集に、紀貫之の「古今和歌集」があります。
紫式部「源氏物語」 清少納言「枕草子」
など、女流文学作品が生まれました。
大和絵(やまとえ)
日本の風景や人物を描いた絵です。日本画の基になりました。
十二単(じゅうにひとえ)
色鮮やかな、平安時代を代表する貴族女性の装束です。

平安時代は、末法思想(まっぽうしそう)にあたる時代でした。
末法思想ですか?
仏教の開祖、釈迦(しゃか)がいなくなって2000年後に、釈迦の教えが行き届かなくなり、乱れた世になると言う思想です。
10世紀半ば、次第に社会が乱れ、人々は末法思想に陥り、不安な気持ちが高まって行きました。
阿弥陀如来(あみだにょらい)にすがり、死後、極楽浄土(阿弥陀如来がいる、苦しみのない世界)へ行けることを願う
浄土信仰(じょうどしんこう)
が起こりました。
11世紀には、浄土信仰が人々の間でも広がりました。
阿弥陀如来像やそれを納めた阿弥陀堂が各地に造られました。
京都の宇治には、代表的な阿弥陀堂があります。
それが平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)です。
長らくお疲れさまでした。今日で古代の話は終わりになります。
次は武士か。かっこいい!!
中世のお話しも楽しみです。
と、その前に、世界の四大文明を飛ばしていましたので、次回はいったんそのお話しに戻りますね。