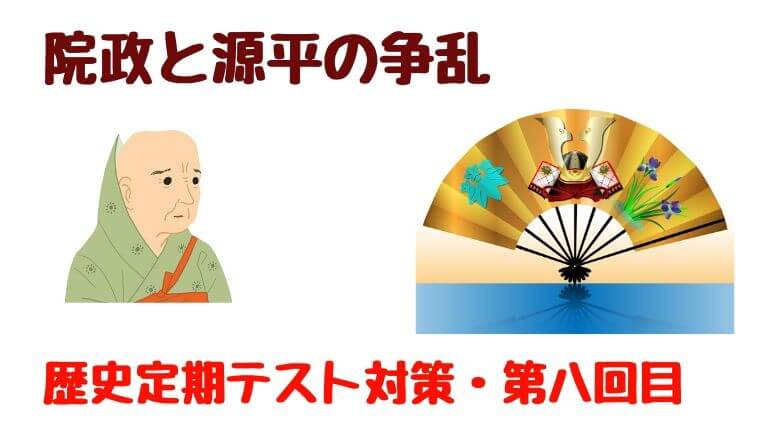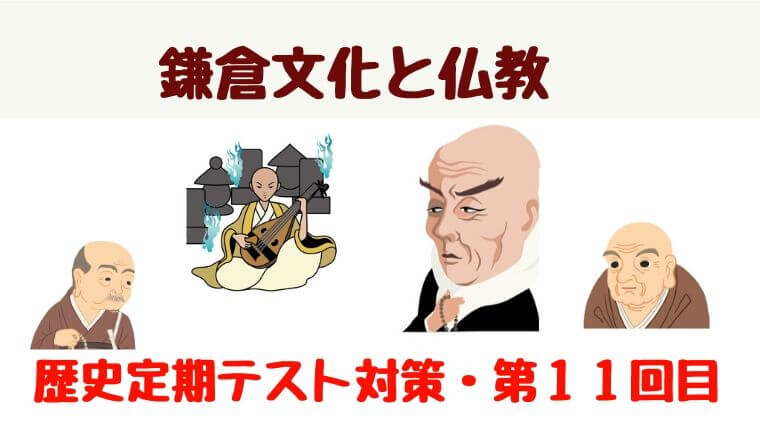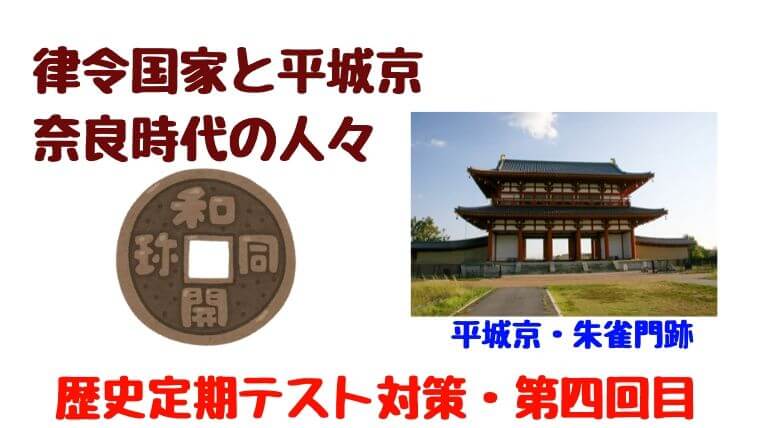江戸時代の厳しい身分制度
Contents
江戸時代の厳しい身分制度
中学歴史定期テスト対策の第25回目です。
教科書は114P~115Pです。
江戸時代の身分と暮らしです。
江戸時代は身分制度が強化された時代です。
どのような身分があり、そしてどのような割合で身分がわかれていたのかを理解しましょう。
江戸時代の武士と町人
身分は豊臣秀吉の政策で明確に定まりました。
農民が武具を奪われ、武士との身分の違いを明確にされたのです。
刀狩(かたながり)だね。
太閤検地(たいこうけんち)も身分の明確化には関わっていますよ。
わかりますか?
えっと、石高(こくだか)が使用されるようになりました。
武士の領地だけ石高で表されるようになりました。
太閤検地(たいこうけんち)により、初めて全国統一の計測方法により、田畑の収穫量を割り出せるようになりました。
この予想される収穫量が、石高(こくだか)です。
単純に石高(こくだか)が多い者が、領地や田畑を多く有していることになります。
そして石高(こくだか)で示されたのは武士の領地です。
それ以外の公家や寺社などといった荘園領主、有力な農民が持っていた土地への複雑な権利が否定されました。
検地帳に登録された農民だけに土地の所有権を認めました。
つまり、武士とその他の身分を明確に分け、農民には耕作に専念させることを実現したものが太閤検地(たいこうけんち)です。
戦国時代は農民も武士も曖昧だったしね。
こうした秀吉の頃に出来上がった身分が、さらに強化されたのが江戸時代の身分制度です。
武士、百姓(ひゃくしょう)、町人に大きく明確化されて事が特徴です。
軍役(ぐんやく)を果たす代わりに、主君からは領地や米を与えられました。
これを俸禄(ほうろく)と言います。
現代で言うお給料です。
名字を持つ権利、帯刀(たいとう)する権利を認められました。
名誉や忠義を重んじる武士道が磨かれました。

町人は幕府や藩に営業を行うための税を収めている者です。
ひとつの町ごとに自治を行いました。
自治とは、自分たちのことは自分たちで決めて行うことです。
町に住む者達の間で守らなければならないルールや取り決めを、自分たちで決めて行いました。
名主(なぬし)が町役人が選ばれて、自治を行いました。
しかし、現代のように町に住むものが皆、会議に参加できるような開かれた組織ではありませんでした。
町の運営に参加できるのは地主や家を持つ者に限られたのです。
江戸時代で、個人で家を持つ者はかなり限られていました。
多くの者は家を借りる借家人として暮らしていたのです。
いかに町の運営に携われる人が、限定されていたかがわかると思います。

百姓は全人口の85%を占めました。
いかに百姓の人数が多かったかわかるでしょう。

村もまた、町と同様に自治を行いました。
町と同様、運営に関われる人間は限られていました。
百姓のうち、有力な本百姓(ほんびゃくしょう)は庄屋(しょうや)や名主(なぬし)、組頭(くみがしら)、百姓代(ひゃくしょうだい)などの村役人となりました。
村役人が村の自治を行いました。
幕府は村の年貢を頼りにしていました。
そこで、村ごとに五人組と呼ばれる制度を作り、犯罪の防止や年貢の納入に連帯責任を負わせました。
文字通り、五人一組ごとのグループにわけ、責任を負わせたのです。
村ではしきたりや寄合(よりあい)で定められたおきてを破る者には、葬式以外は協力しない村八分(むらはちぶ)という罰が行われました。
村八分とは、いわゆる仲間はずれのことです。

江戸時代は百姓の全体に占める割合が85%です。
いかに彼らの納める年貢が、幕府にとって重要であったかがわかりますね。
武士はもっと少ないんですか?
武士は7%、町人は5%です。
100人いたら百姓が85人、武士が7人、町人が5人ということですね。
武士はそんなに少ないの!?意外だな!
それでも100人に満たないですね。
他にはどのような人がいたのですか?
公家や僧侶、そしてえた身分・ひにん身分と呼ばれる身分がありました。
江戸時代の身分差別
えた身分は年貢も納めましたが、死んだ牛馬の解体や雪駄(せった)作りを行いました。
ヒエエ
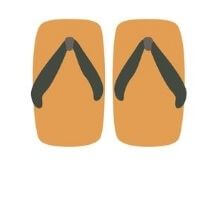
ひにん身分は役人の下働きなどを行いました。
えた身分やひにん身分の人々は、祭りにも参加できないなど、厳しい身分差別の中暮らしていたのです。
ひどい話だね。
江戸時代は特に身分差別が厳しかったのです。
「百姓は酒や茶を飲んでいけない、女は子を産み、夫やその親に従うべし」
などですね。
自分たちは酒飲んで大騒ぎしているのに。
勝手だよね。
女の人だって、家のこと以外にもやりたいことってありますよ。
身分差別と戦い、ようやく個々人の権利が認められてきたのです。
現代の平等社会も、長い歴史の中ではつい最近実現されたものなんですよ。